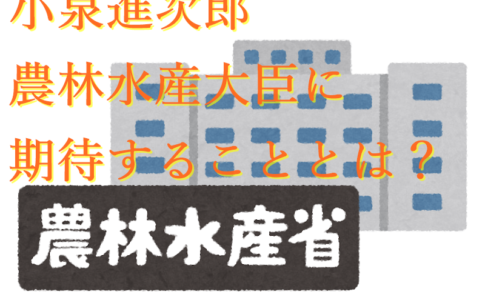2025年の梅雨シーズンが近づいてきましたね!「洗濯物が乾かない…」「お出かけの予定が立てづらい…」など、梅雨ならではの悩みは尽きません。
少しでも快適に過ごすためには、まず「いつから梅雨入りするのか?」を知ることが大切です。
この記事では、日本気象協会などの最新情報をもとに、2025年の全国各地の梅雨入り予想日を詳しくご紹介します。
平年や昨年との比較はもちろん、今年の梅雨の特徴である「陽性梅雨」の可能性や、注意すべき点についても触れています。さらに、梅雨を乗り切るための具体的な対策や豆知識も満載!この記事を参考に、万全の準備で2025年の梅雨を迎えましょう。
2025年の梅雨入りはいつから?【最新予想】
全国の梅雨入り傾向:平年並みか早めの予想
2025年の全体的な傾向
2025年の梅雨入りは、全国的に「平年並み」か「平年より早い」地域が多いと予想されています。
特に、2024年は多くの地域で梅雨入りが6月下旬にずれ込むなど平年より遅かったため、今年はそれと比較すると早く梅雨の季節が訪れると感じられるかもしれません。
気象庁や日本気象協会の発表によると、梅雨をもたらす太平洋高気圧の日本付近への張り出しが平年よりも強まる見込みであることが、この傾向の主な理由として挙げられています。
この高気圧の勢力が強いと、梅雨前線が例年より早く北上しやすくなるためです。
実際に、4月中旬の段階で、将来的に梅雨前線へと発達する可能性のある停滞前線が日本の南の海上で確認されており、季節の歩みが早いことを示唆しています。全体としては、早めの梅雨入りを念頭に置いて準備を進めるのが良さそうです。
平年より早まる可能性のある地域
現時点での予想では、多くの地域で平年並みの梅雨入りが見込まれていますが、一部の報道や気象予報士の見解では、平年よりもやや早まる可能性も指摘されています。
太平洋高気圧の張り出し具合によっては、九州から関東にかけての梅雨入りが平年より数日早まるシナリオも考えられます。
2024年は全国的に梅雨入りが遅れた反動もあり、今年は前線の北上がスムーズに進む可能性が示唆されています。ただし、梅雨入りの時期は、その年の気象条件によって変動が大きいため、一概に「早まる」と断定はできません。
例えば沖縄地方は、平年よりやや遅いか平年並みという予想も出ています。
最終的な梅雨入りの発表は、気象庁が実際の天候の推移を監視して行いますので、今後の最新情報に注意が必要です。

【地域別】2025年梅雨入りいつから?予想日まとめ
ここでは、日本気象協会や各気象予報サービスによる2025年の地域別梅雨入り予想日をまとめました。平年値や昨年の情報と比較しながら見ていきましょう。
沖縄・奄美地方【梅雨入り2025】予想
沖縄の予想日と平年値
日本の梅雨前線は、まず沖縄地方から北上を開始します。
2025年の沖縄地方の梅雨入りは、5月中旬と予想されています。
具体的な日付としては、5月10日ごろや5月17日ごろといった予想が出ています。
平年の沖縄地方の梅雨入りは5月10日ごろですので、2025年は「平年並み」か「平年よりやや遅い」梅雨入りとなりそうです。
昨年2024年は5月21日ごろと平年より11日も遅い梅雨入りでしたので、それと比べると早めのスタートとなりそうです。ただし、沖縄の梅雨は年による変動が大きく、梅雨明けが早まる可能性も指摘されており、その場合は水不足への懸念も出てきます。
奄美の予想日と平年値
沖縄の次に梅雨入りを迎えるのが奄美地方です。
2025年の奄美地方の梅雨入りは、沖縄と同様に5月中旬と予想されています。
具体的な日付としては、5月12日ごろという予想が多く見られます。
奄美地方の平年の梅雨入りは5月12日ごろですので、2025年はほぼ「平年並み」の梅雨入りとなる見込みです。
昨年2024年は沖縄と同じく5月21日ごろと、平年より9日遅い梅雨入りでした。
平年通りであれば、沖縄の梅雨入りから数日後に奄美も梅雨の季節に入る流れとなります。最新の気象情報に注意し、早めの備えを心がけましょう。
九州地方(南部・北部)【梅雨入り2025】予想
九州南部の予想日と平年値
奄美地方に続き、梅雨前線は九州南部へと北上します。
2025年の九州南部の梅雨入りは、5月下旬と予想されています。
具体的な日付としては、5月30日ごろという予想が複数の情報源で見られます。
九州南部の平年の梅雨入りは5月30日ごろですので、2025年は「平年並み」のタイミングでの梅雨入りとなりそうです。
昨年2024年は6月8日ごろと平年より9日遅い梅雨入りでした。
平年通りであれば、5月の終わりには九州南部で雨の季節が始まることになります。本格的な梅雨シーズンを前に、雨具の準備や側溝の掃除など、早めの対策を始めましょう。
九州北部の予想日と平年値
九州南部から少し遅れて、九州北部も梅雨入りを迎えます。
2025年の九州北部の梅雨入りは、6月上旬と予想されています。
具体的な日付としては、6月4日ごろという予想が多く出ています。
九州北部の平年の梅雨入りは6月4日ごろですので、2025年は九州南部と同様に「平年並み」のタイミングでの梅雨入りとなる見込みです。
昨年2024年は6月17日ごろと、平年より13日も遅い梅雨入りでした。九州北部にお住まいの方は、6月に入る頃には梅雨入りを意識し、大雨への備えなども確認しておくと安心です。
四国・中国地方【梅雨入り2025】予想
四国の予想日と平年値
九州北部とほぼ同時期に、四国地方も梅雨入りします。
2025年の四国地方の梅雨入りは、6月上旬と予想されています。
具体的な日付としては、6月5日ごろという予想が多く見られます。
四国地方の平年の梅雨入りは6月5日ごろですので、こちらも「平年並み」のスタートとなりそうです。昨年2024年は6月9日ごろまたは6月17日ごろ、6月22日ごろと情報源により差がありますが、いずれにしても平年より遅い梅雨入りでした。
四国地方は梅雨末期に豪雨に見舞われることも多いため、早めの情報収集と対策が重要です。
中国地方の予想日と平年値
四国地方に続き、中国地方も梅雨の季節を迎えます。
2025年の中国地方の梅雨入りは、6月上旬と予想されています。
具体的な日付としては、6月6日ごろという予想が多く出ています。
中国地方の平年の梅雨入りは6月6日ごろですので、四国地方と同様に「平年並み」のタイミングでの梅雨入りとなりそうです。
昨年2024年は6月20日ごろや6月22日ごろと、平年より2週間ほど遅い梅雨入りでした。中国地方も地形的に大雨による災害リスクがある地域です。ハザードマップの確認など、事前の備えを怠らないようにしましょう。
近畿・東海地方【梅雨入り2025】予想
近畿の予想日と平年値
西日本の中部、近畿地方の梅雨入りも間近です。
2025年の近畿地方の梅雨入りは、6月上旬と予想されています。
具体的な日付としては、中国地方と同じく6月6日ごろという予想が多く見られます。
近畿地方の平年の梅雨入りは6月6日ごろですので、こちらも「平年並み」のスタートとなる見込みです。
昨年2024年は6月17日ごろや6月21日ごろと、平年より10日以上遅い梅雨入りでした。近畿地方も都市部での内水氾濫や、山間部での土砂災害などに注意が必要です。最新の気象情報に常に注意を払いましょう。
東海の予想日と平年値
近畿地方とほぼ時を同じくして、東海地方も梅雨入りします。
2025年の東海地方の梅雨入りは、6月上旬と予想されています。
具体的な日付としては、近畿地方と同じく6月6日ごろという予想が多く出ています。
東海地方の平年の梅雨入りも6月6日ごろですので、2025年は「平年並み」のタイミングでの梅雨入りとなりそうです。
昨年2024年は6月21日ごろと、平年より2週間以上遅い梅雨入りでした。東海地方は太平洋からの湿った空気が流れ込みやすく、大雨になりやすい地域でもあります。早めの対策と情報確認を心がけてください。
関東甲信地方【梅雨入り2025】予想
関東甲信の予想日と平年値
いよいよ首都圏を含む関東甲信地方の梅雨入りです。
2025年の関東甲信地方の梅雨入りは、6月上旬と予想されています。
具体的な日付としては、6月7日ごろという予想が多く見られます。
関東甲信地方の平年の梅雨入りは6月7日ごろですので、こちらも「平年並み」のスタートとなる見込みです。
昨年2024年は6月21日ごろと、平年よりちょうど2週間遅い梅雨入りでした。関東甲信地方は人口も多く、交通機関への影響なども大きいため、梅雨入り情報は特に注目されます。通勤・通学の準備なども早めに進めましょう。
【東京 梅雨入り 2025】日本気象協会
関東甲信地方に含まれる東京の梅雨入りも、基本的には関東甲信地方の発表に準じます。
日本気象協会によりますと、2025年の東京の梅雨入りは、6月7日ごろと予想されています。
これは平年の6月上旬と比べてほぼ同じタイミングです。
昨年2024年の関東甲信地方の梅雨入りが6月21日ごろだったことを考えると、今年は2週間ほど早い梅雨の訪れとなりそうです。
都心部ではゲリラ豪雨による都市型水害のリスクもあります。側溝や排水溝の点検、そして日々の天気予報のチェックを欠かさず行い、急な大雨にも対応できるよう備えておくことが重要です。折りたたみ傘の携帯なども習慣づけましょう。
北陸・東北地方【梅雨入り2025】予想
北陸の予想日と平年値
本州の日本海側に位置する北陸地方の梅雨入りは、他の地域より少し遅めになります。
2025年の北陸地方の梅雨入りは、6月中旬と予想されています。
具体的な日付としては、6月11日ごろという予想が多く見られます。
北陸地方の平年の梅雨入りは6月11日ごろですので、こちらも「平年並み」のタイミングとなりそうです。
昨年2024年は6月22日ごろと、平年より11日遅い梅雨入りでした。北陸地方も梅雨末期には大雨となることがあります。最新の予報を確認し、必要な備えを進めてください。
【2025】東北南部・北部の予想日と平年値
梅雨前線の北上は、最後に東北地方へと到達します。
2025年の東北地方の梅雨入りは、南部・北部ともに6月中旬と予想されています。
具体的な日付としては、東北南部が6月12日ごろ、東北北部が6月15日ごろという予想が出ています。
東北南部の平年の梅雨入りは6月12日ごろ、東北北部は6月15日ごろですので、いずれも「平年並み」の梅雨入りとなる見込みです。
昨年2024年は、南部・北部ともに6月23日ごろと、平年より10日前後遅い梅雨入りでした。東北地方の梅雨は「やませ」の影響を受けることもあり、年によって様相が異なります。今後の情報に注意しましょう。
【今年の梅雨の特徴2025】今年の梅雨は雨が少ない?
今年の梅雨は雨が少ないですか?
今年の梅雨は、地域によって雨の量が異なる見込みです。沖縄や奄美地方では平年並みか少ない雨量が予想されていますが、九州南部から東北北部にかけては平年並みか多い雨量となる見通しです。したがって、「全国的に雨が少ない」とは言えず、特に本州以北では例年通りか多めの雨が降る可能性があります。
予想される梅雨の特徴:「陽性梅雨」に注意?
陽性梅雨とは?
2025年の梅雨は、「陽性梅雨(ようせいつゆ)」となる可能性が指摘されています。
陽性梅雨とは・・・梅雨期間中の気温が平年よりも高く、蒸し暑い日が続くタイプの梅雨を指します。
シベリア方面からの冷たいオホーツク海高気圧の勢力が弱く、南からの暖かく湿った空気を持つ太平洋高気圧の勢力が強い場合に起こりやすいとされています。
雨の降り方としては、しとしとと長時間降り続く「陰性梅雨」とは対照的に、晴れ間が見られる日もある一方で、降る時には短時間で激しい雨(ゲリラ豪雨など)が降ることが多くなる傾向があります。
近年、梅雨寒と呼ばれるような肌寒い日が少なくなり、この陽性梅雨の傾向が強まっていると言われています。
蒸し暑さと激しい雨への警戒
陽性梅雨の年には、特に注意したい点が二つあります。
一つは「蒸し暑さ」です。
気温が高く湿度も高いため、不快指数が上がりやすく、熱中症のリスクが高まります。
室内ではエアコンの除湿機能を活用したり、こまめな水分補給を心がけたりするなど、体調管理が重要になります。
もう一つは「激しい雨」への警戒です。
梅雨前線の活動が活発になると、線状降水帯が発生するなどして、局地的に非常に激しい雨が降り、短時間で河川の増水や土砂災害、都市部での浸水などの災害を引き起こす可能性があります。
特に梅雨末期には大雨のリスクが高まるため、最新の気象情報や自治体からの避難情報に常に注意を払い、危険を感じたら早めに安全な場所へ避難することが大切です。
【2025】降水量の傾向:地域による違い
雨量が多くなる可能性のある地域
2025年の梅雨期間中の降水量は、地域によって傾向が異なると予想されています。
沖縄地方では「かなり多く」、奄美地方、中国地方、近畿地方、東海地方、関東甲信地方でも「平年より多くなる」可能性が示唆されています。
これは、太平洋高気圧の張り出しが強く、南からの暖かく湿った空気が流れ込みやすいため、梅雨前線の活動が活発になることが予想されるためです。
雨量が多くなると、河川の氾濫や土砂災害のリスクが高まります。特に、梅雨末期には集中豪雨が発生しやすいため、普段からハザードマップを確認し、避難経路や避難場所を把握しておくことが重要です。

【2025】梅雨シーズン到来!今からできる備えと対策
早めの準備が肝心!おすすめ梅雨対策グッズ
傘やレインコートの選び方
梅雨の必須アイテムといえば、傘やレインコートです。いざという時に壊れていたり、撥水性が落ちていたりしないか、早めにチェックしておきましょう。
傘は、風が強い日でも壊れにくい耐風骨のものや、ワンタッチで開閉できるものが便利です。また、カバンに入れて持ち歩くなら軽量コンパクトな折りたたみ傘が必須ですが、常に携帯することを考えると、置き傘として丈夫な長傘も用意しておくと安心です。
レインコートやレインウェアは、自転車に乗る方や、傘だけでは濡れてしまうような活動をする際に役立ちます。選ぶ際は、防水性だけでなく、衣服内の蒸れを逃がす透湿性にも注目しましょう。最近ではデザイン性の高いものも増えているので、お気に入りの一着を見つけて、雨の日のお出かけを少しでも快適にしたいですね。
室内干し対策と除湿アイテム
梅雨時期の悩みの種が洗濯物です。
外に干せず室内干しが続くと、生乾きの嫌な臭いが発生しやすくなります。対策としては、まず洗濯槽自体をきれいに保つことが大切です。定期的な洗濯槽クリーナーの使用をおすすめします。
干す際は、扇風機やサーキュレーターで風を当てて、できるだけ早く乾かす工夫をしましょう。
アーチ干し(長いものを両端、短いものを中央に干す)や、衣類同士の間隔を空けることも効果的です。さらに、除湿機やエアコンの除湿(ドライ)機能、浴室乾燥機などを活用するのも良いでしょう。
部屋の湿度を下げることは、カビの発生を抑えることにも繋がります。クローゼットや押し入れには、置き型の除湿剤や吊り下げタイプの除湿剤を活用するのもおすすめです。
大雨・災害への備え:ハザードマップ確認と避難準備
ハザードマップの重要性
梅雨の時期は、大雨による洪水や土砂災害のリスクが高まります。
自分の住んでいる地域や勤務先、よく行く場所などにどのような危険があるのかを事前に知っておくことが、命を守る行動につながります。
そのために役立つのが「ハザードマップ」です。
ハザードマップは、お住まいの自治体のウェブサイトや窓口で入手できます。洪水で浸水が想定される区域、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)の危険箇所などが地図上に示されています。
自宅や周辺地域にどのようなリスクがあるのか、浸水の深さはどれくらいか、土砂災害警戒区域に含まれていないかなどを、梅雨入り前に必ず確認しておきましょう。いざという時に慌てないためにも、事前の情報収集が非常に重要です。
避難場所と経路の確認
ハザードマップで自宅周辺のリスクを確認したら、次にやるべきことは、安全な避難場所とそこまでの避難経路を確認することです。
自治体が指定する避難所(学校や公民館など)の場所だけでなく、その場所が自宅のリスク(洪水、土砂災害など)に対して安全かどうかを確認しましょう。場合によっては、より安全な親戚や知人の家、高層階の頑丈な建物なども避難先として考えておく(垂直避難)ことも有効です。
また、避難場所までの経路も重要です。
複数の経路を確認し、どの道が浸水しやすいか、土砂災害の危険がないかなどを考慮しておきましょう。実際に歩いてみて、危険な箇所がないか確認しておくのも良いでしょう。非常持ち出し袋の準備と合わせて、家族で避難場所や連絡方法について話し合っておくことも大切です。
体調管理のポイント:蒸し暑さ対策と健康維持
湿度管理とカビ対策
梅雨時期は湿度が高くなり、カビが発生しやすい環境になります。
カビは見た目が不快なだけでなく、アレルギーの原因になったり、喘息を悪化させたりすることもあります。健康を維持するためにも、室内の湿度管理とカビ対策は重要です。エアコンの除湿機能や除湿機を適切に使い、湿度を60%以下に保つことを目指しましょう。
換気も大切ですが、雨の日に窓を開けると逆に湿気を呼び込んでしまうこともあるため、換気扇を活用したり、晴れ間を狙って短時間で効率よく換気したりする工夫が必要です。特に水回り(キッチン、浴室、洗面所)や、クローゼット、押し入れ、窓際はカビが生えやすい場所なので、こまめな掃除と乾燥を心がけましょう。
食中毒予防と体調管理
高温多湿な梅雨の時期は、細菌が繁殖しやすく、食中毒のリスクが高まります。
食品の取り扱いには十分注意が必要です。調理前後の手洗いを徹底し、まな板や包丁などの調理器具は清潔に保ちましょう。
食材は十分に加熱し、作り置きした料理は冷蔵庫で保存し、早めに食べきるようにしましょう。お弁当なども傷みやすいため、保冷剤を入れるなどの工夫が必要です。また、梅雨時期は気圧の変化や日照不足、蒸し暑さなどから、だるさや頭痛、気分の落ち込みなど、心身の不調を感じやすくなる人もいます。
「梅雨だる」とも呼ばれるこれらの症状を予防・軽減するためには、規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけることが大切です。
【2025】梅雨に関する豆知識
「梅雨入り」「入梅」の違いとは?
気象庁が発表する「梅雨入り」
私たちが普段ニュースなどで耳にする「梅雨入り」は、気象庁が発表するものです。
これは、実際の天候の状況に基づいて判断されます。具体的には、「曇りや雨の日が多くなり始める時期」を指し、前後5日間程度の移り変わり期間の中日を「梅雨入り日」として、後日確定値として発表されます。
つまり、「梅雨入り宣言」があった日がそのまま梅雨入りの日になるわけではなく、あくまで速報値としての発表です。この気象庁が発表する「梅雨入り」は、その年の気象条件によって毎年日付が異なり、地域によっても時期が異なります。私たちの生活に直接関わる雨の季節の始まりを示す指標として、広く用いられています。
暦の上の季節の節目「入梅」
一方、「入梅(にゅうばい)」という言葉もあります。
これは、二十四節気や雑節といった、古くから使われている暦の上での季節の節目の一つです。太陽の黄経(太陽が天球上の黄道を通る角度)が80度に達する日とされており、毎年日付がほぼ決まっています。
2025年の「入梅」は6月11日(水)です。
昔の農作業において、田植えの時期の目安として使われてきました。気象現象としての「梅雨入り」とは異なり、実際の天候とは必ずしも一致しません。例えば、2025年の関東甲信地方の梅雨入り予想は6月7日ごろであり、「入梅」の6月11日よりも早くなっています。
このように、「梅雨入り」と「入梅」は意味合いが異なる点に注意が必要です。
北海道に梅雨はない?
気象学的な定義と北海道の気候
よく「北海道には梅雨がない」と言われますが、これは気象庁が北海道に対して「梅雨入り」「梅雨明け」の発表を行っていないためです。
気象学的に見ると、梅雨は、本州付近に停滞する梅雨前線によってもたらされる長雨の期間を指します。
梅雨前線は、南の暖かく湿った空気(太平洋高気圧)と北の冷たく湿った空気(オホーツク海高気圧)がぶつかる境界に形成されます。通常、梅雨前線は日本列島を南から北へとゆっくり北上しますが、北海道付近まで北上する頃には勢力が弱まったり、性質が変わったりすることが多く、本州のような明瞭な梅雨の期間が現れにくいのです。
そのため、気象庁は北海道の梅雨入り・明けを特定していないのです。
蝦夷梅雨 2025
2025年の蝦夷梅雨は、5月下旬~6月上旬にかけて発生する見込みです。
この北海道特有の現象は、梅雨前線が北海道付近に停滞し、長雨や曇りの日が続くことが特徴です。
オホーツク海高気圧の張り出しと梅雨前線の北上により、10~14日程度の小雨や霧雨が続く傾向。本州の梅雨より期間が短く、降水量も少ないようです。今年は7年連続の猛暑が予測され、高温と多雨が予想されています。
北海道では気象庁が公式に梅雨入り・梅雨明けを発表していませんが、天気図でオホーツク海高気圧や前線の動向をチェックすることで蝦夷梅雨の傾向を把握できます。2023年には網走で1時間93mmの記録的大雨を観測したケースもあり、局地的な大雨への警戒も必要です。
「蝦夷梅雨」と呼ばれる現象
気象庁の公式な発表はないものの、北海道でも6月下旬から7月上旬にかけて、ぐずついた天気が続くことがあります。
これを俗に「蝦夷梅雨(えぞつゆ)」と呼ぶことがあります。
これは、本州の梅雨末期に北上してきた梅雨前線の影響を受けたり、オホーツク海高気圧からの冷たく湿った気流(やませ)の影響を受けたりして、低温で日照不足、霧雨や小雨が続くような天候になる現象です。
本州の梅雨のように高温多湿で大雨が降るのとは少し様相が異なりますが、農作物への影響が出ることもあります。したがって、「梅雨がない」からといって、この時期に全く雨が降らないわけではなく、長雨に対する注意は必要です。

梅雨明け予想と夏の天気
各地の梅雨明け予想時期
梅雨入りがあれば、梅雨明けもあります。
2025年の梅雨明け時期については、まだ具体的な予想は出ていませんが、平年の梅雨明け時期は以下のようになっています。
-
沖縄地方: 6月21日ごろ 奄美地方: 6月29日ごろ
-
九州南部: 7月15日ごろ 九州北部: 7月19日ごろ
-
四国地方: 7月17日ごろ 中国地方: 7月19日ごろ
-
近畿地方: 7月19日ごろ
-
東海地方: 7月19日ごろ
-
関東甲信地方: 7月19日ごろ
-
北陸地方: 7月23日ごろ
-
東北南部: 7月24日ごろ 東北北部: 7月28日ごろ
2025年は梅雨入りが平年並みか早い傾向にあるため、梅雨明けも平年より早まる可能性があると指摘されています。
ただし、梅雨明けの時期も年によって変動が大きいため、今後の気象情報に注目が必要です。
梅雨明け後の猛暑予測
梅雨が明けると、いよいよ本格的な夏の到来です。
2025年の夏は、梅雨明け後、全国的に厳しい暑さ、いわゆる「猛暑」になる可能性が高いと予測されています。
これは、梅雨をもたらした太平洋高気圧が、梅雨明け後も日本列島を覆い続けるためと考えられます。近年、夏の猛暑は常態化しつつあり、「冷夏」という言葉は聞かれなくなりました。
2024年も記録的な猛暑となりましたが、2025年も同様に厳しい暑さになる可能性があるため、早めの暑さ対策が重要です。エアコンの試運転やフィルター掃除、日傘や帽子の準備、熱中症対策グッズの用意など、梅雨の時期から夏の暑さに備えておきましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1: 2025年の梅雨入りは、結局平年と比べてどうなりそうですか?
A1: 2025年の梅雨入りは、多くの地域で「平年並み」と予想されています。沖縄・奄美地方は「平年並みか遅い」、九州から関東甲信にかけては「平年並み」、北陸・東北地方は「平年並みか遅い」というのが日本気象協会の見解です(2025年4月24日発表時点)。ただし、一部の予報では「平年より早い」可能性も指摘されており、昨年2024年の記録的な遅い梅雨入りと比較すると、今年は早く感じられるでしょう。
Q2: 「陽性梅雨」って何ですか?注意点は?
A2: 「陽性梅雨」とは、梅雨期間中の気温が平年より高く、蒸し暑い日が続くタイプの梅雨のことです。雨はしとしと降り続くのではなく、短時間で激しく降る傾向があります。注意点としては、①高温多湿による熱中症リスクの上昇、②局地的な大雨やゲリラ豪雨による浸水・土砂災害のリスクが挙げられます。体調管理と防災意識をいつも以上に高めることが大切です。
Q3: 梅雨の時期、洗濯物はどう干すのがおすすめですか?
A3: 梅雨時期の洗濯物は、室内干しが基本になります。生乾き臭を防ぐためには、①洗濯槽を清潔に保つ、②洗濯物を溜め込まずこまめに洗う、③扇風機やサーキュレーターで風を当てて早く乾かす、④衣類同士の間隔を空けて干す(アーチ干しなど)、⑤除湿機やエアコンの除湿機能を活用する、といった工夫が有効です。部屋干し用の洗剤を使うのも良いでしょう。
【2025】梅雨入りはいつ?《総括》
「2025年の梅雨入りはいつ?」その答えは「多くの地域で平年並み」となりそうです。
最新の予想では、沖縄・奄美は5月中旬、九州南部は5月下旬、本州の大部分(九州北部~関東甲信)は6月上旬、北陸・東北は6月中旬に梅雨入りする見込みです。昨年が記録的な遅さだったため、今年は「早まった」と感じるかもしれませんが、平年通りと考えられます。
ただし、単に時期だけでなく、梅雨の「質」にも注意が必要です。
今年は「陽性梅雨」の傾向が強く、蒸し暑さと激しい雨が特徴となりそうです。しとしと降る雨ではなく、ザーッと降るゲリラ豪雨のような雨が増えるかもしれません。
熱中症対策はもちろん、短時間での河川増水や土砂災害への警戒が不可欠です。お住まいの地域のハザードマップを確認し、万が一の際の避難行動を考えておきましょう。
梅雨を少しでも快適に過ごすためには、事前の準備が鍵となります。
基本的な雨具のチェックに加え、室内干しの工夫(サーキュレーター活用など)や除湿機の導入、カビ対策、食中毒予防を心がけましょう。また、気圧の変化などで体調を崩しやすい時期でもあるため、規則正しい生活で乗り切りましょう。
この記事で紹介した地域別の予想日や梅雨の特徴、対策を参考に、2025年の梅雨シーズンに備えてください。最新情報は気象庁などの発表をこまめにチェックすることをお忘れなく。梅雨明け後の猛暑も見据え、早め早めの対策で、安全・快適に過ごしましょう。