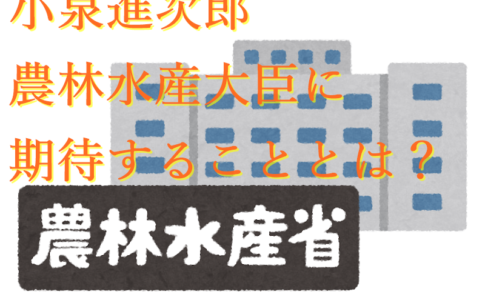2025年参議院選挙の比例代表選挙で、政界に大きな変化の兆しが見えています。
各社の世論調査では自民党が首位を維持しているものの、前回から大幅な議席減が予想され、一方で参政党が急伸して2位に浮上する勢いを見せています。
物価高対策への関心が高まる中、消費税減税への支持が7割を超え、有権者の政策重視の姿勢が鮮明になっています。
未定層が2割存在する流動的な情勢の中、投票率の動向が最終的な議席配分を左右する重要な要因となっています。
こちらの記事では、最新の2025年参議院選【全国比例区】情勢調査を更新しならお伝えします。
2025年参議院選【全国比例区】7月7日情勢調査
2025年7月5~6日実施の主要世論調査をまとめると、自民党が依然トップを維持しつつも調査機関間で支持率に開きが見られる一方、参政党が大きく伸長し2位前後に浮上しています。
無党派層の高止まりも目立ち、終盤の動向次第で議席配分に大きな変化が生じる可能性が高いと言えるでしょう。
2025年参議院選【全国比例区】各社世論調査結果
| 調査機関 | 自民党 | 立憲民主党 | 国民民主党 | 参政党 | 公明党 | 維新の会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANN(テレビ朝日系) | 23.6% | 11.0% | 非公表 | 6.3% | 5.6% | 4.2% |
| 共同通信トレンド調査 | 18.2% | 6.6% | 6.8% | 8.1% | ― | ― |
※ANNは「投票先未定」19%、「わからない・答えない」14.9%、共同通信は非公表
2025年参議院選【全国比例区】支持率の特徴と論点
自民党
-
ANNでは23.6%と高位を維持しつつ、共同通信では18.2%と大幅下落。調査手法差が示すように、支持基盤は固まる一方で無党派層への浸透力には課題が残ります。
参政党
-
ANNの6.3%から共同通信の8.1%へと大幅増。SNSを活用した若年層への訴求が奏功し、序盤情勢から台風の目に躍進している。
野党主要3党
-
立憲民主党は11.0→6.6%へと調査間で差が大きく、支持の安定化が課題。
-
国民民主党は6.8%と堅調に伸長し、若年層支持を背景に倍増議席の公算大。
-
公明党・維新の会はいずれも5%前後で足踏み。党勢維持には組織動員力や地域戦略が鍵。
2025年参議院選【全国比例区】世論動向の行方を左右する要因
-
未定層の動向:約20%が依然未定。最後の1週間での党派・候補者アプローチが勝敗を分ける。
-
物価高対策:ANN調査で「消費税減税」57%対「現金給付」19%。政策争点化で票の行方が変動しやすい。
-
期日前投票・デジタル戦略:SNS動員に長けた参政党・れいわ新選組の勢いが継続するか注目。日本保守党にも新たな波が予想されます。
2025年参議院選【全国比例区】議席予測への示唆
序盤調査ベースの支持率を改選50議席に当てはめると、以下が概算議席範囲となります。
| 政党 | 支持率帯間 | 議席レンジ(概算) |
|---|---|---|
| 自民党 | 18~24% | 14~17 |
| 立憲民主党 | 6~11% | 6~9 |
| 国民民主党 | 6~7% | 5~7 |
| 参政党 | 6~8% | 5~8 |
| 公明党 | 5~6% | 5–6 |
| 維新の会 | 4~5% | 2–4 |
| れいわ新選組 | 2–4% | 2–4 |
| 共産党 | 2–4% | 2–4 |
| 日本保守党 | 1–2% | 1–2 |
与党(自民+公明)は合計約19~23議席にとどまり、改選過半数25議席確保は微妙。野党勢力と新興政党の伸長次第で勢力図が大きく動く。
2025年参議院選【全国比例区】今後の注目ポイント
-
終盤の支持固め:自民党の「比例一本化」と参政党のデジタル動員の成果度合い。
-
未定層の取り込み:主要各党の最終票読みと期日前投票動向。
-
政策争点の変化:物価高対策や外交安全保障など、終盤で争点再定義が起こるか。
自民党首位は確実視されるものの支持率に揺らぎがあり、新興勢力の躍進と未定層の高止まりが終盤の鍵を握る。今後1週間の情勢変化が最終的な議席配分を左右することになるでしょう。
2025年参議院選挙比例区の情勢調査
各社世論調査の結果比較
2025年7月上旬に実施された各社の世論調査では、自民党が依然として首位を維持しているものの、調査機関によって大きな差異が見られる状況となっています。
テレビ朝日系ANN調査では自民党が23.6%で圧倒的な支持を集める一方、共同通信のトレンド調査では18.2%と5ポイント以上の差が生じています。この差は調査手法や対象者の違いによるものですが、有権者の投票先が流動的であることを示しています。
特に注目すべきは参政党の急伸で、共同通信調査では8.1%で2位に浮上し、立憲民主党の6.6%を上回る結果となりました。
これは前回調査から2.3ポイントの大幅な伸びを示しており、新興勢力の台頭が既存政党の勢力図を大きく変える可能性を示唆しています。
政党別支持率の動向分析
自民党は各調査で首位を維持しているものの、支持基盤の固め切れていない状況が浮き彫りになっています。読売新聞の調査では、自民党支持層の7割強は固めているものの、内閣支持率の低迷により一部票が他党に流出している実態が明らかになっています。
立憲民主党は前回選挙並みの議席確保を目指していますが、ANN調査の11.0%から共同通信調査の6.6%まで大きな幅があり、安定した支持基盤の構築に課題を抱えています。無党派層の政権批判票を取り込む戦略を展開していますが、参政党の台頭により票の奪い合いが激化しています。
国民民主党は若年層を中心に支持を拡大しており、前回3議席から6議席程度への倍増が視野に入っています。18~39歳の層で2割強の支持を得ており、世代交代への期待が高まっています。
2025年参議院選【全国比例区】主要政党の議席予測と戦略
与党(自民・公明)の現状と課題
自民党は比例代表で前回2022年の18議席から大幅減の16議席前後にとどまる見通しです。日本経済新聞の情勢調査では、改選19議席の確保は困難で、過去最低の2010年に記録した12議席と同水準まで落ち込む可能性も指摘されています。
この背景には、内閣支持率25%台という低水準があり、政権への不信が比例票の減少に直結している状況があります。自民党は終盤戦で支持層の「比例一本化」を図る戦略を展開していますが、新興政党への票流出を完全に防ぐのは困難な情勢です。
公明党は前回6議席から5~6議席と歴史的最低水準が瀬戸際となっています。1983年以降の現行制度下で6議席を下回ったことがなく、組織票の動員力が最終結果を左右する重要な要素となっています。
野党各党の勢力図変化
立憲民主党は前回並みの7~9議席を確保する公算が高く、野党第一党としての地位は維持する見通しです。政権批判票の受け皿として一定の役割を果たしていますが、参政党の台頭により無党派層の票を奪われる懸念があります。
国民民主党は最も勢いのある政党の一つで、前回3議席から6議席前後への倍増が確実視されています。玉木雄一郎代表の積極的な政策提言と、若年層への訴求力が功を奏している状況です。
日本維新の会は関西以外での伸び悩みが顕著で、前回4議席から2~4議席と半減ペースとなっています。全国政党としての浸透に課題を抱えており、地域政党からの脱却が急務となっています。
新興政党の台頭と影響
参政党が今回選挙の最大の台風の目となっています。前回1議席から5~8議席への大幅増が見込まれ、共同通信調査では比例2位に浮上する勢いを見せています。
ネット世論を背景とした急伸が特徴で、SNSを活用した情報発信と若年層への訴求が効果を上げています。参政党の票が伸びる場合、比例名簿上位の著名候補の大量当選が現実味を帯びており、既存政党の議席配分に大きな影響を与える可能性があります。
日本保守党も1~2議席をうかがう勢いで、保守系新興勢力の台頭が政界再編の引き金となる可能性があります。公明党の組織票と競合する関係にあり、与党の議席確保戦略に影響を与える要因となっています。

2025年参議院選【全国比例区】有権者の投票行動と世論動向
未定層の動向と流動性
各調査で「未定層が10~20%存在する」ことが、今回選挙の大きな特徴となっています。
ANN調査では「投票先を決めていない」が19.0%、「わからない・答えない」が14.9%と高水準で、今後の動向変化余地が非常に大きい状況です。
この未定層の動向が最終的な議席配分を大きく左右する可能性があり、各党は終盤戦での訴求力強化に全力を挙げています。特に無党派層の動向が注目され、「与党過半数割れ望む」が49.9%に達している状況は、政権批判票の行方を左右する重要な指標となっています。
争点別世論調査結果
物価高対策が最大の争点となっており、消費税減税への支持が圧倒的です。
ANN調査では「消費税の減税」が57%の支持を集め、「現金給付」の19%を大きく上回っています。共同通信調査でも「消費税減税」が76.7%に達し、6.7ポイントの増加を示しています。
外国人受け入れ政策についても世論の関心が高く、「規制を強化すべきだ」が47%、「いまのままでよい」が33%、「規制を緩和すべきだ」が14%となっています。この結果は参政党や日本保守党の支持拡大と密接に関連しており、保守系政党への追い風となっています。
年代別・地域別投票傾向
若年層の離反が与党にとって深刻な課題となっています。18~39歳の層で国民民主党・参政党が2割超の支持を得る調査が複数あり、従来の政党支持構造に大きな変化が生じています。
この世代交代の波は、既存政党の支持基盤を根本から揺るがす可能性があり、長期的な政界再編の起点となる可能性があります。特にSNSを活用した情報発信に長けた新興政党が、若年層の支持を集める傾向が顕著になっています。

比例代表制度の仕組みと議席配分
ドント方式による議席計算
参議院比例代表選挙ではドント方式による議席配分が採用されており、各政党の得票数に応じて50議席が配分されます。この方式は得票数の多い政党が有利になりすぎず、少数派の意見もある程度反映される仕組みとなっています。
具体的には、各政党の得票数を1、2、3…で順次割り、その商の大きい順に議席を配分していきます。この計算方法により、得票率と議席獲得数が比例的に配分され、民意の正確な反映が図られています。
投票方法と名簿順位の影響
比例代表選挙では政党名または候補者個人名のいずれかを記入して投票します。
政党名と個人名の票の合計が各党の得票数となり、個人名での得票が多い候補者は名簿順位に関係なく当選する可能性があります。
この非拘束名簿式の採用により、政党への支持と個人への信頼の両方が結果に反映される柔軟な制度となっています。特に知名度の高い候補者や話題性のある人物が個人票を集めることで、予想外の当選を果たすケースも見られます。
特定枠制度の活用状況
2019年から導入された特定枠制度により、政党は一定数の候補者を優先的に当選させることが可能になりました。この制度は主に合区対象県の候補者救済を目的としていますが、各党の戦略的活用も注目されています。
特定枠に指定された候補者は個人名での得票に関係なく優先的に当選するため、政党の戦略的判断が議席配分に大きな影響を与える要素となっています。
2025年参議院選【全国比例区】終盤の注目ポイント
投票率予測と影響分析
投票率の動向が最終的な議席配分を大きく左右する要因となっています。前回2022年の投票率52.0%を上回り、55%を超える場合は野党と新興勢力に追い風となる可能性が高いとされています。
高投票率は一般的に無党派層の投票参加を意味し、政権批判票の増加につながる傾向があります。
特に今回は物価高対策への関心が高く、生活に直結する政策への有権者の関心が投票行動に反映される可能性があります。
最終盤での情勢変化要因
期日前投票の動向とSNSでの情報拡散が、従来の選挙戦略を大きく変える要因となっています。
参政党やれいわ新選組がオンライン動員で支持を拡大している状況は、デジタル時代の新しい選挙戦の形を示しています。
また、各党の比例一本化戦略の成否も重要な要素です。特に自民党は支持層の結束を図り、票の分散を防ぐ戦略を展開していますが、新興政党への票流出を完全に防げるかが焦点となっています。
開票速報の見どころ
開票速報では参政党の議席数が最大の注目ポイントとなります。
予想を上回る議席を獲得した場合、既存政党の勢力図に大きな変化をもたらし、今後の政界再編の引き金となる可能性があります。
また、与党の過半数維持の成否も重要な観点です。非改選議席を含めた参議院全体での過半数124議席を維持できるかが、今後の政権運営に大きな影響を与えることになるでしょう。
【総括】2025参議院選【全国比例区】情勢調査
今回比例区のキーワードは「三極化」と「世代分断」です。
保守本流の自民、公明連合は支持率2割強で高齢層を中心に固める一方、立憲・共産など従来野党は支持を伸ばし切れず、中間に位置する国民民主や維新が都市部で競り合うことになる。
そこへ参政党、日本保守党といった新興勢力がSNS経由で存在感を高め、“第三極”が10議席超を狙う構図。
18~39歳では自民支持が2割を割り込み、国民民主・参政党で4割近くを占めるとの調査もあります。
物価高対策では「消費税減税」が7割近い支持を得ており、政策先鋭化した党が票を吸収。
ドント方式下での票割れが議席数に直結するため、与党が比例一本化を徹底できるか、新興勢力が個人名票を上積みできるかが終盤の焦点となるでしょう。