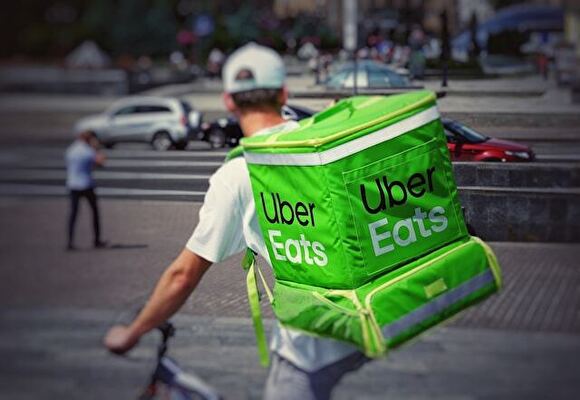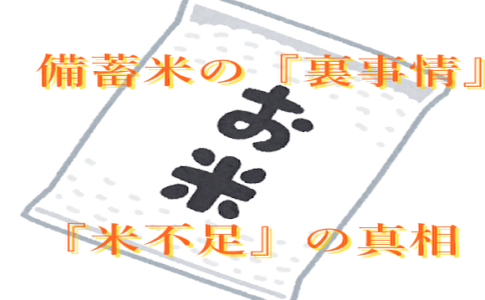コロナ禍で急成長を遂げたフードデリバリー業界・・・。
「Uber Eats」や「出前館」のロゴ入りバッグを持った配達員の姿は、街の風景として定着しました。しかし、新型コロナが5類感染症に移行し、日常が戻りつつある今、業界の風景は大きく変わりつつあります。
2023年度には過去最多の倒産件数を記録し、中小事業者を中心に淘汰が進む一方で、大手プラットフォーマーは成長を続けるという二極化が鮮明になっています。
「コロナ特需は終わった」と言われるデリバリー業界ですが、実際はどうなのでしょうか?
食材費高騰や人手不足、競争激化など複合的な課題に直面する中、生き残りをかけた各社の戦略と、これからのデリバリー業界の行方を徹底解説します。
コロナ後の「第3フェーズ」に突入したデリバリー業界の現在地と未来図をお届けします。

デリバリー業界のコロナ後:特需終焉と新たな局面
コロナ禍を経て、フードデリバリー業界は大きな変化の波の中にいます。爆発的な成長を遂げた後、今は新たなフェーズへと移行しているのです。
コロナ禍での爆発的成長とその要因
コロナ禍以前から成長傾向にあったフードデリバリー市場ですが、パンデミックを機にその成長は加速しました。その背景には、複合的な要因があります。
外出自粛と「巣ごもり需要」
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、全国的に外出自粛が要請され、飲食店の営業時間短縮や休業が相次ぎました。
これにより、自宅で食事をする「巣ごもり需要」が急増。
人々は外食の代わりに、自宅でレストランの味を楽しめるフードデリバリーを利用するようになりました。生活必需品の購入においても、非接触が推奨される中で宅配サービスの利用が増加しました。
この未曾有の状況が、デリバリー需要を爆発的に押し上げる最大の要因となったのです。
デリバリーアプリの普及と利便性向上
Uber Eatsや出前館といったフードデリバリーアプリの普及も、市場成長を後押ししました。
スマートフォン一つで簡単に多様な飲食店のメニューを注文でき、決済から配達状況の確認まで完結する手軽さが、幅広い層のユーザーに受け入れられました。
また、コロナ禍でデリバリーサービスを導入する飲食店が急増し、消費者の選択肢が大幅に増えたことも利用促進につながりました。
テクノロジーの進化とサービスの拡充が、デリバリーの利便性を飛躍的に向上させ、人々の生活に浸透する基盤を築いたと言えるでしょう。

デリバリー業界「コロナバブル」の終焉と市場の変化
急成長を遂げたデリバリー業界ですが、コロナ禍が落ち着きを見せ始めると、市場の様相は変化し始めました。
「コロナバブル」とも呼べる特需が終わり、業界は新たな課題に直面しています。
需要の落ち着きと競争激化
2023年5月に新型コロナウイルスが5類感染症へ移行し、人々の生活が平常化に向かうにつれて、デリバリー需要の伸びは鈍化しました。
外食機会が増え、デリバリーの利用頻度が減った人も少なくありません。
一方で、コロナ禍で多数の事業者が参入した結果、市場は飽和状態となり、競争が激化。
特に価格競争が厳しくなり、クーポンや割引に頼らざるを得ない状況も生まれています。需要の落ち着きと過当競争が、業界全体の収益性を圧迫する要因となっています。
中小企業の倒産増加とその背景
競争激化の波は、特に経営基盤の弱い中小・個人のデリバリー事業者を直撃しています。

背景には、デリバリー事業の参入障壁の低さがあります。
店舗が不要で初期投資を抑えられるため、コロナ特需に乗じて安易に参入した事業者が多かったものの、品質やサービスの差別化ができず、コスト増にも耐えきれずに淘汰されているのです。
デリバリー業界がコロナ後に直面する課題
需要の落ち着きや競争激化に加え、デリバリー業界は様々なコスト増加や構造的な問題にも直面しています。これらの課題が、特に中小事業者の経営を圧迫しています。
【デリバリー業界】コスト増加の三重苦
デリバリー事業の運営には、様々なコストがかかります。近年、これらのコストが軒並み上昇しており、利益を確保することが難しくなっています。
食材価格の高騰
世界的な物価上昇の影響を受け、飲食業に不可欠な食材価格が高騰しています。
円安も輸入食材の価格上昇に拍車をかけています。
デリバリー専門店はもちろん、実店舗を持つ飲食店にとっても、原材料費の上昇は経営を直撃する大きな問題です。
価格転嫁が難しい場合、利益率の低下は避けられません。特に、価格競争が激しいデリバリー市場においては、値上げによる顧客離れのリスクも高く、多くの事業者が厳しい判断を迫られています。
人件費の上昇と人手不足
飲食業界全体が、深刻な人手不足に悩まされています。
特に、コロナ禍で一度離れたスタッフが戻ってこないケースが多く見られます。
デリバリー業界においても、配達員の確保は大きな課題です。最低賃金の引き上げや、より良い条件を求める人材の流動化により、人件費は上昇傾向にあります。
配達員の不足は、配達時間の遅延やサービスエリアの縮小につながり、顧客満足度の低下を招く可能性もあります。人件費の上昇と人手不足は、コスト面だけでなくサービス品質にも影響を与える深刻な問題なのです。
エネルギーコスト増の影響
電気代やガス代、ガソリン代などのエネルギーコストの上昇も、デリバリー事業者の経営を圧迫しています。
厨房での調理に必要な光熱費はもちろん、配達に使用するバイクや自動車の燃料費も増加しています。自社で配達網を持つ事業者にとっては、ガソリン価格の高騰は無視できないコスト増となります。
これらのエネルギーコストは、事業運営の根幹に関わる部分であり、上昇分を吸収することは容易ではありません。食材費、人件費と合わせて、三重苦とも言えるコスト増が業界全体の収益性を悪化させています。
デリバリー業界の構造的な問題点
コスト増に加え、デリバリー業界特有の構造的な問題も、事業者の経営を難しくしています。
脆弱な収益モデルと価格競争
デリバリー事業は、一見するとテクノロジーを活用した効率的なビジネスに見えますが、実際には配達員というマンパワーに大きく依存しており、固定費や変動費がかさむ構造です。
プラットフォーム利用料や配達手数料も高く、利益を確保しにくい側面があります。
さらに、参入障壁の低さからくる過当競争により、値下げやクーポン配布合戦に陥りやすく、体力を消耗しがちです。赤字覚悟のセールに頼らず、持続可能な収益モデルを確立することが、業界全体の大きな課題となっています。
配達員の確保と品質維持の難しさ
フードデリバリーの品質は、料理の味だけでなく、配達員の対応や配達時間にも大きく左右されます。
しかし、配達員の多くはギグワーカーであり、雇用関係がないため、サービスの質を均一に保つことが難しいという課題があります。配達員のスキルやモラルにはばらつきがあり、交通ルールの無視や配達トラブル(遅延、誤配、商品の破損、無断キャンセルなど)も後を絶ちません。
配達員の確保自体も難しくなっており、安定したサービス提供の障害となっています。
実店舗との両立の課題
実店舗を持つ飲食店がデリバリーを導入する場合、新たな課題が生じます。
コロナ禍が落ち着き、店内飲食の客足が戻ってくると、厨房やスタッフのリソースを店内とデリバリーの両方に割く必要が出てきます。
ピークタイムには注文が集中し、調理や梱包、配達員への受け渡しに遅れが生じ、店内・デリバリー双方の顧客満足度が低下するリスクがあります。
デリバリー用のメニュー開発や在庫管理、オンライン注文システムへの対応など、運営負荷も増大します。リアル店舗の運営とデリバリー事業をいかに効率的に両立させるかが、多くの飲食店にとっての課題となっているのです。

コロナ後のデリバリー需要は終わった?利用者のリアルな声
コロナ特需が落ち着いたとはいえ、デリバリー需要が完全になくなったわけではありません。利用者の行動や意識はどのように変化しているのでしょうか。
需要は継続?変化する利用シーン
デリバリーは、一過性のブームではなく、私たちの生活様式の一部として定着しつつあります。利用シーンも多様化しているのです。
リモートワーク定着と日常化
コロナ禍をきっかけに普及したリモートワークは、アフターコロナにおいても一定の割合で継続されています。
在宅勤務中の昼食や、仕事終わりの夕食を手軽に済ませたいというニーズは依然として高く、デリバリーの利用を支えています。
また、コロナ禍でデリバリーの便利さを体験した人々にとって、それは特別な日の選択肢だけでなく、忙しい日の時短手段や、悪天候で外出したくない時など、日常的な選択肢の一つとして定着しました。
このように、デリバリーは特定の状況下だけでなく、日々の生活に溶け込んだサービスへと変化しています。
利便性の認知とリピート利用
一度デリバリーの利便性を知ると、継続的に利用するユーザーは少なくありません。
アプリで簡単に注文でき、自宅まで届けてもらえる手軽さは、時間や労力を節約したい現代人のニーズに合致しています。
子育て中の家庭や高齢者など、買い物や外食が難しい層にとっても、デリバリーは重要な生活インフラとなりつつあります。
大手プラットフォームは、メニューの見せ方やアプリの使いやすさ(ユーザーエクスペリエンス)の改善にも注力しており、こうした利便性の向上がリピート利用を促進し、市場全体の底支えにつながっています。
利用頻度の変化と今後の意向
デリバリーが日常化した一方で、利用者の意識や行動には変化も見られます。今後の利用意向についても、様々な声があります。
「利用を減らす」層の存在
デリバリー需要が底堅い一方で、今後の利用を減らす、あるいは利用しない予定だと考える人も半数以上いるという調査結果もあります。
その理由としては、外食機会の増加、節約志向の高まり、デリバリー料金(商品代金+配達料+サービス料)への割高感などが考えられます。
また、コロナ禍で頻繁に利用していた層が、以前のライフスタイルに戻る中で、利用頻度を見直しているケースもあるでしょう。全ての人がコロナ禍と同様の頻度で利用し続けるわけではなく、利用者の二極化が進む可能性も指摘されています。
ユーザーが求める価値の変化
コロナ禍初期は「とにかく届けてくれる」こと自体に価値がありましたが、サービスが普及するにつれて、ユーザーがデリバリーに求める価値も変化しています。
単に空腹を満たすだけでなく、より美味しいもの、より早く届くこと、より丁寧な対応など、サービス品質への要求が高まっています。
価格の安さも依然として重要ですが、それ以上に、信頼できる店舗の味や、時間通りの配達、丁寧な接客といった「体験価値」を重視する傾向が見られます。
今後は、こうした多様化するユーザーニーズにいかに応えられるかが、事業者にとっての鍵となります。
【デリバリー業界】生き残りをかけた戦略:「第3フェーズ」の戦い方
需要の落ち着きと競争激化、コスト増という厳しい環境の中、デリバリー業界は「第3フェーズ」とも呼ばれる新たな競争段階に入りました。
各社は生き残りをかけ、様々な戦略を展開しています。
【デリバリー業界】大手プラットフォーマーの動向
市場を牽引する大手プラットフォームの動きは、業界全体の方向性を左右します。各社の戦略には違いが見られます。
Uber Eatsの好調と加盟店支援
業界最大手のUber Eatsは、アフターコロナでも取扱高が二桁成長を維持するなど、好調を維持しています。

加盟店の優勝劣敗が進む中で、こうした支援策がUber Eatsの優位性をさらに強固にする可能性があります。
出前館などの苦戦と模索
一方、Uber Eatsに次ぐ規模を持つ出前館は、長らく赤字経営が続き、苦戦を強いられています。
かつては国内最大手でしたが、競争激化の中で収益性の改善が課題となっています。
他のプラットフォームも同様に厳しい状況にあり、一部では事業エリアの縮小や撤退の動きも見られます。これらの企業は、Uber Eatsとの差別化を図るため、特定の地域やジャンルへの特化、独自のサービス開発などを模索していると考えられます。
プラットフォーム間の競争は今後も続き、各社の戦略が生き残りを左右することになるでしょう。

差別化と新たな収益源の模索
プラットフォーム事業者も加盟飲食店も、他社との差別化を図り、新たな収益源を見つけることが急務となっています。
取扱商品の拡大(日用品など)
フード(食事)以外の領域に活路を見出そうとする動きもあります。
Uber Eatsなどが、食品だけでなく日用品や雑貨、医薬品などのデリバリー(クイックコマース)に参入しています。これにより、利用頻度の向上や客単価アップを狙っているのです。
ただし、日用品の即配サービスについては、「ダークストア」と呼ばれる専用倉庫からの配送モデルが登場したものの、日本ではまだ十分に浸透しておらず、既に撤退する動きも見られます。食以外の分野でのデリバリーが新たな収益の柱となるかは、まだ不透明な状況です。

配達時間短縮とサービス品質向上
価格競争から脱却し、サービス品質で差別化を図る動きも強まっています。
特に、配達時間の短縮は顧客満足度に直結するため、各社が注力しているポイントです。
より効率的な配達ルートの最適化、配達員へのインセンティブ設計、AI技術の活用などが進められています。また、丁寧な梱包、正確な配達、配達員のスムーズなコミュニケーションなど、総合的なサービス品質の向上も重要視されています。
今後は、単に早い・安いだけでなく、信頼性や満足度の高いサービスを提供できるかが、顧客獲得の鍵となります。
バーチャルレストラン・ゴーストレストランの活用
実店舗を持たず、デリバリー専門で運営する「ゴーストレストラン」や、既存の飲食店の厨房を活用して別ブランドのデリバリー専門店をオンライン上に出店する「バーチャルレストラン」といった業態もコロナ禍で注目されました。
これらは、初期投資を抑えつつ、特定のジャンルに特化したり、複数のブランドを展開したりすることで、多様な顧客ニーズに応え、収益機会を増やす戦略です。
ただし、実店舗がないことによる信頼性の低さや、品質管理の難しさといった課題もあります。成功のためには、料理のクオリティ維持と効果的なマーケティングが不可欠です。
実店舗を持つ強みとオンライン化
デリバリー市場においても、実店舗を持つことの強みが再認識されています。同時に、オンラインへの対応も不可欠となっています。
ブランド力と信頼性
結局のところ、デリバリーでリピートされるのは、実店舗で支持されている、品質が安定したお店であることが多いです。
長年培ってきたブランドイメージや、実際に店舗で食事をした経験は、顧客にとっての安心感や信頼につながります。
ゴーストレストランのように実態が見えにくい業態と比較して、実店舗を持つ飲食店は、品質への期待感や安心感という点で有利です。
コロナ禍で一時的にデリバリー専門店が急増しましたが、最終的には、地道に品質を追求し、顧客との信頼関係を築いてきた店舗が競争力を維持しています。
オンライン売上の重要性
実店舗を持つ飲食店にとっても、デリバリーやテイクアウト、モバイルオーダーといったオンライン経由の売上は、無視できない存在となっています。
特に都市部の大手チェーンなどでは、オンライン売上が全体の4割を占めることを見据えた戦略を立てています。
リアル店舗での集客だけでなく、オンラインでの販売チャネルを確立し、多角的に収益を上げることが、今後の飲食店経営においてますます重要になります。
デリバリープラットフォームへの出店だけでなく、自社アプリやウェブサイトでの注文受付など、オンライン化への投資が求められています。
【デリバリー業界】配達員(ギグワーカー)を取り巻く環境の変化
デリバリーサービスを支える配達員。その多くは個人事業主として働くギグワーカーであり、彼らを取り巻く環境も変化しています。
【デリバリー業界】働き方の変化と課題
自由な時間に働ける魅力がある一方で、ギグワーカーとしての働き方には課題も指摘されています。
収入の不安定さとリスク
ギグワーカーである配達員の収入は、配達件数に応じた出来高制が基本であり、天候や曜日、時間帯によって大きく変動します。
安定した収入を得ることが難しく、特に新規参入者は稼ぎにくいという声もあります。
また、個人事業主であるため、事故に遭った際の労災保険による補償が十分でないなど、社会的なセーフティネットが弱いという問題も指摘されています。
コロナ禍で一時的に配達員に転身した人も多いですが、収入や保障の不安定さから、長期的なキャリアとして選択するにはリスクも伴います。
労働環境と法的保護の議論(インボイス、背番号など)
ギグワーカーの法的保護については、世界的に議論が進んでいます。
日本ではまだ労働者としての権利が十分に保障されていないのが現状ですが、変化の兆しもあります。
2023年から始まったインボイス制度は、免税事業者であった配達員の収入や契約に影響を与える可能性があります。また、配達中の事故増加を受け、配達員を識別するための背番号表示の義務化が検討されるなど、安全確保と責任の明確化に向けた動きも出ています。
今後、ギグワーカーの労働環境改善や法的地位に関する議論がさらに進むことが予想されます。
デリバリー業界『2024年問題』の影響
物流業界全体に影響を与える「2024年問題」は、フードデリバリーの配達網にも影響を及ぼす可能性があります。
軽貨物運送業界への影響
2024年4月から、自動車運転業務の時間外労働に年間960時間の上限規制が適用されました(通称「2024年問題」)。
これは主にトラックドライバーを対象としていますが、フードデリバリーの一部を担う軽貨物運送事業者にも影響が及ぶ可能性があります。
ドライバーの労働時間減少による収入減や、業界全体での人手不足の深刻化が懸念されているのです。これにより、輸配送コストの上昇や、サービスの維持が困難になる地域が出てくるかもしれません。フードデリバリー事業者も、配達網の維持・効率化が一層求められることになります。
配達員不足への懸念
2024年問題による物流業界全体の人手不足は、フードデリバリーの配達員確保にも影響を与える可能性があります。
より待遇の良い運送業界へ人材が流出したり、ギグワーカーとして働く魅力が相対的に低下したりすることも考えられ、ただでさえ配達員の確保が課題となっている中で、人手不足がさらに深刻化すれば、配達遅延の常態化やサービス提供エリアの縮小につながりかねません。
安定したデリバリーサービスを維持するためには、配達員の待遇改善や働きやすい環境整備が、これまで以上に重要になってくるでしょう。
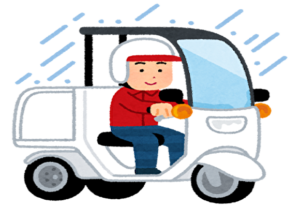
Q&A『デリバリー業界のコロナ後』 よくある質問
Q1: コロナが終わってもデリバリーの需要はなくならない?
A1: 需要が完全になくなることは考えにくいです。コロナ禍でデリバリーの利便性が広く認知され、リモートワークの定着などもあり、日常生活の一部として定着した側面が強いからです。ただし、コロナ禍のような爆発的な伸びは落ち着き、利用頻度が減る人もいます。今後は、日常的な利用と、特別なシーンでの利用が混在し、安定した市場を形成していくと考えられます。価格だけでなく、味や配達時間、サービス品質など、利用者が求める価値に応えられるサービスが選ばれていくでしょう。
Q2: デリバリー専門店の経営はもう難しい?
A2: 非常に厳しい状況と言えます。コロナ特需期に参入したデリバリー専門店(ゴーストレストラン等)の多くが、競争激化やコスト増により淘汰されています。実店舗を持たないため、ブランド力や信頼性の面で不利になりがちです。生き残るためには、他にはない独自のメニューやコンセプトで強いファンを獲得する、徹底した品質管理と効率的なオペレーションを構築する、などの高度な経営戦略が必要です。実店舗を持ち、その延長線上でデリバリーを行う方が、安定性は高いと言えるでしょう。
Q3: 配達員として働くのは今後どうなる?
A3: 働き方の自由度は魅力ですが、収入の不安定さや社会保障の課題は依然として残ります。インボイス制度の導入や、背番号義務化の検討など、ギグワーカーを取り巻く環境は変化しており、今後も法的整備が進む可能性があります。また、「2024年問題」による物流業界全体の人手不足が、配達員の需要や待遇にどう影響するかも注視が必要です。短期的には仕事があるかもしれませんが、長期的に安定した収入を得るには、他の仕事との兼業や、スキルアップなども視野に入れる必要があるかもしれません。
【総括】デリバリー業界の現在地:コロナ後の変化と生き残り戦略
コロナ後のフードデリバリー業界は、まさに「生存競争」の時代に突入しています。
2023年度には過去最多の倒産を記録し、特に中小事業者が苦戦する二極化が鮮明になりました。
その背景には、コロナ特需の終焉に加え、食材費・人件費・エネルギーコストの「三重苦」と過当競争があります。
しかし、市場そのものは今後も成長が見込まれており、Uber Eatsのような大手プラットフォーマーは二桁成長を維持しています。
この明暗を分けるのは、「持続可能なビジネスモデル」の有無です。
実店舗を持つ飲食店はブランド力と信頼性という強みを活かし、デジタル技術を駆使した効率的なオペレーションと顧客満足度向上に注力しています。
今後のデリバリー業界で生き残るためには、価格競争からの脱却、料理の品質とサービスの信頼性による差別化、そしてデータ分析を活用したパーソナライズされた体験の提供が鍵となります。また、食品以外への取扱商品拡大や、複数の販売チャネル構築によるリスク分散も有効な戦略です。
コロナ特需という一時的なブームは終わりましたが、デリバリーが生活インフラとして定着した今、真に顧客価値を提供できる事業者だけが生き残る「第3フェーズ」が始まったのです。