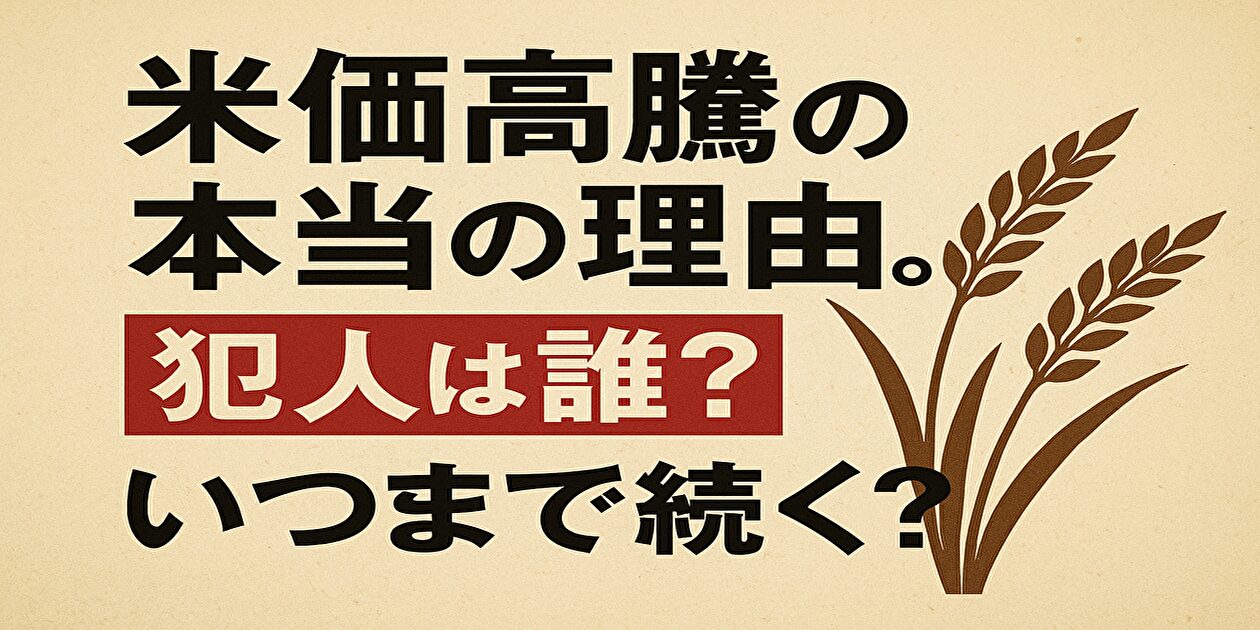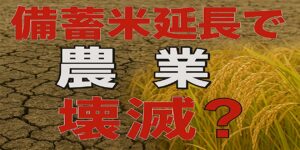「スーパーのお米、高すぎて買えない…」毎日そうため息をついていませんか?
新米が出回れば安くなると言われていたのに、12月になっても5kg 3,000円超えは当たり前。
実はこれ、猛暑や不作だけが原因ではありません。
なぜ在庫が余り始めているのに値段は下がらないのか?なぜ政府は「増産」と言った直後に「減産」へ方針を変えたのか?
この記事では、私たちの食卓を直撃する「人災」としての米高騰、その「誰のせい」という疑問の核心に、最新データで切り込みます。
米が高いのは誰のせい?農林水産省の迷走と責任
最大の「主犯」は誰だ?農林水産省の50年続く責任
根本的な原因:「減反政策」という諸悪の根源
米が高騰する根本的な原因、つまり「真犯人」は、農林水産省が半世紀にわたり続けてきた「減反政策」です。
この政策の仕組みは、驚くほどシンプルかつ不合理です。
政府は毎年約3,500億円の税金を使い、農家に「米を作らないこと」を奨励し、補助金を支払っています。
これは極めて矛盾した政策です。
鈴木農水大臣の「方針転換」と「おこめ券」という失策
さらに火に油を注いだのが、2025年の政府対応です。
政治実績皆無の前政権が珍しくまともな政策となる「歴史的な増産転換」8月に掲げ、米の生産拡大を宣言しました。
しかし10月に就任した鈴木憲和農水大臣は、この方針を事実上撤回。「需要に応じた生産」という言葉で、再び減反政策へとUターンしてしまいました。
さらに問題なのが、価格高騰対策として打ち出した「おこめ券」という施策です。
この政策は「高い米価を税金で買い支える」という愚策そのものであり、価格を下げる努力を放棄したに等しいと、経済学者や消費者から猛烈な批判を浴びています。
経済学者・山下一仁氏は明確に指摘しています「おこめ券が配られれば、高い米価での購入が促進され、相対的に米価維持につながる。減反で供給を絞りながら、価格を市場任せにする態度は無責任である」。
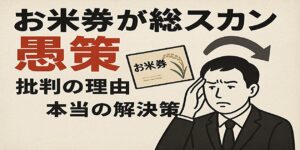
米が高いのは誰のせい?価格を吊り上げた「実行犯」JA(農協)の戦略
過去最高レベルの「概算金」設定が価格を決定づけた
2025年産の米価格を決定づけた「実行犯」と言えるのがJA(農協)グループです。
彼らは今年の収穫前、農家に支払う前払い金(概算金)を、前年比1.5倍以上という過去最高レベル(60kgあたり3万円超)に設定しました。
兼業農家の囲い込み:JA金融ビジネスの本質
なぜJAはこれほど強気な価格設定をするのでしょうか?その理由は、「兼業農家の囲い込み」のためです。米価が高ければ、赤字になりがちな小規模農家も離農せずに済みます。
消費者の悲鳴よりも、組織の論理が優先された結果が、今の高値という現実なのです。
「複合災害」:政府・JA・卸売業者の利害が絡まる構造
初期の「便乗値上げ」から一転、在庫パンクの苦悩へ
騒動の初期、一部の大手卸売業者は「在庫隠し」「便乗値上げ」と批判され、実際に増益を記録しました。しかし12月現在、彼らは一転して「被害者」になりつつあります。JAが高い価格を設定したため、高値で仕入れざるを得なかった大量の米が、消費者の買い控えによって倉庫に積み上がっているのです。
 杉山 制空
杉山 制空このままでは保管料がかさむ上、古米になれば価値は暴落します。「高値掴み」させられた卸売業者の悲鳴が、業界内部で響き渡り始めています。
スーパーも実は苦戦中:客離れの実態
「スーパーも便乗値上げしているのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし多くのスーパー、特に安さを売りにするディスカウント店は苦境に立たされています。米は集客の要となる商品ですが、仕入れ値が高すぎて特売ができず、利益率を削って販売しているのです。
その結果、「米が高いから店に行かない」という客離れが発生し、他の食材の売上まで落ち込む悪循環に陥っているのです。OKストアやロピアといった「安さ」が武器の店ほど、この異常な高値構造に苦しめられているのが実情です。
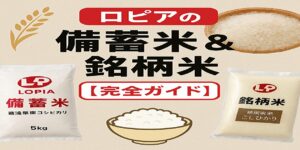
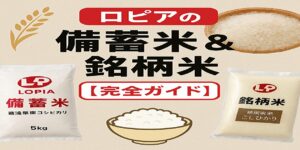
政策の本当の責任者たち:「鉄のトライアングル」の存在
なぜこの不合理な政策が50年も続くのか
この不合理な減反政策が50年以上も維持される背景には、「農水省」「JA農協」「農林族議員」の3者による強固な利害関係、通称「鉄のトライアングル」が存在します。
この3者が互いの利益のために固く結びついた結果、消費者や国全体の利益がないがしろにされているのが現状なのです。
今後の展開と「米バブル崩壊」の予測
2026年6月頃に「価格崩壊」のシナリオ
結論として、現在の高値は長くは続きません。
消費者不在の価格吊り上げは、必ず限界を迎えます。専門家の間では、次の新米が出る前の端境期、具体的には「2026年6月頃」に価格が暴落するとの予測が出ています。パンク寸前の在庫を抱えきれなくなった業者が、なりふり構わず「投げ売り」を始める可能性があるからです。
消費者ができる最善の対策



私たち消費者にできる最大の自衛策は、慌てて買いだめせず、この歪んだ「米バブル」が弾けるのを冷静に見守ることです。パンや麺類など代替品を上手に活用し、高値掴みを避けて「待つ」ことが、この不公正な市場に対する最も効果的な反撃です。
米が高いのは誰のせい?よくある質問
Q1. 米の値段は誰が決めているのですか?
A. 建前は「市場」ですが、実質は「JA」と「政府」が誘導しています。JA(農協)が農家からの買取価格(概算金)を大幅に引き上げたことで、それが「最低価格」となって市場全体が高騰しました。さらに、政府(農水省)が減反政策で供給量を絞っているため、価格が下がりにくい土壌を作っています。
Q2. 米が高いなら、農家さんは儲かってウハウハなのでは?
A. 残念ながら、農家の9割以上は経営が苦しいままです。米の買取価格は上がりましたが、それ以上に肥料・燃料・機械代などの生産コストが爆上がりしているからです。また、政府からの補助金も減額傾向にあり、実質的な手取りは増えていません。儲かっているのは、手数料を取る流通業者や、組織を維持できるJAなどの一部だけという構造があります。
Q3. この米高騰はいつまで続くの?
A. 2026年の初夏(6月頃)に値下がりする可能性があります。現在、高すぎて売れない米が倉庫に余り始めています。この在庫が限界に達すると予想されるのが2026年6月頃です。次の新米が出る前に倉庫を空けるため、業者が「投げ売り」を始める可能性が高く、そこが価格崩壊(=安くなる)のタイミングと予測されています。
《総括》米が高いのは「誰のせい」
米が高いのは「誰のせい」なのかという疑問に対する答えは、明確に存在します。
最大の責任は、50年以上にわたり「減反政策」を続け、意図的に供給不足を作り出してきた農林水産省にあります。さらに、その政策に乗じて価格を吊り上げ、組織の利益を優先したJA(農協)**の罪も重いと言わざるを得ません。
現在の米価は、「気象条件や自然要因」ではなく、政治的・組織的な意思決定の産物です。
鈴木農水大臣が「価格は市場が決める」と言い放ちますが、その市場を歪めているのは他ならぬ政府の政策なのです。おこめ券というその場しのぎの対策でお茶を濁すのではなく、減反政策の完全廃止という根本治療が必要です。
この不合理な構造によって、私たち国民は「二重の負担」を強いられています。
12月現在、市場には在庫が溜まり始め、バブル崩壊の兆候が見られています。この不条理な騒動が、日本の食料政策が大きく変わるきっかけになることを、多くの国民が望んでいるのです。