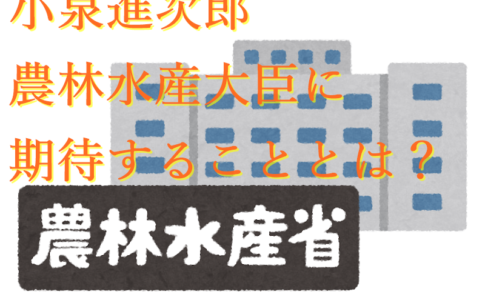トランプ政権が発動した「相互関税」政策が日本経済に大きな波紋を広げています。
すでに自動車に対する25%の追加関税が発動され、日本の株価は一気に1000円程度下落。さらに全輸入品に10%の基本関税、日本には追加で合計24%の関税が課される見通しです。
しかし、この関税問題で最も懸念されるのが日本の米産業への影響です。
トランプ政権は「日本は米に700%の関税をかけている」と主張していますが、実際には国際米価格の上昇により関税率は約213%まで低下しています。
もし米の関税撤廃を迫られれば、5キロ750円程度のアメリカ産米が日本市場に流入し、5キロ4,000円の日本産米は価格競争に太刀打ちできなくなるでしょう。
日本の食料安全保障が脅かされる中、私たちはどう備えるべきなのでしょうか。
本記事では、トランプ政権の「相互関税」政策が日本の米産業に与える深刻な影響について解説します。
「日本は米に700%の関税をかけている」というトランプの主張の真偽から、実際の関税率の推移、関税撤廃が実現した場合の日本農業への打撃、食料安全保障上のリスクまで、多角的に分析。
さらに、政府レベルでの対応策から個人レベルでの備えまで、具体的な対策を提案します。
日本の主食を守るために、今知っておくべき重要情報をお届けします。
【トランプ関税】700%関税は本当か?誤解と日本の米関税の実態と影響
レビット報道官は何者?発言とその波紋
ホワイトハウスのレビット大統領報道官は2025年3月31日、日本が米国から輸入する米に対して「700%の関税を課している」と発言し、大きな波紋を広げました。
この発言は3月11日にも同様の内容で行われており、日本側の反発を招いていましたが、再び根拠を示さずに繰り返されました。
レビット報道官はホワイトハウスでの記者会見で、アメリカ産品に対して関税を課している国々を念頭に置き、「長い間、我が国から金を搾り取って、アメリカの労働者を軽視してきた」と指摘し、トランプ政権が「不公正な貿易慣行」とみなす事例として、「日本が米国産の米に700%の関税をかけている」と名指しで批判しました。

リーヴィットは1997年8月24日に生まれ、現在27歳で、米国史上最年少のホワイトハウス報道官となっています。ニューハンプシャー州アトキンソン出身で、両親はアイスクリーム店と中古車販売を営んでいました。保守的なカトリック教徒の家庭で育ち、彼女は家族の中で初めて大学を卒業した人物です。
マサチューセッツ州のセントラル・カトリックハイスクールを卒業
セント・アンセム大学で政治学とコミュニケーションを専攻
大学では放送クラブを設立し、トランプ支持の活動を展開
政治キャリア
リーヴィットの政治キャリアは以下の通りです。
トランプ前政権でケイリー・マケナニー報道官の下でアシスタントを務めた
その後、エリーズ・ステファニク下院議員のコミュニケーション・ディレクターに就任
2022年、ニューハンプシャー州第1選挙区から連邦下院議員選挙に共和党候補として出馬したが、民主党のクリス・パパスに敗れる
2024年、トランプ大統領選挙キャンペーンの全国広報官に就任
2024年11月15日、トランプから次期ホワイトハウス報道官に指名される
2025年1月20日、第36代ホワイトハウス報道官に就任
個人生活
リーヴィットは32歳年上の不動産開発業者ニコラス・リッチオと結婚しています。2024年7月に男児を出産しましたが、トランプ暗殺未遂事件が発生した際には、予定していた産休を切り上げて生後わずか4日で職務に復帰するという忠誠心を示しました。
報道官としての特徴
リーヴィットは若さにもかかわらず、報道官として以下のような特徴を見せています:
若さに見合わぬ熟練ぶりと自信に満ちた態度
メモや説明資料を参照せずに質問に対応する能力
従来型メディアに対して時に毅然とした態度や軽蔑を示す
トランプ大統領の発言や誇張を増幅させる傾向がある
ミニマムアクセス制度の概要
日本の米輸入制度の重要な柱となっているのが「ミニマムアクセス(MA)」制度です。
これは、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果として導入された制度で、日本が一定量の米を無関税で義務的に受け入れるというものです。
現在、日本はアメリカを含む各国から年間77万トンを上限に無関税で米を購入しています。
この制度は、日本の米市場を一定程度開放しつつも、国内の米生産を保護するためのバランスを取った措置として機能しています。
ミニマムアクセス制度の導入は、当時のアメリカ(クリントン政権)が、日本の米について関税化の例外(特例措置)を認める代わりに要求したものでした。
この制度により、アメリカは一定量の米を確実に日本市場に輸出できるようになり、日本は国内の米産業を守りながら国際的な貿易ルールに対応することが可能になりました。
トランプ政権の「700%関税」という主張は、このミニマムアクセス制度の存在を無視したものだと言えます。
1キロあたり341円の固定関税の仕組み
ミニマムアクセス枠を超える米の輸入に対しては、1キログラム(kg)あたり341円の固定関税が課されています。
これは率ではなく固定額で設定されているという点が重要です。
通常の関税は輸入品の価格に対して一定の割合(率)で課されることが多いのですが、日本の米関税は重量に対して固定額で課税する仕組みになっています。
この仕組みの問題点は、国際的な米価格が上昇すると実質的な関税率が低下してしまうことです。
例えば、米の国際価格が1キロ44円だった2005年には、341円の固定関税は実質的に778%の関税率に相当していました。しかし、米の国際価格が上昇するにつれて、同じ341円の固定関税でも実質的な関税率は低下していきます。
この仕組みは当初、日本の米産業を強力に保護する目的で設計されましたが、国際的な米価格の上昇という予想外の展開により、その保護機能が徐々に弱まってきているのです。
現在のトランプ政権が問題視しているのは、この固定関税の仕組み自体ではなく、かつての高い実質関税率を根拠に「不公正」と主張している点です。
国際米価格の上昇と実質関税率の低下
国際的な米価格は過去20年間で大幅に上昇しており、これに伴い日本の固定関税の実質的な保護効果は著しく低下しています。
農水省の計算によると、2005年当時の米の国際価格は1キロあたり44円でした。この時点では、1キロあたり341円の固定関税は実質的に778%の関税率に相当していました。
しかし、2009年には国際米価格が1キロあたり122円まで上昇し、同じ341円の固定関税でも実質関税率は280%まで低下しました。
これは約3分の1への低下を意味します。
この傾向は続いており、2025年現在のアメリカ産カルロース米の価格は1キロあたり約160円程度まで上昇しています。その結果、341円の固定関税の実質関税率は約213%まで低下しています。
つまり、トランプ政権が主張する「700%の関税」は過去の一時点での数値であり、現在の実態を正確に反映していないのです。
この実質関税率の低下は、日本の米産業にとって大きな脅威となっています。なぜなら、関税による保護効果が弱まることで、輸入米と国産米の価格差が縮まり、価格競争が激化する可能性があるからです。
2025年現在の実質関税率の試算
2025年現在の状況を具体的に試算すると、日本の米関税の実質的な保護効果はさらに弱まっていることがわかります。
現在のアメリカ産カルロース米の国際価格は1キロあたり約160円程度です。これに1キロあたり341円の固定関税を加えると、輸入時の価格は1キロあたり約501円になります。これは国際価格の約213%の関税率に相当します。
かつての778%と比較すると、実質関税率は約4分の1に低下したことになります。この傾向は今後も続くと予想され、国際的な食料価格の上昇や円安の進行によって、実質関税率はさらに低下する可能性があります。
また、5キロ単位で考えると、関税なしのアメリカ産カルロース米は約750円程度で流通する可能性があるのに対し、日本産米は5キロあたり約4,000円程度です。
この価格差は、関税がなければ日本の米農家が価格競争で太刀打ちできない状況を示しています。
トランプ政権の関税政策と日米貿易交渉の行方次第では、日本の米産業は存続の危機に直面する可能性があるのです。
【コメ関税撤廃】トランプ関税により日本の米産業が直面するリスク
【コメ関税撤廃】米国との貿易交渉における米の位置づけ
米国との貿易交渉において、米は常に重要な交渉カードとして位置づけられてきました。
トランプ政権は「アメリカファースト」の方針のもと、日本に対して農産物市場のさらなる開放を求めています。
特に米は、アメリカにとって重要な輸出品目であり、日本市場への参入拡大を長年求めてきた分野です。
今回のトランプ関税政策では、自動車産業への25%の追加関税という強力なカードを切ることで、日本に対して米の関税撤廃を迫る可能性が高まっています。
過去の交渉でも、日本は自動車輸出を守るために農産物で譲歩するパターンが見られました。

関税撤廃を求められる可能性と背景
トランプ政権が日本に対して米の関税撤廃を求める可能性は非常に高いと言えます。
その背景には、アメリカの農業州からの政治的圧力があります。
アメリカの農業州は共和党の強固な支持基盤であり、トランプ大統領にとって重要な選挙区です。
これらの州の農家は、日本市場への輸出拡大を強く望んでいます。また、トランプ政権は「公平な貿易」を掲げており、日本の米関税を「不公正な貿易障壁」と位置づけています。
さらに、日本の米関税制度が固定額(1キロあたり341円)で設定されているため、国際価格の上昇に伴い実質的な関税率が低下しているという事実は、アメリカ側にとって「今こそ関税撤廃を求めるチャンス」と映る可能性があります。
実際、現在の実質関税率は約213%まで低下しており、かつての778%と比べると大幅に下がっています。この状況を踏まえ、トランプ政権は「すでに機能が低下している関税をいっそのこと撤廃せよ」と主張する可能性が高いのです。
米国産カルロース米と日本産米の価格差
米国産カルロース米と日本産米の間には、圧倒的な価格差が存在します。
現在の国際価格に基づいて試算すると、関税が撤廃された場合、アメリカ産カルロース米は5キロあたり約750円程度で日本市場に流通する可能性があります。
これに対して、日本産米は5キロあたり約4,000円程度で販売されており、その価格差は5倍以上にもなります。
仮に流通コストや小売マージンを加えても、アメリカ産米は1,000円から1,200円程度で店頭に並ぶ可能性があり、依然として日本産米との間に大きな価格差が生じます。
この価格差は、日本の消費者にとって無視できない魅力となるでしょう。
特に、経済的に厳しい状況にある家庭や、米の消費量が多い飲食店などにとっては、安価なアメリカ産米への切り替えは合理的な選択となります。
また、日本の若い世代を中心に、米の味や品質よりも価格を重視する消費者が増えている傾向も、この価格競争をさらに厳しいものにする要因となっています。
消費者選択への影響予測
関税撤廃によって安価な輸入米が流入した場合、消費者の選択行動は大きく変化すると予測されます。
価格に敏感な層、特に若年層や低所得層、大家族世帯などは、安価な輸入米へと購買をシフトする可能性が高いでしょう。
また、業務用需要(飲食店、弁当チェーン、給食センターなど)も、コスト削減のためにアメリカ産米への切り替えが進むと考えられます。
一方で、高品質な日本産米を好む層、特に高所得層や高齢者層は、引き続き国産米を選択する傾向が続くでしょう。
しかし、この層だけでは日本の米農家を支えるには不十分です。
また、消費者の中には「普段使いはアメリカ産、特別な時は日本産」という使い分けをする層も増えると予想されます。
さらに、長期的には消費者の味覚自体が変化し、アメリカ産米に慣れてしまう可能性もあります。
特に子供の頃からアメリカ産米を食べて育った世代が増えると、将来的に日本産米の需要はさらに減少する恐れがあります。
これらの変化は、日本の米産業に壊滅的な打撃を与える可能性があります。
生産規模の縮小と農家数の減少見通し
関税撤廃が実現した場合、日本の米産業は急速な縮小を余儀なくされるでしょう。
現在でも高齢化や後継者不足により農家数は減少傾向にありますが、関税撤廃によってこの傾向は加速します。
具体的には、現在の米農家数が10分の1程度にまで減少する可能性があります。
特に、中小規模の農家は価格競争に耐えられず、真っ先に廃業に追い込まれるでしょう。
一部の大規模農家や、特殊な品種・有機栽培などの付加価値を持つ農家のみが生き残る可能性がありますが、それでも厳しい経営環境が続くと予想されます。
農家の減少に伴い、農業機械メーカーや肥料・農薬メーカー、農協など関連産業も大きな打撃を受けます。さらに、農家の減少は耕作放棄地の増加につながり、日本の農村景観や生態系にも悪影響を及ぼす可能性があります。
一度失われた農地や農業技術、種子などの遺伝資源は、簡単に取り戻すことができません。このような状況は、日本の食料安全保障にとって深刻なリスクとなります。
地域経済への波及効果
米産業の縮小は、地域経済に広範な波及効果をもたらします。
まず、農村部では農家の収入減少により、地域の購買力が低下します。
これにより、地元の小売店やサービス業も打撃を受け、地域経済全体が衰退するという悪循環に陥る恐れがあります。
特に、米作が主要産業である地域(新潟、秋田、山形など)では、その影響は深刻です。
また、農業関連の雇用(農業機械販売・修理、肥料・農薬販売、農協職員など)も減少し、地域の雇用情勢が悪化する可能性があります。
米作を中心とした農村文化や伝統行事(田植え祭り、収穫祭など)も失われる恐れがあります。加えて、水田は洪水防止や地下水涵養、生物多様性維持などの多面的機能を持っていますが、耕作放棄によりこれらの機能が失われると、環境面でも悪影響が生じます。
中山間地域では、水田が果たしている土砂崩れ防止などの防災機能が失われることで、災害リスクが高まる可能性もあります。
このように、米産業の縮小は単なる一産業の問題ではなく、地域社会全体の存続に関わる重大な問題なのです。
【トランプ関税】日本の『食料安全保障』の観点からの影響
食料自給率低下の危険性
日本の食料自給率はカロリーベースですでに38%程度と先進国の中でも極めて低い水準にあります。
米は日本人の主食であり、現在でも比較的高い自給率を維持している数少ない作物です。
しかし、米の関税が撤廃され輸入米に市場を奪われると、この自給率はさらに低下する恐れがあります。
食料自給率の低下は、国家の安全保障上の重大なリスクとなります。
世界的な人口増加や気候変動による不作、紛争などによって国際的な食料供給が不安定化した場合、輸入依存度の高い国は深刻な食料危機に直面する可能性があります。
また、食料は戦略物資でもあり、外交交渉における交渉力の低下にもつながります。
実際に、過去の歴史を振り返ると、食料自給能力の喪失は国家の独立性や主権にも影響を及ぼしてきました。米の自給率低下は、単なる一産業の問題ではなく、国家の存立基盤に関わる問題として捉える必要があります。
単一国への依存がもたらす脆弱性
米の関税撤廃によって、日本の米市場はアメリカ産米に大きく依存することになります。
このような単一国への依存は、供給の脆弱性を著しく高めます。
アメリカとの関係が悪化した場合や、アメリカ国内の政策変更(輸出規制など)があった場合、日本の食料供給は直ちに危機に陥る可能性があります。
トランプ大統領の「アメリカファースト」政策を考えると、このリスクは決して小さくありません。
実際に、過去には食料を外交カードとして利用した事例も多く見られます。

紛争や気候変動による供給不安
国際的な紛争や気候変動は、世界の食料供給に大きな影響を与えます。
直近では、ロシア・ウクライナ紛争は世界の小麦供給に大きな打撃を与え、多くの国で小麦価格が高騰しました。
米についても同様のリスクが存在します。
アメリカの穀倉地帯では、気候変動の影響による干ばつや洪水が頻発しており、生産量の変動が大きくなっています。また、水資源の枯渇や土壌劣化など、長期的な環境問題も米の生産に影響を与える可能性があります。
さらに、国際的な紛争やテロ、サイバー攻撃などによって物流が混乱した場合、輸入に依存する日本は深刻な食料不足に陥る恐れがあります。
島国である日本は、海上輸送路の安全確保が不可欠ですが、これは完全には日本の管理下にありません。このような不確実性の高い国際環境において、基礎的な食料である米の自給能力を失うことは、国家の安全保障上大きなリスクとなります。
20%の供給減で2倍の価格上昇の法則
農業経済学では、食料の供給量が20%減少すると、価格が2倍になるという法則があります。
これは食料の需要の価格弾力性が低い(価格が上がっても需要があまり減らない)ことに起因しています。
つまり、わずかな供給減少でも、価格は大幅に上昇する傾向があるのです。
実際に、日本の米市場でもこの法則に近い現象が観察されています。
2023年には米の流通量がわずか数パーセント(3〜4%程度)減少しただけで、米価が大幅に上昇しました。もし輸入依存度が高まり、何らかの理由で輸入量が20%減少した場合、米価は現在の2倍以上に高騰する可能性があります。
さらに、パニック買いや投機的な動きが加わると、価格上昇はさらに加速する恐れがあります。
このような急激な価格上昇は、特に低所得層に大きな打撃を与え、社会不安を引き起こす可能性もあります。食料安全保障の観点からは、このような価格変動リスクを最小化するためにも、一定の自給能力を維持することが重要です。
最近の米価高騰事例からの教訓
2023年の米価高騰は、食料供給の脆弱性を示す重要な教訓となりました。
この時は、流通量のわずか数パーセントの減少で米価が大幅に上昇しました。
これは、食料市場の需給バランスがいかに繊細であるかを示しており、もし米の関税が撤廃され、日本の米生産が大幅に縮小した後に、輸入米の供給に問題が生じた場合、2023年の事例をはるかに超える価格高騰が起こる可能性があります。
また、2008年の世界食料危機では、主要輸出国による輸出規制や投機マネーの流入により、穀物価格が短期間で2〜3倍に高騰しました。
この時、日本は比較的高い米の自給率を維持していたため、深刻な影響は避けられましたが、米の自給能力を失った状態で同様の危機が起これば、その影響は計り知れません。
これらの事例は、食料安全保障における自給能力の重要性を改めて示しています。
短期的な経済効率性だけを追求し、食料の自給能力を失うことは、長期的には大きなリスクとなる可能性があります。
トランプ関税への日本政府としての対策
自動車と農業のバランスを考えた交渉アプローチ
日本政府は、トランプ政権との交渉において、自動車産業と農業のバランスを慎重に考慮したアプローチが求められます。
自動車産業は日本の主要輸出産業であり、すでに25%の追加関税が発動されたことで大きな打撃を受けています。
この状況を打開するために、農業分野、特に米の関税撤廃を交渉カードとして使うよう求められる可能性が高いです。しかし、単純に自動車産業を守るために農業を犠牲にするという短絡的な判断は避けるべきです。
両産業はともに日本経済と社会にとって重要な役割を果たしており、どちらかを犠牲にするのではなく、双方を守る創造的な解決策を模索する必要があります。
例えば、米の関税は維持しつつも、他の農産物や分野での譲歩を検討する、あるいは段階的な関税引き下げと国内農家への支援策をセットで提案するなど、バランスの取れた交渉戦略が求められます。
また、WTOの枠組みを活用し、トランプ政権の一方的な関税措置の不当性を国際社会に訴えるアプローチも重要です。
国際的な支持獲得の重要性
トランプ政権の「相互関税」政策に対抗するためには、日本単独の努力だけでなく、国際的な支持を獲得することが重要です。
トランプ政権の関税政策は日本だけでなく、EU、中国、韓国など多くの国々にも影響を与えています。これらの国々と連携し、共同戦線を張ることで交渉力を高めることができます。
食料安全保障の重要性については、多くの国が共感する課題です。
WTOの場を活用して、食料安全保障のための一定の関税措置は正当であるという国際的なコンセンサスを形成することが重要です。また、アメリカ国内でも、極端な保護主義政策に反対する声は少なくありません。
特に、日本への輸出に依存するアメリカの産業界や、自由貿易を支持する政治勢力との連携も検討すべきです。さらに、日本の農業政策が単なる保護主義ではなく、食料安全保障や環境保全、文化的価値の維持など多面的な機能を持つことを国際社会に理解してもらう外交努力も必要です。
輸出促進と国内生産基盤強化の両立
日本政府は、米の輸出促進と国内生産基盤強化を両立させる政策を推進すべきです。
日本産米は品質が高く、海外でも一定の評価を得ています。
特にアジア諸国では日本食ブームもあり、高級米としての需要が存在します。この機会を活かし、日本産米の輸出を積極的に促進することで、国内農家の新たな販路を開拓できます。
同時に、国内生産基盤の強化も不可欠です。
具体的には、農地の集約化や大規模化による生産効率の向上、スマート農業の導入による労働生産性の向上、若手農家の育成や新規就農者の支援強化などが考えられます。
また、ブランド化や有機栽培など付加価値の高い米作りを支援し、単純な価格競争ではなく、品質や特性で差別化する戦略も重要です。
さらに、米だけでなく、複合経営や6次産業化を推進し、農家の収入源を多様化することも、関税撤廃のリスクに対するヘッジとなります。
これらの施策を通じて、国際競争力のある持続可能な米産業の構築を目指すべきです。
農家支援策の再構築
関税による保護機能が低下する中、日本政府は農家支援策を根本的に再構築する必要があります。
従来の価格支持型の政策から、直接支払い型の政策へのシフトが求められます。
環境保全型農業や多面的機能の維持に対する直接支払い、条件不利地域での営農継続に対する支援、若手農家や新規就農者への重点的支援などが考えられます。
米の生産調整(減反政策)の見直しも必要です。
現在の政策は生産量を抑制することで価格を維持する方向ですが、これは国際競争力の向上には逆効果です。むしろ、適正規模での生産を促進し、コスト削減と品質向上を両立させる政策が求められます。
農業保険制度の拡充や、災害時の支援体制の強化など、農家の経営リスクを軽減する施策も重要です。加えて、農業技術の研究開発への投資を増やし、収量増加やコスト削減につながる新技術の普及を促進することも必要です。
これらの支援策は、単に農家の所得を補填するだけでなく、日本の農業の構造改革と競争力強化を促進するものでなければなりません。
若手農家との直接取引関係の構築
消費者レベルでの対策として、若手農家との直接取引関係の構築が重要です。
特に40代以下の後継者がいる農家との関係構築は、長期的な食料確保の観点から非常に価値があります。直接取引には様々な形態があります。オンラインでの産直購入、CSA(Community Supported Agriculture:地域支援型農業)への参加、定期宅配サービスの利用などが代表的です。
これらの方法を通じて、消費者は安定した品質の米を適正価格で購入できるだけでなく、生産者の顔が見える安心感も得られます。
一方、農家にとっても、安定した販路の確保や中間マージンの削減によって、適正な収入を得ることができます。
]消費者との直接的なコミュニケーションを通じて、消費者ニーズを把握し、生産改善につなげることも可能になります。このような直接取引関係は、食料危機時にも強みを発揮します。
一般の流通ルートで米が品薄になり価格が高騰しても、直接取引関係があれば優先的に供給を受けられる可能性が高まります。また、日常的な交流を通じて、農業や食料生産への理解が深まり、食料安全保障の重要性についての認識も高まります。
適切な備蓄と消費行動の見直し
個人レベルでの食料安全保障対策として、適切な備蓄と消費行動の見直しが重要です。
米の備蓄については、家庭の状況に応じた適量を保管することが基本です。
一般的には、1人あたり1〜3ヶ月分程度の備蓄が推奨されています。備蓄する際は、米の冷蔵庫や密閉容器を使用し、品質劣化を防ぐことが重要です。また、定期的に消費し補充する「ローリングストック法」を採用することで、常に新鮮な状態を維持できます。
消費行動の見直しも重要です。例えば、国産米と輸入米をバランスよく使い分ける、米の無駄をなくす調理法を工夫する、米以外の穀物(麦、雑穀など)も取り入れて食生活を多様化するなどの工夫が考えられます。
自家栽培や市民農園の活用など、小規模でも自給自足の要素を取り入れることも一つの選択肢です。
さらに、地域コミュニティでの食料共有システムの構築や、災害時の食料確保に関する地域での話し合いなど、個人を超えた取り組みも重要です。
これらの対策は、食料危機時の備えとなるだけでなく、日常的な食料コストの削減や、食料に対する意識向上にもつながります。
【総括】トランプ関税で日本の米が絶滅?日本の農業への影響
トランプ政権の関税政策は、日本の米産業に短期的にも長期的にも大きな影響を与える可能性があります。
短期的には、自動車産業への25%の追加関税が日本経済に打撃を与え、その対応として米の関税撤廃を求められる可能性があります。もし米の関税が撤廃されれば、安価なアメリカ産米が日本市場に流入し、日本の米農家は価格競争に太刀打ちできなくなるでしょう。
これにより、多くの農家が廃業を余儀なくされ、日本の米生産は急速に縮小する恐れがあります。
長期的には、米の自給率低下による食料安全保障上のリスクが高まります。
国際情勢の変化や気候変動による供給不安、輸出国の自国優先政策などにより、米の安定供給が脅かされる可能性があります。また、一度失われた農地や農業技術、種子などの遺伝資源は、簡単に取り戻すことができません。
このような状況を避けるためには、日本政府は自動車と農業のバランスを考えた交渉戦略を取るとともに、国内の米産業の競争力強化と農家支援策の再構築を進める必要があります。
消費者も、若手農家との直接取引関係の構築や適切な備蓄を通じて、食料安全保障に貢献することが重要です。
トランプ政権の関税政策は、今後の日米関係と日本の農業の行方に大きな影響を与えるでしょう。
日米関係においては、自動車と農業をめぐる貿易交渉が一層厳しさを増すことが予想されます。
トランプ大統領の「アメリカファースト」政策のもと、日本に対してさらなる市場開放を求める圧力は強まるのは間違いなく、日米関係と日本の農業は、今後数年間で大きな転換点を迎えることになるでしょう。
日本人が日本のお米を守るため、何ができるか?私たちが「今できる事」をやるしかないですね。