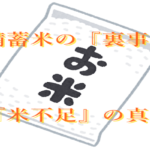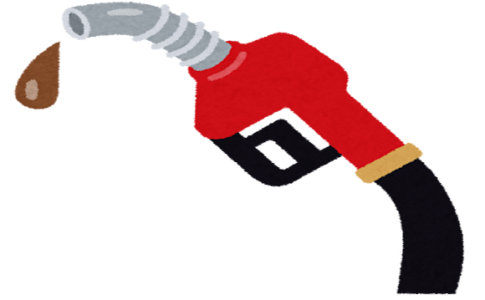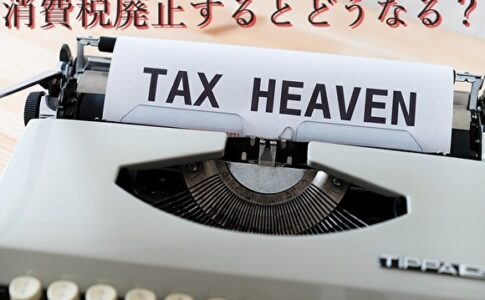スタンドに給油に行くたびに「ガソリン代が高すぎる…」と感じていますよね?
2024年12月、自民党・公明党・国民民主党の三党は、ガソリンの暫定税率廃止を含む税制改正大綱に合意しました。
これが実現すれば、ガソリン価格は1リットルあたり約27.6円引き下がり、40リットル満タン給油で約1,104円の負担軽減となります。
しかし、石破首相は「廃止は既定路線」としながらも、代替財源や地方財政への影響を理由に具体的な実施時期を示していません。
いったいいつから私たちの家計は楽になるのでしょうか?
また、年間1.5兆円の税収減はどのように補填されるのでしょうか?
本記事では、ガソリン税暫定税率廃止の最新動向と実施時期、経済効果、
そして代替財源としての建設国債論について徹底解説します。
【最新動向】ガソリンの暫定税率廃止はいつから?
2025年3月時点『暫定税率廃止』政治状況
野党提出の廃止法案の内容
2025年3月時点で、ガソリン税暫定税率廃止を巡る政治状況は混迷を深めています。
立憲民主党と国民民主党は3月3日に、2025年4月からガソリン税の暫定税率を即時廃止する法案を共同で提出しました。
この法案は、1リットルあたり25.1円の暫定税率を完全に撤廃し、本則税率の28.7円のみを課税するという内容です。両党は、物価高に苦しむ国民生活を守るため、速やかな実施を求めています。
一方、日本維新の会は「準備期間不足」を理由に、2026年4月からの廃止を求める法案を単独で提出しており、野党間でも足並みが揃っていない状況です。この対立は、与党が衆院で過半数割れしている現状において、法案成立の可能性に大きな影響を与えています。

石破首相の発言と政府の立場
石破茂首相は3月3日の衆院予算委員会において、「暫定税率は廃止することは決まっている」と明言しつつも、「代替の財源は何に求めるのか、地方の減収分をどのようにして手当てをするのかについて結論が出ないままに、いつ廃止するということは私どもとして申し上げることはできない」と述べ、具体的な実施時期の明示を避けています。
政府の立場としては、年間約1.5兆円に上る税収減への対応策が最大の課題となっており、特に地方交付税減収分(約5,000億円)の補填策が未確定であることを理由に、慎重な姿勢を崩していません。
ただし石破首相は「今年12月をめどとするのは一つの見識」との考えも示しており、2025年末までには何らかの結論を出す意向を示唆しています。

暫定税率廃止の経緯と背景
暫定税率の歴史と目的
ガソリン税の暫定税率は、1974年に道路整備財源を確保する目的で導入された臨時措置です。
本来は時限立法として一定期間で終了する予定でしたが、道路整備の必要性や財源確保を理由に、約50年にわたり延長が繰り返されてきました。
2009年には道路特定財源制度が廃止され、税収は一般財源化されましたが、暫定税率自体は「特例税率」という名称に変更されつつも実質的に維持されてきました。
この間、1リットルあたり25.1円という上乗せ税率は変わらず、本則税率28.7円と合わせて53.8円という高い税率が課されてきました。
この暫定税率の長期継続は、道路整備から一般財源確保へと目的が変質しながらも、安定した税収源として政府に重宝されてきた歴史を物語っています。

ガソリン税暫定税率廃止はいつから実施される?
【暫定税率廃止いつから】有力視される2026年4月説
2026年4月説が有力視される理由
ガソリン税暫定税率廃止の実施時期として、2026年4月が最も有力視されています。
その主な理由は、政府が2026年度の税制改正において、暫定税率廃止を含む税制の見直しを行うことを検討している点にあります。
2026年4月は新たな会計年度の開始時期であり、税制改正を実施するタイミングとしても適切であるからです。また、日本維新の会が単独で提出した法案も2026年4月からの廃止を求めており、野党の一部からも現実的な時期として支持されています。
さらに、財源確保や地方減収分の補填策を検討するためには一定の準備期間が必要であり、2025年度内の実施は現実的ではないという判断もあります。
政府内では、2026年度予算案や税制改正案を成立させるための野党との取引材料として、この暫定税率廃止を利用する狙いもあるとされています。

【暫定税率廃止いつから】その他の実施時期シナリオ
2025年度内実施の可能性と課題
立憲民主党と国民民主党が提出した法案では、2025年4月からの即時廃止を求めていますが、この実現可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
最大の課題は、年間1.5兆円に上る税収減への対応策が未確定であることです。特に地方交付税減収分の補填策については、総務省と財務省の調整が難航しており、短期間での解決は困難な状況です。
また、2025年度予算案審議における与野党協議が難航した結果、法案成立に必要な衆院3分の2の再可決要件を満たす野党協力体制が構築できていません。
野党間でも足並みが揃わず、日本維新の会は2026年4月からの廃止を主張しています。
ガソリンスタンドや流通業界などの関連事業者からも、システム改修や価格表示の変更などの準備期間が必要との声が上がっており、即時実施には現実的な障壁が多いのが実情です。

2027年度以降に延期されるリスク
財源問題が膠着した場合や政治情勢の変化によっては、暫定税率廃止が2027年度以降に延期されるリスクも否定できません。
過去に国民民主党が2019年に提出した「2年後廃止」法案のように、実施時期を先送りする前例もあります。
また、世界的な原油価格の動向や環境政策の強化など、外部環境の変化によっても実施判断が左右される可能性があります。
さらに、財政再建を優先する財務省や一部与党議員からは、恒久的な税収減となる暫定税率廃止への慎重論も根強く、「やるやる詐欺」と批判される状況が続く可能性もあります。
これらの要因が重なれば、2027年4月以降の実施となる長期シナリオも現実味を帯びてきます。

暫定税率廃止による経済効果
【ガソリン税暫定税率廃止】消費者への直接的影響
ガソリン価格の具体的な変化予測
ガソリン税暫定税率が廃止された場合、ガソリン価格は具体的にどう変わるのでしょうか。
現在、全国平均のレギュラーガソリン価格は1リットルあたり約184円程度ですが、このうち1リットルあたり53.8円がガソリン税分(暫定税率25.1円+本則税率28.7円)、2.8円が石油石炭税分、そして10%の消費税が上乗せされています。
暫定税率25.1円が廃止されると、それに伴う消費税分約2.5円も含めて、合計で約27.6円の値下げ効果が期待できます。
具体的には、20リットル給油した場合、現在の3,680円から3,126円へと約554円の負担軽減となります。
ただし、現在はガソリン補助金(2025年3月時点で1リットルあたり約21.5円)が支給されているため、暫定税率廃止と同時に補助金が廃止された場合、実質的な値下げ幅は小さくなる可能性があります。
それでも、補助金に頼らない恒久的な価格引き下げ効果が期待できるため、長期的には消費者にとって大きなメリットとなるでしょう。
【ガソリン税暫定税率廃止】物流コスト削減と物価への影響
ガソリン税暫定税率の廃止は、物流業界のコスト構造に大きな影響を与えます。
運送業界では燃料費が経費の約2〜3割を占めるとされており、1リットルあたり約27.6円の値下げは、業界全体で年間数千億円規模のコスト削減効果をもたらす可能性があります。
このコスト削減は、物流料金の引き下げや、少なくとも値上げ抑制につながり、最終的には幅広い商品の価格安定化に寄与することが期待されます。
特に食料品や日用品など、物流コストが価格に占める割合が大きい商品については、より顕著な効果が見込まれます。
また、eコマースの拡大に伴い、宅配便の需要が増加している現状においては、配送料の安定化は消費者の購買意欲を刺激し、経済全体の活性化につながる可能性があります。
【ガソリン税暫定税率廃止】地方経済への影響
ガソリン税暫定税率廃止の影響は、都市部よりも地方経済においてより顕著に現れると予想されます。
地方では公共交通機関が十分に整備されていないため、日常生活や経済活動における自動車依存度が高く、ガソリン価格の変動の影響をより強く受けます。
暫定税率廃止による価格引き下げは、地方住民の移動コスト削減につながり、消費活動の活性化や観光需要の増加をもたらす可能性があります。
過疎地域では、ガソリン価格の高騰が「ガソリンスタンド過疎」問題と相まって地域経済の衰退要因となっていましたが、価格引き下げによりこの問題が緩和される可能性があります。
また、地方の基幹産業である農林水産業や製造業においても、輸送コストの削減は競争力強化につながります。
一方で、地方自治体にとっては地方揮発油税(4.4円/L)を含む暫定税率廃止により、年間約4,200億円の税収減少が見込まれており、この穴埋めが大きな課題となっています。
地方交付税の一般財源化比率引き上げ(現行32%→40%案)などの対策が検討されていますが、総務省と財務省の調整が難航しており、地方財政への影響を最小限に抑えるための制度設計が急務となっています。
最終的に、『暫定税率廃止』による代替財源の議論になりますが、『建設国債』一択です。
建設国債による代替財源論
建設国債のメカニズムと効果
建設国債とは、道路や橋梁、ダムなどの公共インフラ整備のための財源として発行される国債のことです。
一般的な赤字国債と異なり、将来世代も利用可能な資産を形成するための投資的経費に限って発行が認められています。
建設国債を活用した公共投資のメカニズムは以下のように機能します。
まず、政府が建設国債を発行し、民間銀行(プライマリーディーラー)がこれを購入します。政府は得た資金でインフラ整備などの公共投資を実施し、資本財を供給する企業に支払いが行われます。この過程で企業の銀行預金(マネーストック)が増加し、同時に企業は利益剰余金という形で資本を蓄積します。
このメカニズムにより、建設国債による公共投資は、信用創造によるマネーストックの増加と、一国経済全体の資本(国富)の増加という二重の経済効果をもたらします。
現在のような低金利環境下では、建設国債の発行コストは歴史的に低く、公共投資の費用対効果は高いと言えます。
建設国債活用の経済理論的根拠
建設国債を代替財源として活用する経済理論的根拠は、現代貨幣理論(MMT)の影響を受けた信用創造の考え方に基づいています。
この理論によれば、現代の貨幣システムは「商品価値設」から「信用価値設」へと移行しており、マネーは銀行システム(中央銀行および民間銀行)の負債として捉えられます。
政府の財源には「負債」(国債など)と「資本」(税収)の2種類があり、公会計の観点からは両方が財源となりうるのです。
建設国債による公共投資は、単なる借金ではなく、経済全体を活性化させる手段となります。
また、国債発行が将来世代への負担の先送りであるという一般的な見方も否定されています。
国債償還は将来世代内での納税者と国債保有者間のマネーストック移転であり、世代間搾取ではないという考え方です。
さらに、建設国債で建設された固定資産は将来世代も利用できるため、純粋な負担ではなく資産の世代間移転と捉えるべきだとされています。
適切な規模の政府債務はレバレッジとして機能し、資本の増大を加速させる効果があるという点も、建設国債活用の理論的根拠となっています。

【参考資料】⇒【桜内文城のNewsとって出し】【ガソリン暫定税率】石破総理の言う「代替財源」は建設国債一択!
【総括】ガソリンの『暫定税率廃止』はいつから?
ガソリン税暫定税率廃止を巡る議論は、2025年3月時点で政府与党と野党間の調整が続いており、実施時期の確定には至っていません。
最も有力視されているのは2026年4月からの実施で、、2026年度税制改正大綱に盛り込む意向を示したものと解釈されています。
一方、立憲民主党と国民民主党は2025年4月からの即時廃止を求めていますが、財源問題や野党間の足並みの乱れから、実現可能性は低いとされています。
代替財源問題については、建設国債の活用が提唱されています。
建設国債による公共投資は、信用創造によるマネーストックの増加と、一国経済全体の資本(国富)の増加という二重の経済効果をもたらすとされています。
暫定税率廃止実現のためには、地方減収分の補填メカニズムの確立と、与野党間の政治取引が不可欠です。
2025年夏の参院選を控え、各党が有権者にアピールできる政策成果を求めている状況は、政治取引の可能性を高めていますが、野党間の足並みの乱れが交渉の障害となっています。
現状の政治力学を考慮すれば、2026年4月実施が最も現実的なシナリオと判断されますが、政治情勢の変化によっては更なる先送りのリスクも否定できません。
正直、飽き飽きしていますが、2025年夏の参院選までの政局の動向に注視が必要になります。