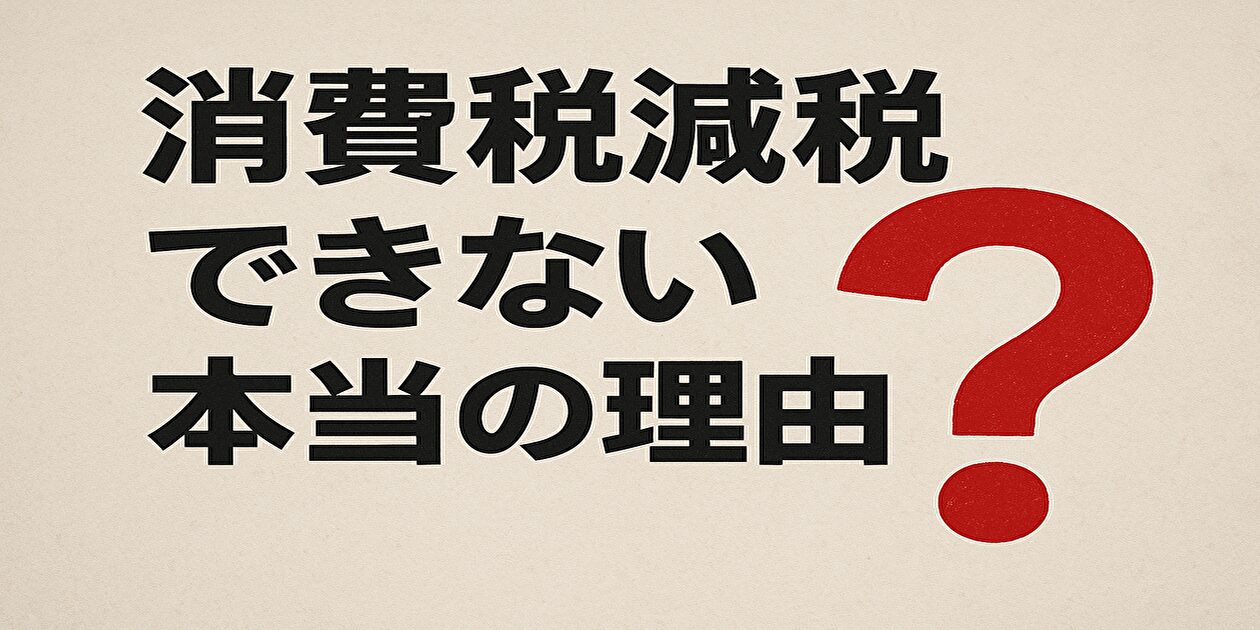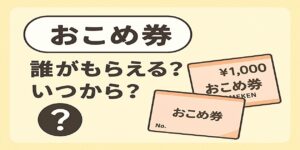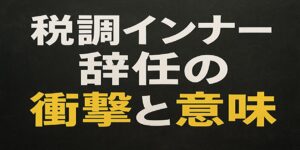「今度こそ生活が楽になるかも…」そんな期待を高市政権に抱いた方も多いのではないでしょうか。
総理になる前は「食料品の消費税ゼロ」と力強く語っていたのに、いざ政権が始まると「レジの改修が…」と慎重な姿勢に・・・。
この「手のひら返し」に、がっかりや怒りを感じていませんか?
この記事では、なぜ高市政権は消費税減税を「できない」のではなく「やらない」のか、その裏に隠された政治の壁を、誰にでも分かるように徹底解説します。
 杉山 制空
杉山 制空ただ、高市総理は、消費税減税をあきらめたわけではないので、私個人としては引き続き見守りたいと思っています。
高市政権はなぜ消費税減税を「やらない」のか?期待から失望への転換
総理就任前の「食料品消費税ゼロ」公約
高市早苗氏は2025年5月、国会で「国の品格として食料品の消費税率は0%にすべき」と明確に主張していました。
歴史的な物価高騰に苦しむ国民にとって、この発言はまさに希望の光でした。
特に、従来の政権とは異なる大胆な経済政策への期待が、高市新政権への80%を超える高支持率につながったのです。食料品という生活必需品への減税は、即効性のある物価高対策として多くの国民が固唾をのんで見守っていた最重要政策の一つでした。
高市政権発足後の「手のひら返し」批判
しかし、総理就任後の国会答弁で高市氏の姿勢は一変します。2025年11月の衆議院予算委員会では、立憲民主党や参政党からの消費税減税要求に対し、「事業者のレジシステムの改修等に一定の時間がかかる」と慎重姿勢を示しました。
この急な方針転換は「手のひら返し」として厳しい批判を浴びることになります。
自らが他者を批判した論理を、今度は政策拒否の盾として用いる姿勢に、支持者の信頼は大きく揺らぎました。



正直、この発言は発するべきはなかったと思います。理由としては、この発言は「財務省からのレクチャー発言」そのままだからです。なぜ?高市総理がこの発言をなさったのか?理解に苦しみます。
JNN世論調査が示す国民の期待
2025年11月1・2日にJNNが実施した世論調査では、「物価高対策で期待する政策」として最も期待が高かったのが「食料品の消費税ゼロ(30%)」でした。
国民の3割が最優先課題として消費税減税を求めているにもかかわらず、政権はその期待に応えられていません。立憲民主党が10月31日に「食料品の消費税を最長2年間ゼロにする法案」を提出したことも、この国民世論を反映したものです。
しかし高市総理は従来の慎重姿勢を崩さず、期待と現実の乖離がさらに広がっています。
高市政権が消費税減税「できない」表向きの理由
繰り返される「レジシステム改修」という説明の矛盾
高市総理が消費税減税に踏み切れない理由として繰り返し挙げているのが、「レジシステムの改修に時間がかかる」という技術的な問題です。
11月の国会答弁でも「事業者のレジシステムの改修等に一定の期間がかかる等との課題にも留意が必要」と述べ、この説明を公式見解としています。
現場からは「即日対応可能」の声
しかし、この「レジ問題」は実態とはかけ離れているという指摘が相次いでいます。
元内閣官房参与の本田悦朗氏が複数のスーパーマーケットの現場責任者に確認したところ、「即できます」「すぐやります」との回答を得たと証言しています。実際に、小売店のレジは日常的に特売やセールで価格変更を行っており、税率変更だけが技術的に乗り越えられない壁とは考えにくいのが現実です。本田氏は「1年もかかるわけがない。でも、自民党の中で反対が多い」と、技術的問題ではなく政治的問題であることを明言しています。
⇒消費税減税の壁?高市総理が主張のレジシステム変更は「即できます」元内閣官房参与が明言「1年もかかるわけがない」(デイリースポーツ) – Yahoo!ニュース
高市総理、過去の自身の発言との鮮やかな矛盾
この問題が特に「手のひら返し」として批判される理由は、高市総理自身の過去の発言との矛盾にあります。
高市政権が消費税減税「できない」「やらない」3つの壁(本当の理由)
本当の壁①:自民党内の根強い反対勢力
「少数派で負けた」という総理の告白
高市総理が消費税減税を実現できない最大の障壁は、自民党内の根強い反対勢力です。
高市総理自身も国会答弁で「自民党の税制調査会では賛同を得ることはできなかった。自分が所属する政党で賛同を得られないことをいつまでも突き通すというわけにもまいりません」と述べています。さらに「党内で意見が真っ二つなんですから。私は少数派で負けた」とまで告白しており、総理でありながら党内において消費税減税を支持する派閥が少数派に追い込まれている実態が明らかになっています。
税制調査会と財務省の強い抵抗
自民党税制調査会は、消費税を社会保障財源の柱と位置づけており、その減税には極めて慎重です。
さらに財政規律を重視する財務省も、年間5兆円規模の税収減につながる消費税減税に強く反対しています。
元内閣官房参与の本田氏も「レジシステムの変更に1年もかかるわけがない。でも、自民党の中で反対が多い」と指摘しており、技術的問題ではなく党内・官僚機構の政治的抵抗が本質であることを明らかにしています。
高市総理のリーダーシップだけでは覆せない厚い岩盤が存在しているのです。
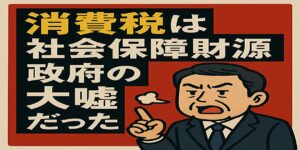
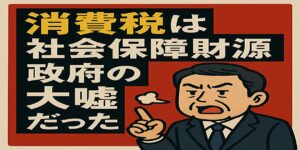
本当の壁②:連立合意の「検討」という玉虫色の文言
自民・維新連立合意の中身
2025年10月20日に自民党と日本維新の会が調印した連立政権合意書では、食料品の消費税率について「2年間ゼロにすることを視野に、法制化を検討する」と記されています。
一見すると減税に前向きな文言に見えますが、重要なのは「検討する」という表現に留まっている点です。
つまり、法的に「実施する」と明確に約束したものではなく、あくまで「検討」という努力目標に過ぎません。この玉虫色の文言が、高市総理にとって減税を先送りするための格好の言い訳となっています。
「検討」で逃げ続ける政治文化
日本の政治において「検討する」という言葉は、実質的な議論や実行を先送りする常套句として使われてきました。今回の連立合意も例外ではありません。
国会で野党から消費税減税の実行を迫られても、高市総理は「連立合意に基づき検討を進める」と繰り返すことで、具体的な実行時期や方法論についての明言を避けることが可能になっています。
レジシステムって聞いたときに「?」ってなりましたね。
— 友(とも)@ああちゃん (@t_i_suzuka) November 9, 2025
私もスーパーで社員やってましたが、あんなもんボタン一つでしょ。
お会計するレジ自体は全く問題なしです。
言い訳せずに時間がかかる理由を明確に示してほしいです。 https://t.co/0Vsa3Lzs7Y
連立維持のための政治的妥協
この曖昧な合意文書は、連立政権を維持するための政治的妥協の産物と言えます。
自民党内では消費税減税に反対する勢力が多数派を占める一方、日本維新の会は減税を強く求めています。
現時点では、両者の主張の隔たりを埋めるため、「視野に入れて検討」という玉虫色の表現で折り合いをつけたということでしょうか・・・。
本当の壁③:農林族という「見えない岩盤」
食料品減税が触れる農政のタブー
消費税減税、特に食料品を対象とした減税が難しいもう一つの理由として、自民党の伝統的な支持基盤である「農林族」の存在が指摘されています。
日本の農業政策は長年、関税や減反政策によって国内の農産物価格を高く維持することで農家を保護してきました。食料品の消費税をゼロにすれば一時的に価格は下がりますが、根本的な物価高対策にはならず、むしろ農業保護政策そのものを見直す必要性が浮き彫りになります。
「米価を下げたくない勢力」の影響
高市政権内部には「米価を下げたくない農林族」が潜り込んでいるとの指摘もあります。
本当に物価を下げるためには、農業保護政策を抜本的に見直し、市場原理を導入する必要がありますが、これは農林族議員や農協などの関連団体から強い反発を招きます。
そのため、高市政権は消費税という国民に分かりやすいテーマで議論を紛らわせ、農政という聖域に手を付けることを避けているのではないかとの見方があります。
消費税減税ができない背景には、こうした自民党の構造的な利益調整メカニズムが横たわっているのです。


物価高対策の根本的ジレンマ
単純な消費税減税だけでは、食料品価格の根本的な低下にはつながらないという構造的な問題も存在します。
日本の食料品が高いのは、消費税だけが原因ではなく、高関税、流通の非効率、農業の生産性の低さなど、複合的な要因が絡み合っています。しかし、これらの根本原因に切り込むことは、自民党の支持基盤を揺るがすことになるため、政治的に極めて困難です。
代替案としての「給付付き税額控除」の問題点
高市総理が前のめりな姿勢を示す理由
消費税減税が困難な中、高市総理が代替案として積極的に推進しているのが「給付付き税額控除」です。
立憲民主党が参院選の公約に掲げていたこの制度について、高市総理は「立憲より先に提唱していた」と述べるなど前のめりな姿勢を示しています。給付付き税額控除とは、所得税を控除しきれない低所得者層にも現金給付という形で恩恵が及ぶ仕組みで、一見すると公平な制度に見えます。


実現には2〜3年かかる制度設計の複雑さ
しかし、この制度には大きな課題があります。
高市総理自身も「実現には2〜3年かかる」と認めているように、制度設計が非常に複雑です。
即効性を求める国民との乖離
物価高に苦しむ国民が求めているのは、今すぐに効果が出る対策です。
しかし、給付付き税額控除は制度設計に2〜3年かかり、消費税減税のような即効性はありません。参政党の神谷代表が「なぜ総理は消費税減税を避け、制度設計に時間を要する給付付き税額控除にかじを切ろうとしているのか」と追及したのは、まさにこの点を突いたものです。結局のところ、党内・財務省の反対を回避できる「時間稼ぎ」の政策として給付付き税額控除が選ばれているのではないかとの疑念が広がっています。
ガソリン暫定税率廃止という成果と不安
年内廃止で正式合意の意義
高市政権が物価高対策として唯一実現にこぎつけたのが、ガソリン暫定税率の廃止です。


「減税の代わりに増税」という本末転倒
少し不安な点は、「ガソリン減税の代わりに増税を」という話が与党筋から出てきている点です。



個人的には、ガソリン減税の代わりに走行距離課税(走行税)が検討されているという噂が気になります。それこそ本末転倒ですからね。
《総括》高市政権は消費税減税を「やたない」ではなく「今はできない」
高市政権下での消費税減税は、現状では実現のハードルが極めて高いと言わざるを得ません。
しかし、これで消費税減税の議論が完全に終わったわけではありません。
歴史的な物価高が続く限り、減税を求める国民の声がやむことはないでしょう。今後の景気動向次第では、経済状況がさらに悪化し、より強力な物価高対策が求められる事態も十分に考えられます。そうなれば、政権も方針転換を余儀なくされる可能性があります。



実際に、高市総理は「消費減税をあきらめたわけではない」と言っています。
高市総理の正確な立場:「あきらめたとは言っていない」
「選択肢として排除するものではございません」 – 食料品の消費税率引き下げについて、完全に否定しているわけではないという立場を明確にしています。



「あきらめたとは言っていない」 – 消費税減税の可能性を将来的には残している姿勢を示しています。私は高市総理を支持します。
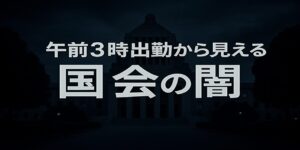
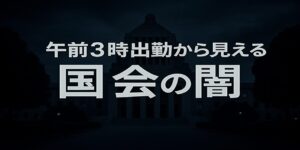
「やらない」と「今はできない」の違い
重要なのは、高市総理は以下のような段階的な考え方を示しているということです:
- 短期(現在): 党内の反対が強く、今すぐには実施できない
- 中期: 自民党と日本維新の会の協議会で検討を進める
- 長期: 経済状況が改善し、税収が増える状態を作れば将来的には実現可能
というのが実態です。
また、来たるべき国政選挙において、消費税減税が再び最大の争点となる可能性も十分にあります。
その時、有権者の厳しい審判を前にして、政権与党がどのような判断を下すのか。今回の「期待外れ」が、将来の大きな政策転換への布石となるのか、あるいは単なる失望で終わるのか。それを決めるのは、政治家ではなく、私たち国民一人ひとりの選択と行動です。
今後も高市政権の動きを、注意深く見守る必要があります。