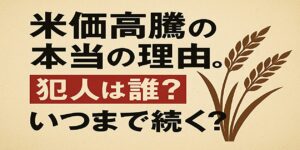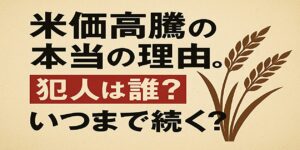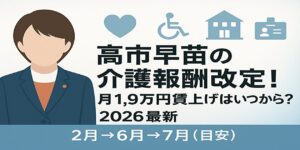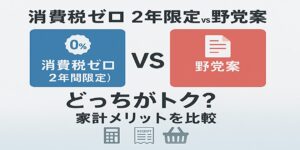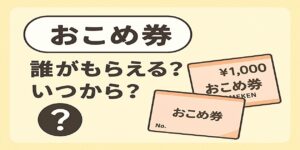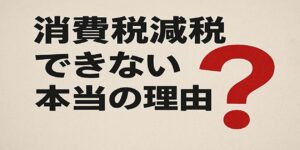2025年10月、初の女性総理として高市早苗内閣が誕生し、日本の農業政策は大きな転換点を迎えました。
新政権が掲げるのは、農業を成長産業へと変革する「稼げる農業」の実現です。
そのキーマンとして農林水産大臣に抜擢されたのが、農水省出身で「米マニア」とも呼ばれる農政のプロ、鈴木憲和氏です。 石破前政権の増産路線を転換し、市場原理を重視する姿勢を鮮明に打ち出しています。
しかし、この改革は本当に日本の農業が抱える後継者不足や所得の低さといった構造問題を解決できるのでしょうか・・・。それとも、理想ばかりが先行し、現場の農家は置き去りにされてしまうのでしょうか。
本記事では、鈴木新農相の具体的な方針や手腕を徹底分析し、「稼げる農業」の実現可能性と、私たちの食卓への影響を深く掘り下げていきます。
 杉山 制空
杉山 制空筆者の父の実家は、広島県の呉市で農業を営んでいますので、高市政権の農業政策に期待しながらも、やはり不安も感じています。そして鈴木農水大臣の発言にも、現時点では「所得補償」についての説明不足を感じているのが正直なところです・・・ということで、この記事を書きました。
高市政権の農業政策で日本はどう変わる?
なぜ今、農業政策が注目されているのか?
近年、異常気象や国際情勢の不安定化により、食料を海外に頼ることのリスクが世界中で高まっています。
日本でも、2024年の「令和の米騒動」は記憶に新しく、食料の安定供給が国民的な関心事となりました。こうした背景から、高市首相は農業を単なる産業ではなく、国の安全を守る「食料安全保障」の要と位置付けています。新政権がどのような農業の未来を描き、実行していくのかに、国民の大きな注目が集まっているのです。
この記事でわかること
この記事を最後まで読めば、高市政権の農業政策のポイントが明確に理解できます。具体的には、「新しい農林水産大臣はどんな人?」、「お米の生産はどう変わるの?」、「食料自給率100%って本当?」といった疑問にすべてお答えします。難しい政治の話を、私たちの身近な「食」の視点から紐解いていきましょう。
高市政権の農業政策、3つの柱
高市政権の農業政策は、単なる付け焼き刃の対策ではありません。
「稼げる農業」と「食料安全保障の確立」という2大ビジョンを実現するため、3つの大きな柱で構成されています。
柱①:経済安全保障としての食料政策
高市政権の農業政策の根幹をなすのが「食料は経済安全保障の要」という考え方です。
これは、食料生産に必要な肥料や飼料の多くを輸入に頼る日本の現状に危機感を持ち、国内での生産基盤を強化しようとするものです。例えば、肥料の原料となるリン鉱石や塩化カリウムは、中国など特定の国への依存度が高く、供給が止まれば日本の農業は大きな打撃を受けます。そのため、肥料の国内備蓄を支援したり、代替原料の開発を進めたりすることで、海外に依存しない強い農業体制の構築を目指しています。
柱②:「稼げる農業」への構造転換
長年、日本の農業は「守り」の政策が中心でしたが、高市政権は農業を成長産業と位置づけ、「攻め」の農政へと転換しようとしています。
その実現のために掲げられたのが、5年間の「農業構造転換集中対策期間」です。
この期間に別枠の予算を確保し、世界トップレベルの植物工場やAI、ドローンといった先端技術の導入を強力に後押しします。耕作放棄地を減らし、農地を集約して大規模化を進めることで生産性を向上させ、農家が安定して高い収益を上げられる「稼げる農業」への転換を目指すのです。
柱③:食料自給率「限りなく100%」への挑戦
高市首相は、総裁選の段階から「食料自給率を限りなく100%に近づける」という野心的な目標を掲げています。
これは、前述の「食料安全保障」を具現化するための象徴的な政策です。
主食であるお米だけでなく、これまで輸入に頼ってきた小麦や大豆などの国内生産を増やし、食料全体の国産割合を高めていくことを目指します。この目標達成のため、これまでの生産調整(減反)政策を見直し、生産者の意欲を引き出す新たな仕組みづくりが検討されています。
【新農相】鈴木憲和大臣はどんな人?政策はどう変わる?
鈴木新農相の経歴と人物像
鈴木憲和氏は、農林水産省出身で、農業の現場と政策の両方に明るい実務家です。
私の農林水産大臣就任記者会見(令和7年10月22日) です。
— 鈴木憲和 (@norikazu_0130) October 24, 2025
よかったらご覧ください。
記者さんからの質問にも出来る限り丁寧に答えたつもりです。
報道振りは、紙面や番組時間の制約があるため切取りになることも致し方ないので、正解な情報が必要な方はぜひ!https://t.co/svIqK4sb0P @YouTubeより
石破前政権からの転換点:コメ増産路線の見直し
鈴木大臣が就任後、最も明確に打ち出したのが、石破前政権が進めた「コメ増産」路線の見直しです。
備蓄米は放出しない?市場原理を重視する姿勢
鈴木大臣は、米価高騰への対策として注目されていた「備蓄米の放出」について、「供給が十分な時に備蓄米を放出すべきではない」と述べ、現時点では実施しない方針を明言しました。
小泉前農相が進めた積極的な放出政策とは一線を画すものであり、高市政権の農政における大きな転換点と言えるでしょう。
具体的にどうなる?米政策の今後の方向性
では、具体的に私たちのお米の生産や価格は今後どうなっていくのでしょうか。
新政権の方針から見える今後の方向性を整理します。
2026年産米は「減産」へ
高市政権は、2026年産の主食用米の生産目標について、2025年の見込み(約748万トン)から約5%少ない711万トン程度に設定する方向で調整に入っています。 これは、米余りによる価格下落を防ぎ、農家の経営を守るための措置です。 石破前政権の「増産」から「減産」へと、静かながらも明確な方針転換が進んでいることがわかります。
価格高騰対策は「おこめ券」を検討
備蓄米を放出しない代わりに、鈴木大臣が消費者向けの価格高騰対策として検討しているのが「おこめ券」の配布です。これは、市場価格に直接介入するのではなく、消費者の負担を直接的に和らげることで対応しようという考え方です。これにより、市場の価格形成機能を維持しつつ、家計への影響を緩和する狙いがあります。
中長期的には「輸出」で需要拡大を目指す
短期的には減産へと舵を切る一方、中長期的には日本の高品質な米を海外に輸出することで、新たな需要を創出し、生産量を再び増やしていくことも視野に入れています。 高市政権が掲げる「稼げる農業」の実現には、国内市場だけでなく、海外市場の開拓が不可欠です。 円安を追い風に、日本の米のブランド価値を高め、輸出を農業の新たな収益の柱に育てていく戦略です。
【高市政権の農業政策】地域別の農家の反応
米の生産が盛んな地域では、今回の政策転換が経営に与える影響が大きいため、特に様々な声が上がっています。
東北地方(秋田県、山形県)
- 減産方針への賛同と安堵: 秋田県の複数の農業関係者からは、近年の米価下落に苦しんできた背景から、減産による価格安定への期待が非常に大きいとの声が聞かれます。 石破前政権の増産路線には強い懸念があったため、今回の方針転換を「ようやく現場の声が届いた」と歓迎する農家も少なくありません。
- 所得補償への強い要望: 一方で、山形県の若手農家からは、生産数量が直接収入に響くため、減産に参加する農家への十分な所得補償がなければ、経営が成り立たないという切実な意見も出ています。 特に、規模拡大を進めてきた農家ほど、作付面積の減少による影響は深刻です。
- 飼料用米などへの転換の課題: 主食用米からの転換先として飼料用米などが挙げられますが、収益性の低さから積極的な転換には至っていないのが現状です。 政策的な後押しがなければ、転換は進まないとの指摘があります。
北陸地方(新潟県)
- ブランド米産地としての期待: 新潟県のJA関係者は、減産によって需給が引き締まれば、高品質なブランド米の価値がさらに高まり、有利な価格で販売できる可能性があると期待を寄せています。 米価が安定すれば、後継者の確保にも繋がると考えています。
- 輸出戦略への関心: 高品質な米を生産する農家が多いことから、政府が掲げる輸出拡大戦略への関心が高い地域です。 すでに独自に輸出に取り組んでいる生産者もおり、政府の支援策が具体化されることを待望する声が上がっています。
- 過剰作付けへの懸念: 一部の農家からは、減産方針が示されても、価格上昇を見込んで自主的に作付けを増やす生産者が出てくるのではないかという懸念も示されています。 これが結果的に米価の不安定化を招くことを心配しています。
北海道の反応
- 冷静な受け止めと多角化の強み: 北海道の農業関係者は、主食用米への依存度が他の地域に比べて低いため、今回の減産方針を比較的冷静に受け止めています。 多くの農家が飼料用米や加工用米、小麦、大豆などとの輪作体系を確立しており、主食用米の減産分を他の作物でカバーできる経営体力があるためです。 このため、大きな混乱は見られていません。
- 輸出への高い関心と実績: 「ゆめぴりか」や「ななつぼし」といったブランド米は、すでに海外でも評価が高く、輸出に積極的に取り組む農家や団体が多いのが北海道の特徴です。 政府の輸出拡大戦略は、こうした動きをさらに後押しするものとして、大きな期待が寄せられています。 円安を追い風に、さらなる販路拡大を目指す声が強く聞かれます。
- スマート農業による効率化: 北海道の広大な農地では、スマート農業技術の導入が進んでいます。 GPSガイダンスシステムを搭載したトラクターやドローンによる農薬散布など、生産性の向上に常に取り組んでおり、減産方針の中でも効率的な農業経営を維持しようとする動きが見られます。
九州地方(福岡県、熊本県)
- 減産への協力姿勢と所得補償への期待: 熊本県や福岡県のJA関係者からは、国の減産方針に協力する姿勢が示されています。 これまでの米価下落の経験から、需給バランスの改善は不可欠であると認識されており、価格安定に向けた政策を評価する声が主流です。 ただし、東北地方などと同様に、減産に伴う所得の減少を補うための手厚い交付金や支援策を強く求めています。
- 高温障害への対策が急務: 近年、夏の猛暑による高温障害で米の品質が低下する「白未熟粒」などの被害が深刻化しています。 このため、農家の関心は減産そのものよりも、気候変動に対応できる高温耐性品種の開発や、栽培技術の確立に集まっています。 政策に対しても、こうした気候変動対策への支援を期待する声が大きいです。
- 輸出ポテンシャルの模索: 九州産の米は、アジア市場に近いという地理的優位性があります。 このため、政府の輸出戦略をビジネスチャンスと捉え、輸出向けの米生産に関心を示す若手農家も増えています。 今後は、現地のニーズに合った品種の選定や、物流網の整備が課題となります。
高市政権の農業政策、期待と課題
新しい農業政策には、大きな期待が寄せられる一方で、乗り越えるべき課題も山積しています。
期待される効果:食料の安定と農家の経営改善
高市政権の政策がうまく機能すれば、まず期待されるのが食料の安定供給です。
需要に応じた生産が行われることで、米価の極端な乱高下を防ぎ、生産者も消費者も安定した環境を手に入れることができます。 また、「稼げる農業」が実現すれば、農業が魅力的な職業となり、後継者不足の解消や耕作放棄地の減少につながる可能性もあります。 女性初の総理として、女性農業者の活躍を後押しするような「女性の発想での農業政策」にも期待が寄せられています。
残された課題:財源の確保と政策の一貫性
最大の課題は、これらの政策を実行するための「財源」をどう確保するかです。
「農業構造転換」には多額の予算が必要となりますが、その具体的な捻出方法はまだ示されていません。また、短期的には「減産」しつつ、中長期的には「輸出で増産」を目指すという政策は、一貫性を保ちながら実行するのが難しい側面もあります。市場の状況を見ながら、いかに柔軟かつ的確に政策を調整していけるか、鈴木大臣の手腕が問われることになります。
【高市政権の農業政策】よくある質問(Q&A)
質問1.高市政権になって、お米の値段はすぐに安くなりますか?
答え1.すぐに安くなる可能性は低いです。鈴木新農相は、米価は市場に委ねるべきという考えを示しており、備蓄米の放出など政府が直接価格を下げる政策には慎重です。価格が高騰した場合は、「おこめ券」の配布などで消費者の負担を和らげる策が検討されています。
質問2.「食料自給率100%」は本当に実現可能なのでしょうか?
答え2.「限りなく100%に近づける」という目標であり、完全に達成するのは非常に困難です。しかし、この高い目標を掲げることで、国内生産の重要性を国民全体で共有し、生産基盤の強化、技術革新、輸出促進など、農業構造の抜本的な改革を進める強いメッセージとなっています。
質問3. 農業政策が変わると、私たちの食生活にどんな影響がありますか?
答え3.短期的には、米価が急激に下がることは考えにくく、安定的な価格帯で推移する可能性があります。中長期的には、「稼げる農業」が進むことで、国産の野菜や果物、畜産物などの品質が向上し、多様な選択肢が増えるかもしれません。また、米粉を使ったパンや麺類など、お米の新しい食べ方が普及する可能性もあります。
《総括》【高市政権の農業政策】鈴木新農相で「稼げる農業」は実現する?
高市政権の農業政策は、「食料安全保障」を最重要課題と位置づけ、「稼げる農業」への転換を目指すものです。
この農業政策は、日本の農業が長年抱えてきた構造問題にメスを入れる、大きな挑戦です。
先端技術の導入や輸出強化による「稼げる農業」が実現すれば、農業は若者にとって魅力的な産業に生まれ変わり、日本の食料自給率は大きく向上するでしょう。
しかし、その道のりは平坦ではありません。
財源の問題、国際競争、そして何より国内の合意形成という高いハードルが待ち構えています。成功すれば、日本の食卓はより豊かで安全なものになりますが、失敗すれば食料の海外依存はさらに進むかもしれません。
私たちは今、日本の農業、そして食の未来を決める大きな分岐点に立っているのです。
新政権の舵取りに期待しつつも、その行方を厳しく見守っていく必要があるのです・・・。