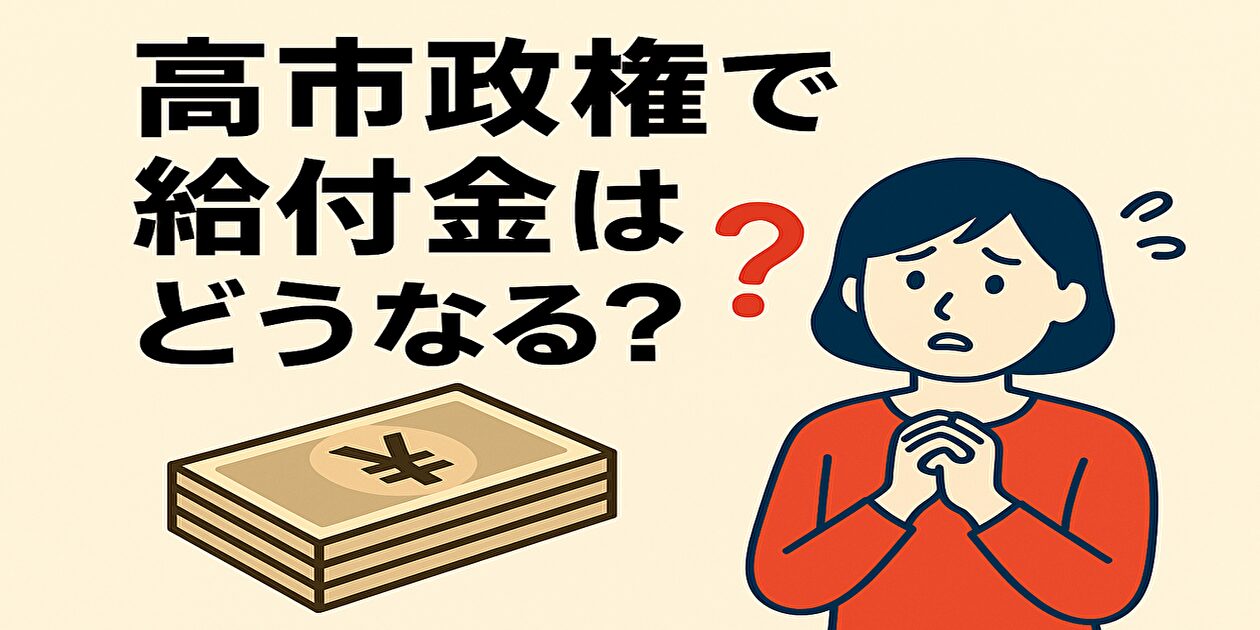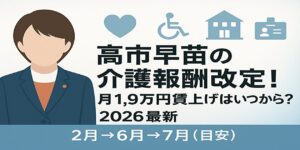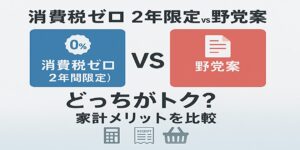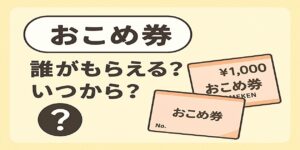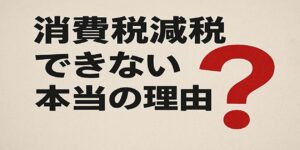結論から言いますと、高市政権下でこれまでのような「一律現金給付金」が行われる可能性は極めて低くなりました。
高市首相は、一律給付の中止を明言し、代わりに所得に応じて支援額が変わる「給付付き税額控除」の導入を急いでいます。
この変更は、私たちの家計にどのような影響を与えるのでしょうか?
 杉山 制空
杉山 制空現役世代に不評の給付金、しかしながら、私たち配食サービスのご利用者様となる、高齢者の非課税世帯には、出来る事なら給付されたい状況になります。
この記事では、新しい制度で「誰が」「いつ」「いくら」もらえるのか、そして一律給付に代わる他の物価高対策は何か、最新情報を基に徹底解説します。



高市政権の新しい経済政策を正しく理解すれば、最大16万円の給付を受けられるかもしれませんよ。
【結論】高市政権で「一律給付金」どうなる?実施されません!
高市首相が「一律給付の中止」を明言
高市早苗首相は2025年10月21日の記者会見で、多くの国民が期待していた1人あたり数万円規模の「一律現金給付」を実施しない方針を明確にしました。
この決定の背景には、夏の参議院選挙で一律給付策が国民の幅広い支持を得られなかったとの判断があります。政府は、一時的な「バラマキ」と批判されがちな政策から、より持続可能で構造的な家計支援へと舵を切ることを宣言した形です。この方針転換は、今後の政府の経済対策の根幹をなすものであり、私たちの生活に直接影響を与える重要なポイントです。



一律給付という分かりやすい支援がなくなることで、不安を感じる方も多いかもしれませんが、政府は新たな支援の枠組みを準備していますので、あと少し待ちましょう・・・。
なぜ一律給付は中止になったのか?
一律給付が中止された最大の理由は、その効果と公平性に対する疑問です。
物価高に苦しむ低所得世帯も、所得に余裕のある富裕層も同じ金額を受け取る仕組みは、「本当に支援が必要な人に届いていない」という批判が常にありました。また、給付金の多くが消費に回らず貯蓄に流れる「貯蓄性向」の高さも問題視されていました。高市政権は、これらの課題を踏まえ、限られた財源をより効果的に活用するため、支援対象を絞り込む「選別主義」へと大きく方針転換したのです。この決定は、連立を組む日本維新の会が主張する「小さな政府」や効率的な財政運営の考え方も反映されています。今後は、支援を必要とする層へ、より手厚く、かつ的確に支援を届ける仕組みが求められます。



2万円の給付金が、本当に貯蓄に回るか?は少し疑問ですね。それほど一般国民の生活はひっ迫しているので、給付金の実施も一時的な物価対策として機能しそうに思えるのですが、どうでしょう?
【新制度】「給付付き税額控除」とは?
「給付付き税額控除」の基本的な仕組み
「給付付き税額控除」は、高市政権が家計支援の新たな柱として導入を目指す制度です。
これは、所得税から一定額を差し引く「税額控除」と、税額が控除額に満たない場合に差額を現金で支給する「給付」を組み合わせたものです。
あなたは対象?【最大16万円】給付額のシミュレーション
給付額は世帯の年収によって変動する見込みです。
あくまで試算段階ですが、以下のようなモデルが示されています。
年収670万円未満の世帯:最大16万円
年収670万円~1232万円未満の世帯:所得に応じて段階的に減額
年収1232万円以上の世帯:対象外
このシミュレーションは、今後の議論で変更される可能性はありますが、低・中所得世帯を重点的に支援するという方向性は揺るがないでしょう。 例えば、4人家族で夫の年収が500万円の場合、満額の16万円が給付される可能性があります。この制度は、物価高で実質的な所得が目減りしている子育て世帯や若者世帯にとって、大きな支えとなることが期待されています。
【時期】「給付付き税額控除」はいつから始まる?
制度設計と導入までのスケジュール
高市首相は、「給付付き税額控除」の制度設計を年内に開始する意向を表明しています。
現在、与野党の垣根を越えた協議会が設置され、具体的な制度設計が進められています。 この制度は、各個人の所得を正確に把握する必要があるため、マイナンバー制度と公金受取口座の活用が前提となります。政治的な環境は整いつつあり、日本維新の会や立憲民主党も同様の制度導入を主張しているため、実現に向けた動きは加速するでしょう。
今から準備しておくべきこと
「給付付き税額控除」をスムーズに受け取るためには、事前の準備が重要になります。
この制度は、申請が不要な「プッシュ型」での給付が検討されており、その基盤となるのがマイナンバーカードと公金受取口座です。 まだマイナンバーカードを取得していない方や、公金受取口座の登録を済ませていない方は、早めに手続きをしておくことを強く推奨します。手続きは、スマートフォンのアプリや市区町村の窓口で簡単に行えます。いざ給付が決定した際に、慌てずに済むよう、今のうちから準備を進めておきましょう。また、確定申告が必要な自営業者やフリーランスの方は、日頃から所得を正確に申告しておくことが、適正な給付を受けるための第一歩となります。
【その他】一律給付に代わる他の物価高対策
ガソリン税の引き下げと光熱費補助
高市政権は、「給付付き税額控除」と並行して、即効性のある物価高対策も進めています。
その筆頭が、ガソリン価格を直接引き下げる「ガソリン税(揮発油税)の暫定税率廃止」です。
これが実現すれば、レギュラーガソリン1リットルあたり約25円の負担減となり、通勤や物流コストの抑制に繋がります。また、高騰が続く電気・ガス料金については、既存の補助金制度を当面継続する方針です。これらの対策は、日々の生活コストを直接的に押し下げる効果があり、多くの国民が恩恵を受けることができます。給付金という形ではありませんが、可処分所得を増やすという意味で重要な家計支援策と言えるでしょう。
高市早苗総理 所信表明演説
— あーぁ (@sxzBST) October 24, 2025
「いわゆるガソリン暫定税率は今国会での廃止法案の成立を期します。軽油引き取り税の暫定税率も早期の廃止を目指します」
ついにキタ ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
ほんと高市さんが去年総理になっとけばよかったんじゃん。
マジで何だったの?この一年。 pic.twitter.com/rE6qlAT1lv
103万円の壁の引き上げ
2025年の年末調整では160万円まで対応することが決定しており、将来的には物価に連動した形でさらに引き上げる制度設計を進めています。
重点支援地方交付金の拡充
地方自治体が地域の実情に応じて支援策を実施できるよう、交付金を積み増しする方針です。 これにより、独自の給付金や商品券配布、省エネ家電への補助などが各自治体の判断で実施できます。
中小企業支援と賃上げ促進策
物価高を乗り越えるためには、家計への直接支援だけでなく、経済の好循環を生み出すことも不可欠です。
高市政権は、日本経済の屋台骨である中小企業への支援を強化し、持続的な賃上げを実現することを目指しています。具体的には、赤字に苦しむ中小企業でも賃上げを実施できるよう、新たな支援策を検討しています。 生産性向上を後押しする補助金や、賃上げを行った企業に対する社会保険料負担の軽減などが議論されています。企業の収益が改善し、それが従業員の給与に反映されるようになれば、物価上昇分を吸収できる強い家計が生まれます。
これは、一時的な給付金よりも根本的な生活安定に繋がる、中長期的な視点に立った重要な政策です。
高市政権で給付金はどうなる?よくある質問(Q&A)
Q1. 結局、2025年に現金がもらえる給付金はないのですか?
A1. 全国一律で全員に配られる現金給付金は、実施されないことが決定的です。しかし、2025年末の開始を目指している「給付付き税額控除」によって、所得の低い世帯を中心に現金が給付される予定です。年収670万円未満の世帯では最大16万円の給付が見込まれており、これが実質的な給付金となります。
Q2. 非課税世帯向けの7万円や10万円の給付金はどうなりますか?
A2. これまで実施されてきた住民税非課税世帯などを対象とした7万円や10万円の給付金は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環でした。高市政権では、こうした単発の給付金を繰り返すのではなく、恒久的な制度である「給付付き税額控除」に一本化していく方針です。したがって、今後は「非課税世帯向け」という形での新たな給付金が発表される可能性は低いと考えられます。
Q3. 「給付付き税額控除」はいつ、どうやって申請すればいいですか?
A3. 給付開始は2025年末を目指して現在制度設計が進められています。申請方法は、マイナンバーカードに紐づけられた公金受取口座へ自動的に振り込まれる「プッシュ型」が有力です。そのため、個人での特別な申請は不要になる可能性が高いです。今のうちにマイナンバーカードの取得と公金受取口座の登録を済ませておくと、スムーズに給付を受けられます。正式な手続きについては、今後政府から発表される情報を確認してください。
【総括】高市政権で給付金はどうなる?
「結局、給付金はもらえないの?」そんな落胆の声が聞こえてきそうですが、悲観する必要はありません。
高市政権の方針転換は、支援が「なくなる」のではなく、「形を変える」ということです。
一律に配るのではなく、本当に支援を必要としている人へ、より手厚く届けるための改革なのです。
新しい「給付付き税額控除」は、あなたの世帯年収によっては、これまでの給付金よりも大きな支援となる可能性があります。変化の時代に最も大切なのは、正確な情報をキャッチし、自分に関わる制度を理解することです。
一律給付の時代は終わりを告げ、今後は自身の所得や世帯状況に応じた支援策を正しく理解し、活用していくことが、家計を守る上でますます重要になるでしょう。
変化の時代に最も大切なのは、正確な情報をキャッチし、自分に関わる制度を理解することです。この記事で解説したポイントを押さえ、今のうちから準備を進めておきましょう。



そして高市政権を応援して、働いて、働いて、働いてもらいましょう!