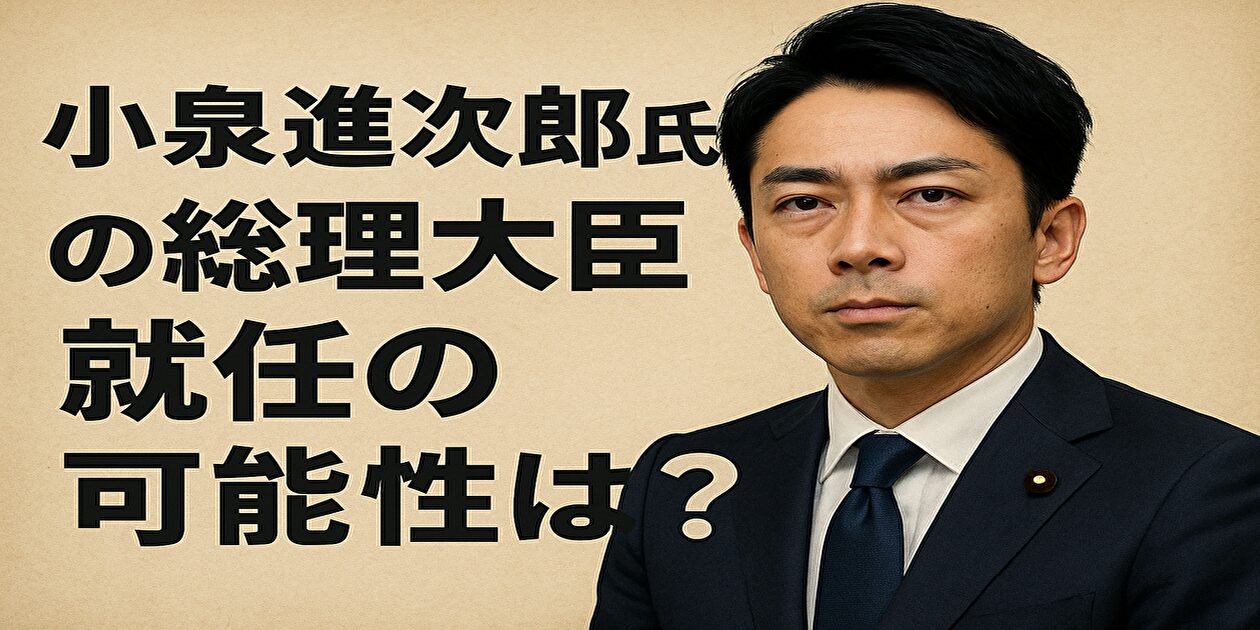石破茂首相の突然の辞任表明により、永田町は一夜にして総裁選モードに突入しました。
そんな中、「ポスト石破」の最有力候補として真っ先に名前が挙がったのが小泉進次郎農相です。
石破首相を辞任に追い込んだキーマンとして、菅義偉元首相とともに説得工作を行った小泉氏・・・その政治的手腕が評価され、世論調査では高市早苗氏と並んでトップの支持を獲得しています。
しかし、総理への道のりには乗り越えるべき「3つの大きな壁」が立ちはだかっています。
小泉進次郎、総理大臣の可能性「ポスト石破」の最有力候補へ
石破首相辞任劇のキーマンとしての役割
菅・小泉ラインによる「辞任勧告」の舞台裏
石破首相の突然の辞任表明。その裏には、菅義偉元首相と小泉進次郎氏による決死の説得がありました。
2025年9月6日の夜、小泉氏は2時間以上も石破首相と直接対話し、退陣を促したのです。当時、総裁選の前倒しを求める声に反発した石破首相が、解散総選挙という「伝家の宝刀」を抜くのではないかという緊張感が永田町を支配していました。もし解散に踏み切れば、自民党は分裂し、政治はさらなる大混乱に陥る。この最悪のシナリオを回避するため、菅・小泉ラインが「党を割らないでほしい」という大義名分を掲げ、石破首相に「苦渋の決断」を迫ったのです。
この動きが、膠着した政局を動かす決定的なターニングポイントとなりました。
 杉山 制空
杉山 制空反石破、総裁選前倒し議員の「救世主」を演じた小泉進次郎氏の戦略は見事ですね。このまま流れを掴めるか?『小泉劇場2025』の始まりです!
自民党分裂回避という大義名分
小泉氏が石破首相を説得した最大の理由は「党の分裂を避ける」というものでした。
総裁選の前倒しを巡って党内の意見は真っ二つに割れており、もし石破首相が解散総選挙に踏み切れば、それは党に対する「重大な背信行為」と見なされ、党が修復不可能なダメージを負うことは確実でした。実際に、石破氏に近い田村憲久元厚労相ですら「解散すれば除名ものだ」と公言するほど、党内の反発は強かったのです。
なぜ?小泉進次郎が本命視されるのか
若さと知名度による国民的人気
小泉進次郎氏が「ポスト石破」の本命と目される最大の理由は、その圧倒的な国民的人気と知名度にあります。
世論調査では常に「次の総理にふさわしい人物」として上位に名を連ね、特に若者や無党派層からの支持は絶大です。彼の若々しいイメージは、停滞する政治に「変革」や「世代交代」を期待させます。また、メディアでの発信力も他の政治家を圧倒しており、難しい政策課題を分かりやすい言葉で語るスタイルは、多くの国民にとって魅力的です。少数与党という厳しい状況下で次の選挙を戦う自民党にとって、彼の「選挙の顔」としての価値は計り知れず、党を勝利に導けるリーダーとして期待する声が党内に広がるのは自然な流れと言えるでしょう。
党内主流派からの支持取り付け
国民的人気だけでは、自民党総裁の座は掴めません。重要になるのが、党内、特に主流派や実力者からの支持です。
その点、小泉氏は着実に足場を固めています。石破首相への辞任勧告を菅義偉元首相と連携して行ったことは、菅氏との強力なパイプを内外に示しました。さらに、麻生太郎副総裁とも良好な関係を築いているとされ、党内の二大実力者のお墨付きを得つつある状況です。
彼が特定の派閥に属していないことは弱点ともいわれますが、逆に言えば、派閥間の対立から一歩引いた立場で、各方面と柔軟に連携できる強みにもなります。
この巧みな立ち回りによって、彼は「国民的人気」と「党内基盤」という、総理になるための二つの重要な要素を手に入れつつあるのです。
【小泉進次郎、総理大臣の可能性】強みと戦略
政策面での強みとアジェンダ
規制改革とデジタル化の推進
小泉進次郎氏が掲げる政策の柱は、徹底した「規制改革」と「デジタル化」の推進です。
彼は、日本の成長を妨げている岩盤規制を打破し、デジタル技術を活用することで、社会全体の生産性を向上させることを目指しています。
こうした未来志向の政策は、旧来の利益配分型の政治からの脱却を象徴しており、新しい時代を切り拓くリーダーとしての彼のイメージを強く印象付けています。
世代交代を象徴する未来志向のアジェンダ
小泉氏の政策は、常に「次の世代」を見据えているのが特徴です。
環境問題への取り組みや、社会保障制度改革はその代表例と言えるでしょう。彼は、目先の利益や票集めにとらわれず、将来世代に負担を先送りしない「持続可能な社会」の実現を訴えます。
特に、社会保険料負担の見直しに重点を置いている点は、現役世代の可処分所得を増やし、経済を活性化させたいという明確な意図の表れです。こうしたアジェンダは、年功序列や既得権益が根強い日本の政治風土の中で、「世代交代」を強くアピールする力を持っています。彼の政策は、これまでの自民党政治とは一線を画すものとして、特に若い世代からの共感と支持を集める大きな要因となっているのです。
小泉進次郎による政局運営の巧みさと連携シナリオ
日本維新の会との連携可能性
現在の自民党は衆参両院で少数与党であり、単独では法案を通すこともままなりません。そのため、次期総理には他党と連携し、安定した政権運営を行う能力が不可欠です。
この点で、小泉進次郎氏は大きな強みを持っています。彼は以前から日本維新の会との連携に前向きな姿勢を示しており、代表の吉村洋文氏とは「密月状態」ともいわれるほど良好な関係を築いています。両者は「規制改革」や「身を切る改革」といった政策面での親和性が高く、連立政権の樹立も十分に考えられます。もし「自民・公明・維新」という新たな連立の枠組みを構築できれば、安定した多数派を形成することが可能となり、政権運営は格段に安定します。この野党とのパイプの太さは、他の候補者にはない彼の大きなアドバンテージです。
少数与党を乗り切るための多党連携シナリオ
小泉氏の描く政権構想は、維新との連携だけにとどまりません。
彼の柔軟な政治姿勢は、他の野党との協力関係、いわゆる「パーシャル連合(部分連合)」を築く上でも有利に働きます。
総裁選では、この「政局運営能力」や「野党との交渉力」が大きな争点となるため、小泉氏の持つ連携シナリオは高く評価されるでしょう。
小泉進次郎が乗り越えるべき3つの壁:総理就任への課題
壁その① 政策の具体性と実現性への懸念
「ポエム」と揶揄される発言への懸念
小泉進次郎氏の課題として最も頻繁に指摘されるのが、その発言内容です。
キャッチーで分かりやすいフレーズを多用する一方、具体的な政策の中身や実現に向けた道筋が不明確であるとして、「中身がない」「ポエムのようだ」と揶揄されることが少なくありません。
例えば、環境大臣時代に「セクシーに取り組む」と発言したことは、彼のイメージを象徴する出来事として記憶されています。 総理大臣という国の最高責任者には、国民の心に響く言葉だけでなく、複雑な課題を解決するための具体的で緻密な政策が求められます。 今後、総裁選の討論会などで、財政、社会保障、外交・安全保障といった重要課題について、どれだけ具体的で説得力のあるビジョンを示せるかが、彼の評価を左右する重要な試金石となるでしょう。



去年の総裁選での一場面ですが…衝撃的でした。
去年の総裁選で「カナダのトルドー首相が就任した年は43歳、私は今43歳。私が総理になったら43歳就任というトップ同士新たな外交を切り開く」と答えた小泉進次郎。北朝鮮の拉致問題についても「同世代同士のトップですから」と意味不明な珍回答。この男に総理大臣は100年早い pic.twitter.com/tP7uxS8iFS
— あーぁ (@sxzBST) September 8, 2025
財政再建路線の限界と反発
小泉氏は、これまでの自民党主流派の路線を引き継ぎ、財政規律を重視する「財政再建路線」の立場を取っています。 しかし、長引くデフレや経済の停滞に苦しむ国民の間では、政府がもっと積極的に財政出動を行い、経済を刺激すべきだという声が強まっています。
特に、ライバルと目される高市早苗氏は「積極財政」を掲げ、消費税減税にも前向きな姿勢を見せています。 この経済政策の対立は、総裁選の大きな争点となります。 小泉氏が財政再建にこだわり続ければ、「国民の苦しみに寄り添っていない」という批判を浴びかねません。 物価高に直面する国民の支持を得るために、これまでの路線を維持しつつも、効果的な経済対策を打ち出せるかどうかが問われています。



ただし「財政再建路線」は、麻生、菅、岸田、森山などの長老たちの支持を得ることが可能であり、そして何より財務省の後ろ盾が就くことになるので、総裁選は有利に戦えることになるでしょう。
壁その② 経験不足と党内基盤の脆弱さ
大臣経験は豊富か?リーダーとしての実績
小泉氏は環境大臣や農林水産大臣などを歴任していますが、総理大臣に求められる外交・安全保障や、財務といった中枢分野での経験は十分とは言えません。
特に、複雑化する国際情勢の中で、各国の首脳と渡り合うための経験や実績は不可欠です。
また、党内でのリーダーシップについても未知数な部分があります。 これまで彼は、特定の派閥を率いて集団を動かすというよりは、個人の発信力で影響力を発揮してきました。 しかし、総理総裁となれば、考え方の違う議員たちをまとめ上げ、党を一致団結させる強力なリーダーシップが求められます。 これまでの実績だけでは、国政のトップを任せるには不安が残るという見方は、党内に根強く存在します。
自身の派閥を持たないことのデメリット
自民党の総裁選は、今なお派閥の力学が大きく影響します。
その中で、小泉氏が自身の派閥を持っていないことは、大きな弱点となり得ます。
派閥は、総裁選における票の取りまとめだけでなく、政権運営を安定させるための基盤ともなります。派閥に属さないことは、クリーンなイメージにつながる一方で、いざという時に頼れる足場がないことを意味します。現在は菅氏や麻生氏といった実力者の支援が期待されていますが、彼らの思惑次第で状況は一変する可能性もあります。総裁選を勝ち抜き、さらに安定した政権を運営するためには、党内の幅広い議員から支持を取り付け、派閥に代わる強固な支持基盤を自ら構築していく必要があります。
壁その③ 保守層からの支持獲得とライバルの存在
ライバル高市早苗氏との対比
小泉氏が総理の座を目指す上で、最大の壁となるのが高市早苗氏の存在です。
高市氏は、安倍晋三元首相の政治信条を受け継ぐ「保守派のアイコン」として、党内の保守層から絶大な支持を得ています。経済政策では積極財政を掲げ、外交・安全保障では毅然とした態度を貫く高市氏の姿勢は、改革や多様性を重視する小泉氏とはまさに対照的です。このため、総裁選は「改革派の小泉 vs 保守派の高市」という、党の路線をかけた戦いになる可能性が高いのです。



前回の参院選で、参政党などに流れた保守層の多くは、現在も自民党員のままです。党員が参加可能となる、フルスペックの戦いになると高市氏が有利と言えるでしょう。
安倍元首相路線からの転換に対する警戒感
自民党内には、安倍元首相が築いた政治路線を堅持すべきだという考え方が根強く残っています。
小泉氏の掲げる「改革」や「世代交代」は、この安倍路線からの転換を意味すると受け止められ、党内の保守派から強い警戒感を招いています。彼らは、小泉氏が総理になれば、安倍氏が進めてきた安全保障政策や経済政策「アベノミクス」が骨抜きにされてしまうのではないかと懸念しているのです。この警戒感を払拭しなければ、党内をまとめ上げることは困難です。小泉氏には、伝統を重んじる保守派の心情にも配慮しつつ、自身の改革ビジョンを丁寧に説明し、理解を求めていくという、難しいバランス感覚が求められることになります。
小泉進次郎とライバル候補との徹底比較!総裁選の行方
高市早苗氏との一騎打ちシナリオ
経済政策の対立軸(財政再建 vs 積極財政)
もし総裁選が小泉進次郎氏と高市早苗氏の一騎打ちとなった場合、最大の争点は経済政策になるでしょう。
具体的には、高市氏は消費税減税にも前向きな姿勢を示しており、物価高に苦しむ国民へのアピールを強めています。この対立軸は、単なる政策の違いにとどまらず、「将来世代への責任」を重視するのか、「現在の経済危機への対処」を優先するのかという、国の進むべき方向性を問う根源的な選択となります。どちらの主張が党員や国民の支持を集めるのか、目が離せません。
総裁選の鍵を握るその他の候補者
茂木敏充氏、林芳正氏らの役割
総裁選の行方は、小泉・高市両氏だけで決まるわけではありません。
茂木敏充元幹事長や林芳正官房長官といった実力者の動向も、レース全体に大きな影響を与えます。



因みにお二人とも、東京大学卒業からハーバード大学のケネディ・スクール出身というエリート中のエリートです。
茂木氏は旧茂木派を率いた経験があり、今も一定の議員グループに影響力を持っています。 林氏は石破政権を官房長官として支え、政策通として知られています。 彼らが自身で出馬するのか、それとも小泉氏か高市氏のどちらかを支持するのかによって、票の流れは大きく変わります。 特に、決選投票にもつれ込んだ場合、彼らがどちらの候補を支持するかは、勝敗を左右する決定的な要因となり得ます。 彼らの動きは、総裁選のキャスティングボートを握っていると言っても過言ではありません。
総裁選の鍵を握る「第三の候補」の存在
小泉氏と高市氏という二人の対立が鮮明になる中で、「第三の候補」が漁夫の利を得る可能性もゼロではありません。
例えば、若手や中堅から待望論が強い小林鷹之元経済安保担当相のような人物です。
もし小泉氏と高市氏が支持を二分し、党内の対立が激化した場合、その対立を収めることができる穏健な候補者を求める声が高まる可能性があります。
そうした状況になれば、両者とは異なる政策やビジョンを掲げる第三の候補が、ダークホースとして急浮上することも考えられます。 特に、総裁選が複数の候補者による乱戦となった場合、議員票が分散し、誰も予想しなかった結果が生まれるかもしれません。 総裁選は、最後まで目が離せない展開となりそうです。
【総括】小泉進次郎は総理になれる?可能性と3つの壁
「小泉進次郎は次の総理になれるのか?」この問いの答えを探ることは、単に一人の政治家のキャリアを追うこと以上の意味を持っています。
それは、私たちが暮らす日本が、これからどのような国を目指していくのかを考えることに他なりません。
小泉氏が象徴するのは「変化」への期待です。
停滞した政治を打破し、デジタル化や規制改革で新しい時代を切り拓いてほしい。そう願う国民の声が、彼を「本命」へと押し上げています。
今回の総裁選は、どちらが正しいという単純な話ではありません。私たち国民一人ひとりが、それぞれの候補者が示すビジョンの光と影を冷静に見極め、日本の未来にとってどの選択が最善なのかを真剣に考える絶好の機会なのです。
永田町の動向を他人事と捉えず、自分の問題として見つめてみませんか・・・。