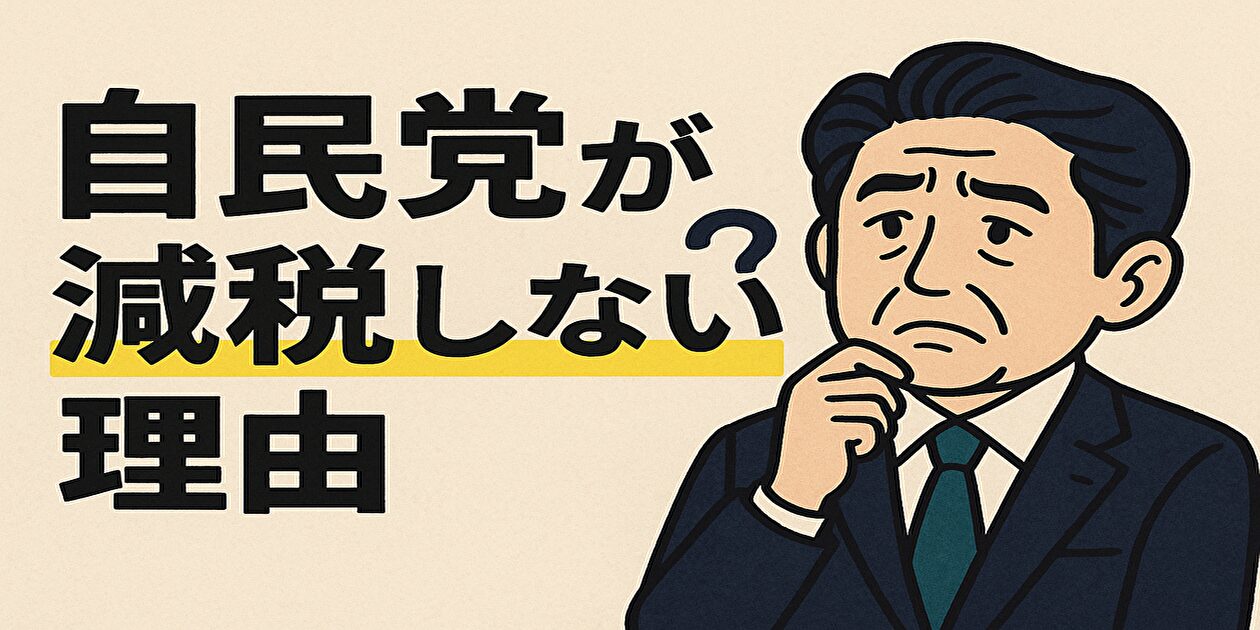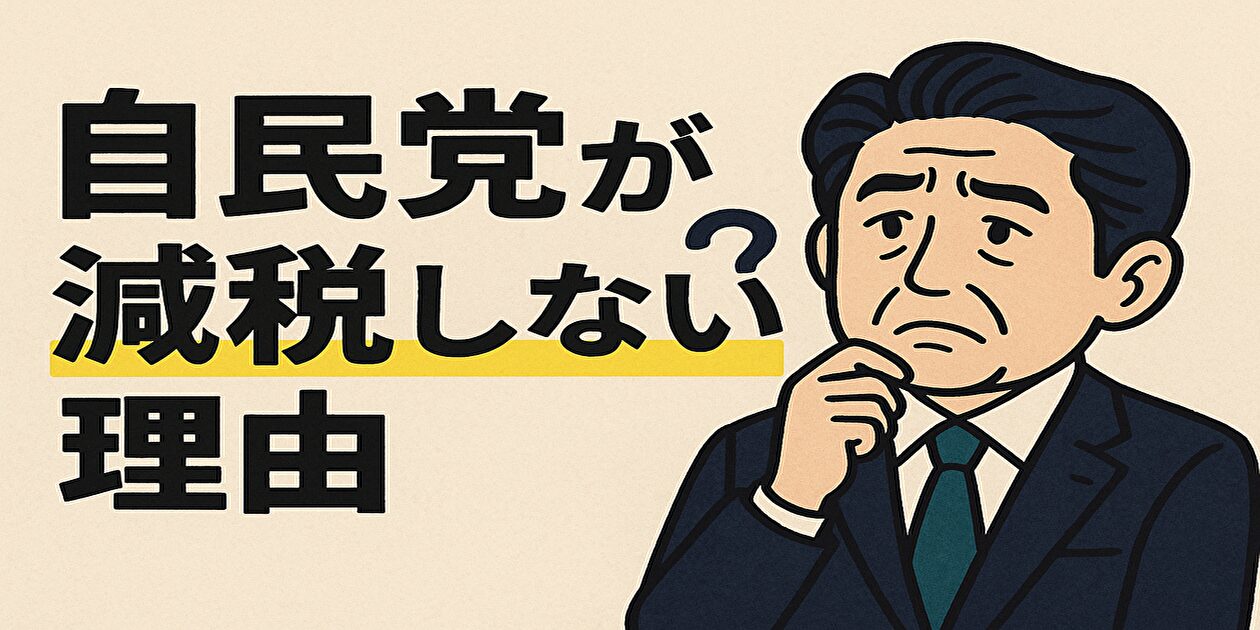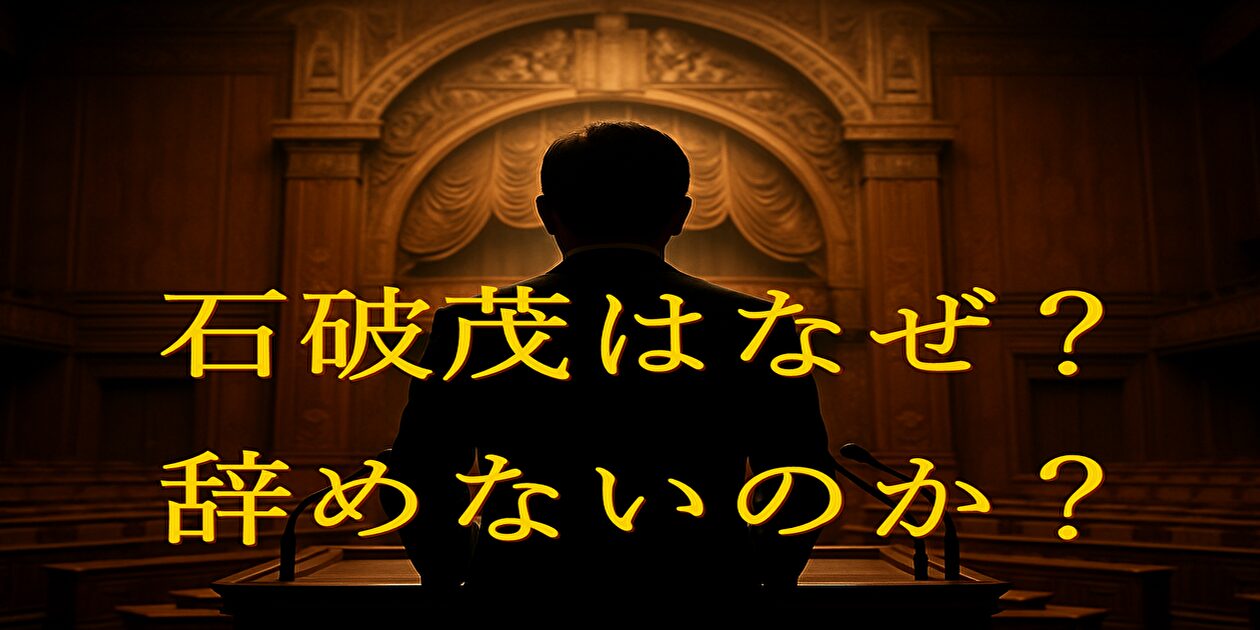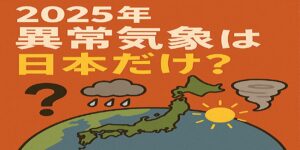衆院選、都議選、そして参院選と、歴史的な3連敗を喫した石破政権。
にもかかわらず、なぜ石破首相は辞任を表明しないのでしょうか。
ニュースを見てもスッキリせず、日本の政治がどこへ向かうのか不安になりますよね。
この記事では、なぜ石破首相が続投に固執するのか、その裏にある「3つの構造的理由」を誰にでも分かるように徹底解説します。
この記事を読めば、今の政治状況のカラクリと、今後の日本経済への影響まですべて理解できます。
なぜ石破首相は辞めないのか?3つの構造的理由
①常識を超えた「総理への執着」という個人的資質
多くの人が「なぜ?」と感じる最大の要因は、石破首相自身の特異なキャラクターにあります。
通常、国政選挙で大敗すれば、首相は責任を取って辞任するのが政治の常識でした。しかし、石破首相は衆議院選挙、東京都議会議員選挙、そして今回の参議院選挙と3回連続で大敗しても、その座に留まり続けています。
これは、政策の実現や国民からの支持よりも、「総理大臣であり続けること」自体が目的化しているためと考えられます。
過去の首相が国民の声や党内の空気を読んで身を引いたのとは対照的に、石破首相は「鋼のメンタル」とも揶揄されるほどの強い執着心で、あらゆる批判を意に介しません。
この「普通ではない」個人の資質が、前例のない長期続投を可能にする第一の理由なのです。
 杉山 制空
杉山 制空今まさに、安倍元総理の「石破さんだけは総理にしてはいけない」の本当の意味に痛感させられています。
②財務省が描く「石破長期政権」というシナリオ
石破首相個人の意思だけでは、これほどの逆風の中で政権を維持することは不可能です。
その背後には、官僚機構、特に「財務省」の強力なサポートがあります。
財務省にとって、石破政権は「最も都合の良い政権」です。なぜなら、石破首相は財務省が推し進めたい「増税」や「財政規律」路線に非常に協力的だからです。
国民から人気の高い「減税」や「積極的な財政出動」を掲げる政治家よりも、自分たちの意向を忠実に実行してくれる石破首相を支える方が、省益にかなうのです。
石破首相、森山幹事長、木原選挙対策委員長というラインは、財務省から見ればまさに「ゴールデントライアングル」です。彼らは石破政権をできるだけ長く維持するためのシナリオを描き、あらゆる手を使って支えているのです。



特に、元財務官僚の木原誠二選挙対策委員長の存在が大きいでしょうね。彼こそ、岸田政権に続き、石破政権でも「影の総理」と言われる存在ですから・・・木原さんを通じて、財務省のバックアップがあるからこそ、石破茂は余裕の顔で「続投宣言」が出来ているのです。
③鉄壁の党内ガードと機能しない退陣要求
「党内の重鎮が反対すれば辞めさせられるのでは?」と思うかもしれませんが、現在の自民党ではその機能が麻痺しています。
また、仮に麻生副総裁などが主導して閣僚を引き上げ(辞任させ)ても、石破首相はすぐに後任を補充するでしょう。大臣のポストに就きたい議員は数多くいるため、この手も決定打になりにくいのが現実です。
このように、党内のチェック機能が働かない構造が、石破政権を延命させる3つ目の理由となっています。
国民の審判は「石破茂辞めろ。」だよ@shigeruishiba @jimin_koho https://t.co/i0aUUPey9i
— あぼーん (@jin_roh00) July 20, 2025
【石破はなぜ?辞めない?】 政権を支える「影のプレイヤー」たちの思惑
官邸を操る「財務省」の狙いとは?
前述の通り、石破政権最大の支持基盤は財務省です。
彼らの狙いはシンプルで、「財政規律を維持し、将来的な増税路線を確実なものにすること」です。
国民的人気が高い「減税」は、彼らにとって最も避けたいシナリオ。
選挙で減税派の議員がどれだけ増えようとも、政権トップが自分たちのコントロール下にあれば、その流れを止めることができます。
石破政権が続く限り、国会を開くタイミングを遅らせたり、議論を先延ばしにしたりすることで、減税政策の実現を骨抜きにできるのです。つまり、財務省は石破首相を「防波堤」として利用し、国民の声が政策に反映されるのを防いでいると言っても過言ではありません。この官僚主導の政治構造こそが、今の日本の政治が停滞している根本原因の一つです。
なぜ野党の一部も「石破延命」に加担するのか?
驚くべきことに、石破政権の延命には野党の一部も間接的に加担している側面があります。
もし与野党の財政規律派が手を組めば、事実上の「大連立」のような形で政権運営が安定し、石破首相はさらに延命することになります。
野党第一党が政権を本気で倒しにいかず、特定の政策で協力する姿勢を見せることは、結果的に石破首相を助けることにつながります。国民からは分かりにくい「永田町の論理」によって、本来は対立するはずの与野党が、水面下で利害を一致させているのです。
今後の政局はどう動く?3つのシナリオを徹底解説
シナリオ1:8月の臨時国会が最初の山場
今後の政局を占う上で、最初の重要なポイントは参院選後30日以内に開かれる臨時国会です。
これは法律で定められた必須の国会ですが、通常は議員の議席確定などを行う儀式的なものですぐに終わります。石破政権側は、この儀式を「関税交渉が大変だ」という「国難」を言い訳にして、さっさと終わらせたいと考えています。
しかし、野党側がこのタイミングで「内閣不信任案」を提出すれば、事態は一変します。
儀式的な国会が、一気に政局の天王山となるのです。ここで不信任案が出されるかどうかが、石破政権の寿命を左右する最初の分岐点と言えるでしょう。8月1日までの動きから目が離せません。
シナリオ2:「解散カード」を切る可能性とリスク
もし野党が内閣不信任案を提出し、追い詰められた場合、石破首相は「衆議院の解散・総選挙」という最後のカードを切る可能性があります。
これは、首相に残された最強の権限です。
しかし、今の低い支持率で解散総選挙に打って出れば、自民党がさらに議席を減らすのは確実で、まさに「自爆テロ」とも言える選択肢です。
そのため、石破首相が解散をちらつかせることで、党内の反発を抑え込もうとする可能性もあります。ぐちゃぐちゃになることを覚悟の上で解散に踏み切るのか、それとも単なる脅しで終わるのか。このチキンレースの行方が、今後の政局を大きく左右します。
シナリオ3:膠着状態が続き「政治の空白」が長期化
最も懸念されるのが、決定的な動きがないまま時間だけが過ぎていく「政治の空白」が続くシナリオです。
石破政権は延命し、野党も決め手を欠き、党内の反発も抑え込まれる。この膠着状態が続けば、本来議論されるべき経済対策や減税、外交問題などがすべて先送りされてしまいます。
「石破首相が辞めない」ことによる国民生活への深刻な影響
期待される「減税」が実現しないカラクリ
今回の選挙では、多くの国民が「減税」を期待して投票したはずです。
しかし、石破首相が辞めない限り、その実現は極めて困難です。
なぜなら、減税を行うには、法案を国会で審議し、可決する必要があるからです。しかし、政権側が国会を開かなければ、議論すら始まりません。
石破政権と、それを支える財務省は減税に消極的ですから、意図的に国会を開くのを遅らせる可能性があります。「選挙で減税を掲げる候補者が勝ったのに、なぜか減税が実現しない」という、民主主義の根幹を揺るがす事態が起こりかねないのです。これは、政治家が国民との約束を無視しているのと同じであり、私たちの生活に直接的なダメージを与える深刻な問題です。
忍び寄る「トランプ関税」と景気悪化のリスク
国内の政治が停滞している間にも、海外の経済情勢は待ってくれません。
特に懸念されるのが、アメリカで再燃する可能性のある「トランプ関税」です。
もし強力な保護主義政策が取られれば、日本の輸出産業は大きな打撃を受け、景気は一気に悪化する恐れがあります。このような経済危機に対応するためには、迅速な経済対策や補正予算の編成が不可欠です。
【Q&A】石破首相が辞めない問題に関するよくある質問
過去の首相はすぐ辞めたのに、なぜ石破首相だけ違うの?
A. 理由は大きく2つあります。1つは、石破首相自身の「総理の座」への強い執着心です。過去の首相の多くは、国民からの支持率低下や党内の反発を受けて「これ以上は政権を維持できない」と判断し、自ら辞任を選びました。しかし、石破首相にはその常識が通用しないと見られています。2つ目は、財務省という強力な後ろ盾の存在です。財務省にとって都合の良い石破政権を維持するため、官僚組織が全力で支えている構造があります。この「個人の資質」と「組織のバックアップ」が組み合わさっている点が、過去の首相とは決定的に異なります。
麻生副総裁など、党内の反発で辞めさせられないの?
A. 理論上は可能ですが、現実的には非常に困難です。首相を辞めさせるには、党のルールに則った手続きが必要ですが、その手続きを動かす中心人物(幹事長など)が石破首相を支えているため、反石破派は手も足も出ない状況です。また、閣僚が一斉に辞任する「閣僚ストライキ」のような手段も考えられますが、大臣のポストは魅力的なため、辞任者が出てもすぐに後任が見つかってしまい、決定打になりにくいのが実情です。党内の力学が複雑に絡み合い、一枚岩で「石破おろし」に動けないのが現状と言えます。
私たち国民にできることはありますか?
A. 無力感を感じるかもしれませんが、できることはあります。まず、この政治状況に関心を持ち続けることが非常に重要です。メディアの報道を鵜呑みにせず、なぜこのような事態になっているのか、その構造を理解しようと努めることが第一歩です。そして、自分の選挙区の国会議員に意見を伝えること(電話、メール、SNSなど)も有効な手段です。多くの有権者が声を上げれば、政治家もそれを無視できなくなります。次の選挙では、こうした政治の停滞を招いた責任が誰にあるのかを厳しく判断し、投票行動で意思を示すことが、最終的に政治を変える最も強力な力になります。
【総括】石破総理はなぜ辞めない?
石破首相が辞めない問題の本質は、「日本の民主主義が正常に機能しているか」という極めて重大な問いを私たちに突きつけています。
選挙という民意を問う最大のイベントを経てもなお、その結果が為政者に届かない。
この「民意の無視」を許しているのは、石破首相個人の資質以上に、彼を支えることで利益を得る財務省や、与野党の一部政治家たちの存在です。彼らは国民生活よりも、自らの組織益や政治的立場を優先しています。
この膠着状態を打破する鍵は、①世論の圧力、②経済の悪化、③政治的イベントの3つです。
世論の「いい加減にしろ」という声が臨界点を超え、支持率が危険水域に達すること。そして、減税が進まないことによる景気悪化が顕著になり、国民の不満が爆発すること。最後に、臨時国会での不信任案提出や、予期せぬスキャンダルといった政治的イベントが、この歪んだ構造に亀裂を入れる可能性があります。
石破政権が続くか否かは、単なる一政権の寿命問題ではありません。国民が主権者として尊重される国であり続けられるかどうかの、試金石なのです。