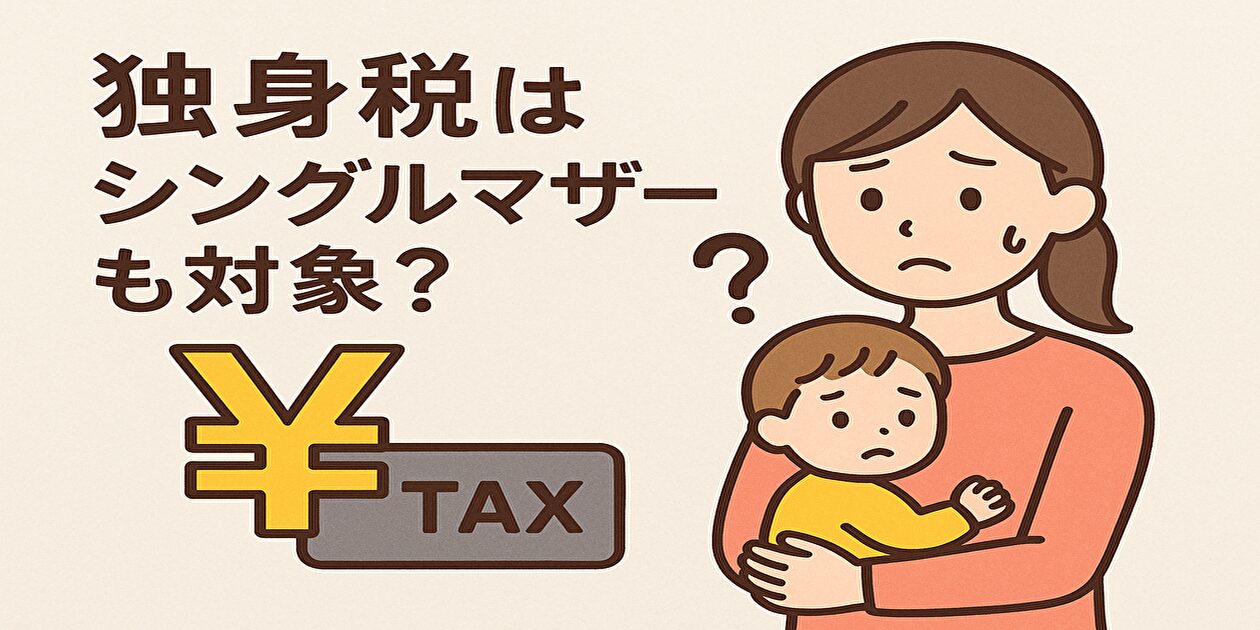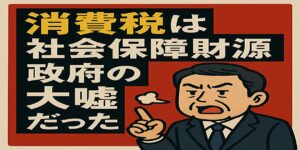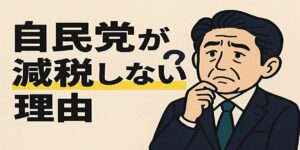「独身税はデマ」という情報もあれば、「シングルマザーも対象」という話もあり、何が本当か分からなくなっていませんか?
2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」、通称「独身税」は、私たちの生活に直接関わる重要なテーマです。
この記事では、制度の対象者や開始時期といった基本情報から、特にシングルマザーの方が気になる負担額、そして家計を守るために知っておくべき税金の優遇措置まで、丁寧に解説していきます。
【独身税】シングルマザーも対象?2026年からの新制度を徹底解説
独身税の正体とは?デマと真実を徹底解説
正式名称は「子ども・子育て支援金制度」
巷で「独身税」と呼ばれているものの正体は、2026年4月から導入が予定されている「子ども・子育て支援金制度」のことになります。
これは、少子化対策を社会全体で支えるために創設される新しい仕組みであり、「税金」ではなく公的医療保険(健康保険)の保険料に上乗せして徴収される「支援金」になります。
独身者や子どものいない世帯にも負担が生じることから「独身税」という俗称が広まりましたが、特定の個人の結婚の有無に対して課税するものではなく、あくまで社会全体で子育てを支えるという理念に基づいています。
「独身税はデマ」という情報のウソ・ホント
「独身税はデマだ」という言説もインターネット上では見られますが、これは半分正しく、半分誤解を招く表現です。
まず、「独身税」という名称の税金が新設されるわけではない、という点では「デマ」と言えます。
政府が公式に発表している名称はあくまで「子ども・子育て支援金制度」です。
しかし、「独身者を含め、子育て世帯以外にも新たな金銭的負担を求める制度が2026年から始まる」という事実自体はデマではありません。
この制度は、独身者、既婚者、子どもの有無にかかわらず、公的医療保険に加入しているほぼすべての国民が負担の対象となるため、結果的に独身者も負担することになります。そのため、「独身税はデマだから安心」と考えるのではなく、新しい社会保険料の負担が始まると正しく理解しておくことが重要です。
シングルマザーも対象?独身税はいつから誰が払う?

【独身税】2026年4月から導入開始
「子ども・子育て支援金制度」の施行は、2026年(令和8年)4月からと予定されています。
政府は制度の導入や周知に準備期間が必要であるとして、このスケジュールを設定しました。この時期から、私たちの毎月の給与や支払いから、医療保険料と合わせて支援金が徴収されることになります。徴収額は段階的に引き上げられる計画で、例えば年収400万円の会社員の場合、2028年度には年間7,800円(月額650円)程度の負担になると試算されています。制度開始までにはまだ時間がありますが、家計管理の上で、この新しい負担が始まることを念頭に置いておく必要があるでしょう。
【独身税】 対象者は医療保険に加入する全国民
この支援金の負担対象者は、「独身者」に限定されているわけではありません。
正しくは、公的医療保険に加入しているすべての人が対象となります。
具体的には、会社員や公務員が加入する「被用者保険」、自営業者などが加入する「国民健康保険」、そして75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」のすべての加入者が含まれます。つまり、未婚・既婚、子どもの有無、年齢や性別を問わず、日本で医療保険に加入しているほぼ全国民が、それぞれの収入に応じた額を負担する仕組みです。この「社会全体で支える」というコンセプトが、この制度の大きな特徴です。したがって、シングルマザー(母子家庭)もこの制度の対象者に含まれることになります。
【独身税】シングルマザー(母子家庭)も対象?

結論:独身税はシングルマザーも負担の対象
最も気になる点だと思いますが、結論から言いますと、シングルマザー(母子家庭)も「子ども・子育て支援金」の負担対象となります。
前述の通り、この制度は医療保険加入者全員を対象としているため、ひとり親世帯であっても例外ではありません。毎月の健康保険料に上乗せされる形で、数百円程度の負担が発生することが見込まれています。
子育てを一人で担い、経済的にも厳しい状況にあることが多いシングルマザーにとって、新たな負担が増えることは大きな不安要素に違いありません。
しかし、この制度は負担を強いるだけでなく、子育て世帯を支援するという重要な側面も持っています。次の項目で、シングルマザーが受けられる支援について詳しく見ていきましょう。
独身税は負担だけでなく支援も受けられる
シングルマザーは支援金の「負担者」であると同時に、制度の恩恵を受ける「受益者」でもあります。
この制度によって集められた財源は、まさに子育て中の世帯を支えるために使われるからです。
具体的には、児童手当の拡充(所得制限の撤廃や支給期間の高校生年代までの延長など)、保育所の利用支援、育児休業給付の増額といった、子育て世帯の経済的負担を直接的に軽減する施策に充当されます。つまり、シングルマザー世帯は毎月数百円の負担は増えるものの、それ以上に拡充された児童手当などの給付を受けられる可能性が高いのです。この「負担と給付」の両面を理解することが、制度を正しく評価する上で非常に重要になります。負担が増えるという事実だけに目を向けるのではなく、家計全体としてプラスになる可能性も考慮する必要があります。
シングルマザーが受けられる税金の免除・控除
ひとり親控除で所得税・住民税を軽減
子ども・子育て支援金の負担とは別に、シングルマザーが利用できる重要な税制優遇措置として「ひとり親控除」があります。
これは、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同一にする子(合計所得金額48万円以下)がいて、本人の合計所得金額が500万円以下のひとり親が対象となる所得控除です。この控除を適用することで、所得税で35万円、住民税で30万円が課税対象の所得から差し引かれます。これにより、課税所得が圧縮され、結果的に所得税や住民税の負担が軽くなります。年末調整の際に勤務先に申告するか、確定申告を行うことで適用を受けられますので、忘れずに手続きを行いましょう。
住民税が非課税になる年収の目安
さらに、シングルマザー(ひとり親)の場合、所得が一定基準以下であれば住民税そのものが非課税になる優遇措置があります。
具体的には、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税は課税されません。これを給与収入に換算すると、年収約204万円未満が目安となります。この基準は、給与所得控除などを考慮して算出されたものです。もし自身の年収がこの基準に近い場合は、非課税の対象となる可能性があります。住民税が非課税になれば、国民健康保険料の軽減など、他の公的サービスの負担軽減にも繋がることがあります。お住まいの自治体の窓口で詳細を確認し、対象となる場合は適切に手続きを行うことが家計の助けになります。
【独身税】よくある質問(Q&A)
Q1. 独身税はシングルマザーも対象ですか?
A1. はい、対象です。「独身税」と俗に呼ばれる「子ども・子育て支援金制度」は、公的医療保険の加入者全員が対象のため、シングルマザー(母子家庭)も負担者となります。ただし、同時に児童手当の拡充など、制度による支援の受け手にもなります。
Q2. 2026年に独身税は本当に導入されますか?
A2. はい。「子ども・子育て支援金制度」として、2026年4月から施行される予定です。「独身税」という名称の税金ではありませんが、実質的に国民の新たな負担となる制度が開始されることは事実です。
Q3. シングルマザーが受けられる税金の控除はありますか?
A3. はい、「ひとり親控除」があります。合計所得金額が500万円以下などの要件を満たす場合、所得税で35万円、住民税で30万円の所得控除が受けられます。また、前年の合計所得が135万円以下(年収約204万円未満が目安)の場合、住民税が非課税になる制度もあります。
【総括】独身税はシングルマザーも対象?
結論として、シングルマザーも2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金」(通称:独身税)の負担対象となります。
しかし、これは決してシングルマザーを狙い撃ちにした制度ではありません。少子化という社会全体の課題に対し、医療保険加入者全員で子育て世帯を支えようという趣旨のものです。シングルマザー世帯は、月数百円の負担は生じるものの、その財源によって拡充される児童手当や各種子育て支援の直接的な受益者となります。
負担の側面だけを見て不安になるのではなく、受けられる給付や、既存の「ひとり親控除」といった税金の優遇制度をしっかりと活用することで、家計への影響を抑え、むしろ恩恵を受けられる可能性があります。
制度の正しい理解が、未来への安心に繋がるのです・・・。