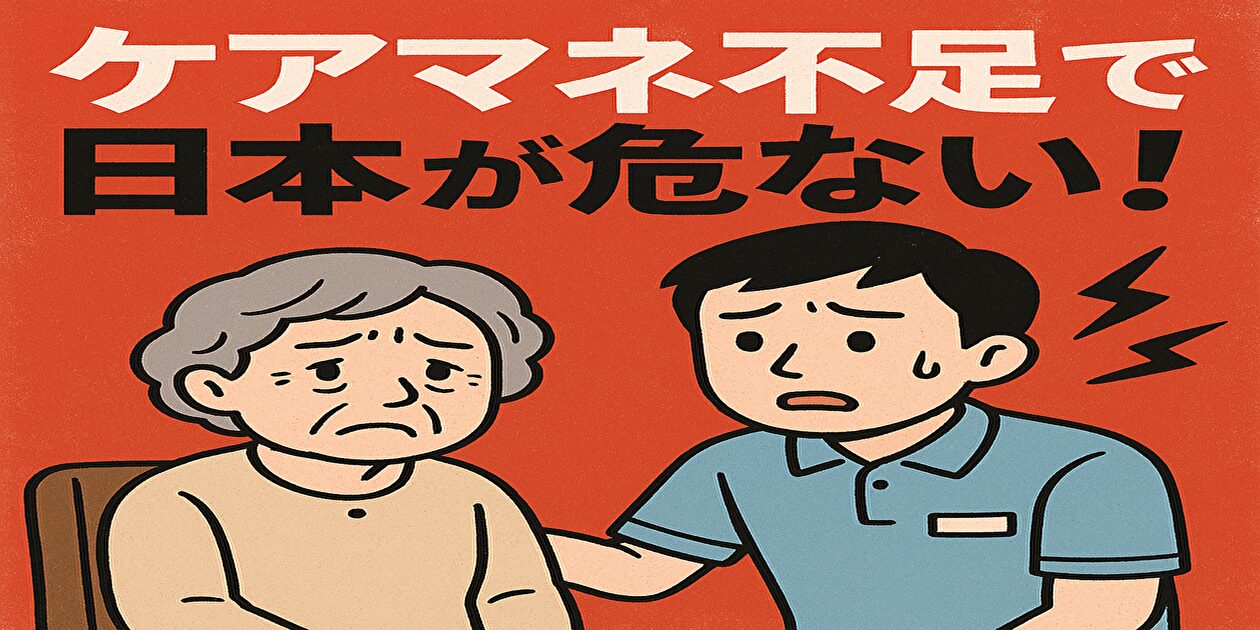「ケアマネが見つからない」という声が全国で急増しています。
実際、ケアマネの従事者数は2018年の約19万人をピークに減少に転じ、2022年には約18.3万人まで落ち込みました。
一方で超高齢社会の進展により、2040年までに約8.3万人の新規確保が必要という厚労省の衝撃的な推計が発表されています。
現在の有効求人倍率9.70倍は「求人10件に対し求職者1人」という異常事態を示し、地方では20倍を超える地域も存在します。
本記事では、なぜここまで深刻な人材不足に陥ったのか、その5つの根本原因を分析し、2027年制度改正で検討されている処遇改善策や業務効率化など、国の最新対策も紹介します。
ケアマネ不足の深刻な現状とは?データで見る危機的状況
2040年には8.3万人が不足?厚労省の衝撃的な推計
日本の介護現場が、静かに、しかし確実に迫りくる危機に直面しています。
その中心にあるのが、介護サービスの司令塔ともいえるケアマネジャーの深刻な不足です。
厚生労働省が2023年に公表したシミュレーションは、衝撃的な未来を予測しています。
それによると、現状のまま推移した場合、2025年度までに約2.7万人、そして2040年度には約8.3万人ものケアマネジャーが不足するというのです。
これは、団塊の世代が後期高齢者となり介護需要が爆発的に増加する一方で、担い手であるケアマネの数が追いつかないことを意味します。すでに、ケアマネの従事者数は2018年度をピークに減少に転じており、介護の最前線を支える基盤そのものが揺らいでいる状況です。この数字は単なる統計ではありません。一人ひとりの高齢者が、必要なケアプランを作成してもらえず、適切な介護サービスに繋がれない未来を示唆しているのです。
「ケアマネ難民」が現実味を帯びる地域も
「ケアマネにお願いしたいのに、どこに連絡しても断られる」。そんな悲鳴が、現実に多くの地域で上がり始めています。
これが「ケアマネ難民」問題です・・・。
特に、ケアマネのなり手が少ない中山間地域や離島では、居宅介護支援事業所そのものが存在しない自治体も出てきており、介護保険サービスを利用したくても、そのためのケアプランを作成してくれる人がいないという事態が起きています。
また、都市部であっても問題は深刻です。
これは、介護が必要な高齢者やその家族にとって、セーフティネットであるはずの介護保険制度が機能不全に陥っていることを意味し、在宅生活の継続を困難にさせる深刻な社会問題となっています。
ケアマネがどんどん減っていく【ケアマネ不足】5つの根本原因
ケアマネ不足【原因1】過酷な業務と責任の重さ
ケアマネジャーが現場を去る最大の理由の一つが、その過酷な業務内容と精神的な負担の大きさです。
ケアマネの仕事は、単にケアプランを作成するだけではありません。利用者や家族からの相談対応、サービス事業者との連絡調整、医療機関との連携、給付管理業務など、その業務は多岐にわたります。
特に、緊急時の対応や困難ケースの調整では、昼夜を問わず対応に追われることも少なくありません。書類作成業務も膨大で、本来の専門業務である相談・調整業務の時間を圧迫しています。
これだけの多忙さに加え、利用者の生活と命を預かるという重い責任が常にのしかかります。
この責任の重さと業務量の多さが見合っていないと感じ、心身ともに疲弊してしまい、燃え尽きてしまう(バーンアウト)ケアマネが後を絶たないのです。
「辞めてよかった」という声の裏には、こうした過酷な労働環境が隠されているのです。
ケアマネ不足【原因2】仕事量に見合わない低い給与水準
責任が重く専門性が高い業務であるにもかかわらず、ケアマネジャーの処遇は決して十分とは言えません。
多くの場合、介護職員に適用される「処遇改善加算」が居宅介護支援事業所のケアマネには対象外となっており、現場で汗を流す介護福祉士よりも給与が低いという逆転現象すら起きています。
令和6年度の介護報酬改定でもこの状況は大きく変わらず、多くのケアマネが失望感と無力感を抱いています。
専門資格を維持するための研修費用や時間も自己負担となるケースが多く、経済的な負担も少なくありません。
これだけのリスクと負担を背負いながら、それに見合った経済的評価が得られないのであれば、新たにケアマネを目指そうという人が減るのは当然と言えるでしょう。魅力的なキャリアパスを描けず、将来への不安から離職を選択する人が多いのが現状です。
ケアマネ不足【原因3】高すぎる資格取得・更新のハードル
ケアマネジャーになるための道のりは、決して平坦ではありません。
まず、受験資格を得るために、特定の国家資格に基づく業務、または相談援助業務において5年以上かつ900日以上の実務経験が必要となります。この時点で、多くの人がふるいにかけられます。さらに、難関の試験に合格した後も、5年ごとに高額な費用と長時間の拘束を伴う更新研修を受け続けなければなりません。この資格取得と更新の負担の大きさが、新たななり手を遠ざけ、現役ケアマネの意欲を削ぐ大きな要因となっています。
特に、子育てや介護と両立しながら研修時間を確保することは容易ではなく、資格を失効させてしまう「潜在ケアマネ」を多く生み出しています。
制度が、意欲ある人材を確保するどころか、むしろ参入障壁として機能してしまっているという皮肉な状況が生まれているのです。
ケアマネ不足【原因4】ケアマネの高齢化と若手不足
ケアマネジャーの世界は、深刻な高齢化に直面しています。
従事者の平均年齢は50歳を超え、60歳以上の割合も高いのが現状です。これは、今後10年から20年の間に、経験豊富なベテランケアマネが一斉に退職期を迎えることを意味します。彼らが長年培ってきた知識やノウハウが失われることは、地域包括ケアシステムにとって大きな損失です。
一方で、若手の参入は非常に少ない状況が続いています。
前述の通り、処遇の低さや業務の過酷さから、若者にとって魅力的な職業と映っていないのが実情でしょう。このまま世代交代が進まなければ、ケアマネの総数が激減するだけでなく、ICT活用など新しい時代の変化に対応できる人材が育たず、業界全体が停滞してしまう恐れがあります。
将来の介護を担う若手をいかに育成し、定着させていくかが、喫緊の課題となっています。
ケアマネ不足【原因5】一部利用者からのハラスメント「ケアマネ老害」問題
近年、ケアマネジャーを精神的に追い詰める要因として「ケアマネ老害」という言葉が聞かれるようになりました。
これは、一部の利用者やその家族による、理不尽な要求や暴言、過度な依存といったハラスメント行為を指す俗語です。例えば、「ケアプランに関係ないことまで頼む」「自分の思い通りにならないと大声で怒鳴る」「24時間いつでも電話してくる」といったケースです。もちろん、多くの利用者は良識ある方々ですが、一部の心ない言動がケアマネの心を深く傷つけ、離職の引き金となることがあります。ケアマネはサービス提供者であり、召使いではありません。しかし、その境界線が曖昧になりがちな中で、一人で利用者の過大な要求を抱え込み、精神的に孤立してしまうのです。こうしたハラスメントからケアマネを守るための組織的なサポート体制の欠如も、人材定着を妨げる深刻な問題と言えるでしょう。
【介護サービスが受けられない⁉️カスハラとシャドウワークでケアマネ人材不足】
— まるた こう一郎/自民党衆議院神奈川13区支部長(瀬谷区、大和市、綾瀬市)/丸田康一郎 (@koichiro_maruta) June 3, 2025
高齢化の中で高まる介護ニーズ。
介護サービス全体の司令塔となるケアマネージャーのなり手が減っています。
背景にあるのは、上がらない賃金と、重すぎる業務負担です。… pic.twitter.com/Gg5PhaF7vQ
このままではヤバイ!ケアマネ不足がもたらす未来
必要な介護サービスが受けられない「介護崩壊」
ケアマネジャー不足がこのまま進行すると、私たちの社会は「介護崩壊」とも呼べる事態に直面する可能性があります。
ケアマネは、利用者に必要なサービスを結びつける「架け橋」です。その架け橋がなくなれば、デイサービスに行きたくても、ホームヘルパーに来てほしくても、そのための手続きができなくなります。
結果として、介護保険という制度がありながら、それを利用できない高齢者が街にあふれる「介護難民」が急増するでしょう。
在宅での生活が限界に達しても、施設入所のための手続きも進まず、行き場を失う人々が出てくるかもしれません。これは、単に高齢者個人の問題ではなく、医療機関の負担増大や、社会全体のセーフティネットの崩壊につながる深刻な事態です。
必要な人に必要なサービスが届かない社会、それがケアマネ不足がもたらす最も恐ろしい未来の姿なのです。
【深刻】ケアマネ不足が加速…「介護難民」時代が到来?7年連続で居宅介護支援事業者が減少💦「ケアマネを大切にしなかった結果」が今#shorts#ケ… https://t.co/zse2cqHcwx @YouTubeより
— ケアマネ笑顔交流チャンネル (@care7mane_nico) August 2, 2025
家族の介護負担が極限まで増大
ケアマネジャーは、利用者本人だけでなく、その家族にとっても重要な支えです。
主任ケアマネ不足でサービスの質が低下
ケアマネジャーの中でも、特に豊富な経験と高い専門性を持つ「主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)」の不足は、介護サービス全体の質の低下に直結する深刻な問題です。
【ケアマネ不足】どうすればいい?国と私たちにできる対策
国が進める処遇改善と業務効率化の動き
深刻化するケアマネ不足に対し、国もようやく重い腰を上げ始めています。
厚生労働省は、2027年度の介護保険制度改正に向け、ケアマネジャーの処遇改善を最優先課題として検討することを表明しました。
2027年度の介護保険制度改正では、ケアマネジャー不足をはじめとする介護現場の危機を打開するため、以下の5つの柱を中心に制度設計が進められています。
- 処遇改善の拡大
- 居宅介護支援事業所に対する「処遇改善加算」の適用範囲を拡大し、ケアマネジャーの基本報酬を引き上げ
- 夜間・休日対応や重症者対応など、専門性・リスクの高い業務への加算要件を新設
- 資格制度の柔軟化
- 受験資格の実務経験要件(5年900日)を段階的に緩和
- 資格更新研修のオンライン講習化・時間短縮化と受講料の公費補助を制度化
- 業務効率化・ICT活用推進
- AI・クラウド型ケアプラン作成支援システムの国庫補助を創設
- 電子署名によるケアプラン交付やモニタリング報告を標準化し、書類負担を大幅に軽減
- 地域間連携・人材配置支援
- 過疎地・離島向け「遠隔ケアマネ支援加算」の導入
- 複数市町村をまたがる兼務・非常勤配置を可能とし、地域包括ケアの空白を解消
- 人材確保・育成強化
- 潜在ケアマネの復職支援プログラム(eラーニング+OJT)を全国展開
- 大学生・専門学校生への奨学金返済支援拡充とインターンシップ推進
上記による、これまで対象外とされてきた処遇改善加算の適用拡大や、基本報酬の引き上げなどが議論されています。また、各政党の議員連盟からも、賃上げや負担軽減を政府に求める声が上がっており、政治的な後押しも強まっています。同時に、業務負担を軽減するための取り組みも進められています。AIを活用したケアプラン作成支援システムの開発や、オンラインでの情報共有プラットフォームの導入など、ICTを活用した業務効率化が推進されています。これらの対策が実を結び、ケアマネが専門性を発揮できる魅力的な職業となるか、今後の動向が注目されます。
 杉山 制空
杉山 制空それでも、現時点での各政党の介護業界改善の政策は微妙です。こちら側は、ただ期待するだけは避けて、強く訴え続けていく姿勢を持ちましょう。
事業所に求められるICT導入と働き方改革
国の制度改正を待つだけでなく、個々の介護事業所レベルでの取り組みも不可欠です。
ケアマネの負担を軽減し、働きやすい環境を整えるためには、ICT(情報通信技術)の積極的な導入が鍵となります。
例えば、タブレット端末を導入して訪問先でも記録を入力できるようにしたり、チャットツールで多職種間の情報共有をスムーズにしたりすることで、移動時間や書類作成にかかる時間を大幅に削減できます。
また、事務作業を専門に行うスタッフを配置し、ケアマネが本来の相談援助業務に集中できる体制を整えることも有効です。さらに、フレックスタイム制の導入やテレワークの許可など、個々の事情に合わせた柔軟な働き方を認めることも、人材の定着につながるでしょう。
事業所が率先して働き方改革を進めることが、ケアマネ不足解消への大きな一歩となります。
私たちがケアマネと良好な関係を築くコツ
ケアマネ不足という大きな問題に対し、私たち利用者や家族にもできることがあります。
利用者とケアマネが信頼関係に基づき、チームとして介護に取り組むことができれば、サービスの質は向上し、ケアマネ自身のやりがいにも繋がります。それが巡り巡って、地域全体の介護の質を守ることになるのです。
【総括】ケアマネ不足の現状
最後までお読みいただき、ありがとうございます。ケアマネジャー不足というテーマは、少し暗い気持ちになったかもしれません。しかし、この問題から目を背けることは、あなた自身やあなたの大切な家族の未来から目を背けることと同じです。
2040年に8.3万人が不足するという現実は、私たちに「これまでの当たり前は、もう続かない」という事実を突きつけています。
だからこそ、今、知ることが重要なのです。なぜケアマネが減っているのか、その背景にある彼らの苦悩を知ること。そして、私たちに何ができるのかを考えること。それは、難しいことではありません。
例えば、担当のケアマネさんに「いつもありがとうございます」と一言伝えること。相談する内容を事前にメモしておくこと。そんな小さな配慮の積み重ねが、疲弊する現場の大きな支えになります。
国や事業所の改革はもちろん重要ですが、最終的に介護の現場を温かいものにするのは、人と人との関係性です。
この記事が、あなたがケアマネジャーという仕事への理解を深め、より良い関係を築くための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
あなたの行動が、日本の介護の未来を少しだけ明るくする力を持っていることを、忘れないでください。